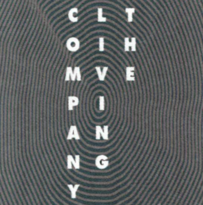-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
自由民権運動の父――板垣退助
長州藩・薩摩藩に次ぐ雄藩として多くの人材を輩出した土佐藩は、日本の立憲政治の樹立に尽力した二人の「父」を輩出しています。
一人は、「板垣死すとも自由は死せず」の名言を残した板垣退助(1837~1919)です。
 板垣退助(1837~1919)
板垣退助(1837~1919)
幕末の動乱期、板垣は討幕派として活躍し、維新後は参議となりますが、征韓論に敗れて下野します。1874年(明治7)、江藤新平(しんぺい)、後藤象二郎(しょうじろう)らと民撰議院設立建白書を政府に提出すると、高知に立志社を設立し、先頭に立って自由民権運動を推進します。
1881年(明治14)には自由党を結成、総理として全国を遊説して周り党勢拡大に努めますが、1882年(明治15)四月、岐阜で暴漢に襲われます。この時に叫んだといわれるのが冒頭の名言です。そして、これが自由民権運動の合言葉となり、板垣は「自由民権運動の父」と称されることとなりました。
板垣は、自由党をいったん解散した後、立憲自由党を結党して総裁となり、第二次伊藤博文内閣の内務大臣に指名されます。さらに、自由党と進歩党が合流して憲政党が結成されると、大隈重信と共に首領に推され、最初の政党内閣といわれる第一次大隈重信内閣の内務大臣に迎えられました。
東京都青梅市の釜の淵公園には、三多摩自由党の有志が党首板垣退助を対岸の河原に招いて鮎漁を楽しんだことを記念して建てられた銅像があります。その台座にある銘には、「自由民権確立のためその生涯を捧げ、今なお憲政の父と仰がるる板垣退助先生かつてこの地に遊ぶ……」と書かれています。
「憲政の父」とも称された板垣は、自由民権運動と共に近代日本の政界の中枢にあって、大日本帝国憲法や国会の開設に大きな影響を与えたことから、日本の立憲政治の礎となる活動を行ったといえます。
もう一人、土佐出身で立憲政治に尽力したのが片岡健吉(けんきち・1843~1903)です。
立志社創設に参加して議長、社長を務め、自由党でも板垣退助の片腕として自由民権運動を後押しし、自由党土佐派の領袖として重きをなします。1890年(明治23)の第一回総選挙から衆議院議員に連続八回当選し、1898年(明治31)から死去するまで衆議院議長を務めました。
高知県議会議事堂(高知市丸ノ内)前に立つ、初代高知県議会議長だった片岡の銅像の銘には、次のように書かれています。
「片岡健吉先生は天保十四年高知城下中島町に誕生。明治維新の創業に参加して功あり。また、欧米を視察して得る所少なからず。後率先して立志社を創立し立憲政治の確立に挺身した明治十二年高知県会初代議長に就任さらに衆議院議長となり上下の信望を集めた。明治三十六年歿享歳六十一。乃ち憲政の恩人として茲に像を再建し不滅の功績を讃えるものである」
片岡が「立憲政治の父」と称されるゆえんです。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)