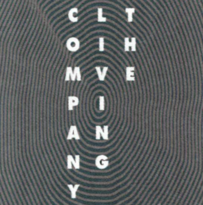日本議会政治の父――尾崎行雄
東京都千代田区永田町の国会議事堂からほど近い「憲政記念館」の入口に、「憲政の神様」と称せられた男の銅像が据えられています。内閣総理大臣も政党総裁も未経験の、一介の衆議院議員ですが、1890年(明治23)に実施された第一回総選挙で衆議院議員に選出されて以後、連続二五回当選という世界議会史上の記録を打ち立てたこの人物は、尾崎行雄(1858~1954)。「立憲政治を守る」を信条に活躍した政治家です。
「政治家たるものは、国民の幸福にならぬようなことは、それが法律であっても、なんであっても、服従してはならない。……政治家にとっては、良心に従って行動することが、複雑な政治問題に対処する最良の方法であり、良心とは自分の心のことである」
 尾崎行雄(1858~1954)
尾崎行雄(1858~1954)
この言葉のとおり、軍国主義支配が進むなか、尾崎は平和の信念を曲げず国に警告し続け、晩年は「世界連邦」という理想を掲げました。
1954年(昭和29)10月、尾崎が96年の生涯を閉じた時、最年長の衆議院議員による追悼演説が行われました。
「君は清廉孤高、清貧に甘んじ、名利を求めない政治家として知られているのであります。……思うに、尾崎君の政治家としての最も敬服すべき点は、その操守の純正なる点にあり、しかも一貫して終生その理想に精進せられたことであります。君は常に民主主義に立脚し、自由と人権とを尊重し、民意を体して公論の伸長に努め、憲政を擁護して議会政治を守ることをもって使命とし、終生変わることがなかったのであります」
1890年(明治23)の第一回帝国議会から大正、昭和の63年余を国選議員として日本の議会制度の発展と共に歩んだ尾崎の人生は、「日本議会政治の父」とも「憲政の父」とも呼ばれるのにふさわしいものでした。
戦後日本の父――吉田茂と片山哲
第二次世界大戦後の日本の復興に尽力した政治家の筆頭は、間違いなく吉田茂(1878~1967)でしょう。
戦前の吉田は、東京帝国大学卒業後、外務省で各国の大使を歴任しますが、駐米大使の時に日独伊三国同盟に反対して職を追われます。戦後は7年余、5度にわたり吉田内閣を組閣し、新憲法の発布、農地改革、教育基本法や労働三法の制定など、戦後の諸改革を処理します。その総決算として、吉田が政治生命をかけたのが、サンフランシスコ平和条約および日米安全保障条約の締結だといわれています。
焼け野原となった国土と疲弊した経済を立て直す日本にとって、戦勝国との和平は最重要課題でした。国内世論は、ソ連など共産圏諸国を含めた全連合国との間に条約締結すべしとする全面講和論と、共産圏を除いた諸国間のみで条約締結すべしとする部分講和(単独講和)論とが激しく対立していました。
そのようななかで、吉田は単独講和に踏み切ります。軽軍備・経済重視で、後に吉田ドクトリンと称される吉田の政治・外交スタイルは、日本人の生活維持、日本の経済復興に大きく貢献しました。吉田が「戦後復興の父」と呼ばれるゆえんです。
吉田の後を受け、新憲法下で初の内閣総理大臣となったのが社会党の片山哲(てつ・1887~1978)です。総選挙で社会党が第一党となり、日本初の社会党首班内閣が誕生。在任期間こそ10カ月余と短命でしたが、新憲法の運用という未知の局面において組閣されたこの内閣は、民法・刑法の改正、警察改革、労働省設置などを進めます。また、全国民が飢えに苦しむ時代、「一億総悩みという状態で、片山内閣は国民に安心感を与え、……片山哲という方が、あの混乱期の昭和22・23年、日本の歴史のなかでなされた功績というもの、これは本当に高く評価しても、高く評価しすぎるということがない」と、後の首相福田赳夫は述べています。
片山は敬虔なクリスチャンとしても知られ、キリスト教的人権思想と社会民主主義の融合を実践した人物でもあり、政界引退後は、護憲運動、世界平和運動、政界浄化運動に尽力します。1978年(昭和53)、91年の生涯を閉じる前の病床にあって「平和を! 平和を!」と繰り返し口にしたといいます。幅広く社会運動をしながら、党派を超えて愛された政治家片山哲は、「平和の父」と呼ばれています。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)