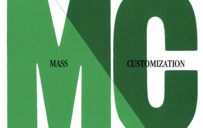五人の民法の父たち
江藤新平からフランス民法典の翻訳を、また参議・副島種臣(そえじまたねおみ)からフランス刑法典の翻訳を命じられた箕作麟祥(みつくりりんしょう)は、5年の歳月をかけてこれらの諸法典を全訳した『仏蘭西法律書』(1874年)を刊行し、近代法典を初めて日本人に紹介します。これが当時の司法官の唯一の手本になり、日本における近代的法制度の整備と法典編纂に多大な影響を与えました。その功績により、箕作は「法律の元祖」と評されています。
箕作は、1873年(明6)に来日したボアソナードの下で各法典の編纂に従事し、民法や商法の編纂委員を務めます。1880年(明治13)には刑法ならびに治罪法が公布され、1882年に無事施行されます。問題が生じたのは民法典(旧民法)です。1890(明23)に公布されたものの、ボアソナードを中心に起草されたそれはわが国の実情に合わないと反対する施行延期派と、断行派の間に論争が起こり、当初予定していた1893年(明治26)の施行を断念せざるをえない事態となるのです。
延期派の穂ほ 積八束(ほづみやつか)は、『民法出テテ忠孝亡フ』と題した論文を発表し、日本の家父長制度を否定する「婚姻を基調とした家族法」を激しく攻撃します。八束は、日本の国家社会の基礎としての「家」の概念を明らかにし、これを国家にまで拡大して、忠孝一致・忠君愛国を国家道徳の中核に据えた法律家です。彼は、個人を国家や家庭の単位と見なす民法は、わが国固有の家制を破壊し、いずれ天皇制国家が破滅すると考えたのです。
そこで法典調査会が再び設置され、八束の実兄で帝国大学教授の穂積陳重(のぶしげ)(1856~1926)や梅謙次郎(けんじろう・1860~1910)らが起草委員となり、これまでのフランス民法からドイツ民法に重点を置いた明治民法典が完成し、1898年(明31)7月16日に施行されます。これが、わが国最初の体系的な民法典です。制定に携わった梅と陳重は、「日本民法の父」と称されています。
梅は出雲国宍道湖畔松江灘町(現島根県松江市)出身、幼少より英才のほまれ高く、その麒麟児ぶりは「梅の小坊さんは日朗様(日蓮)の再来だ」といわれ、12歳で藩主の前で日本外史を講じて褒賞されたといわれます。東京外国語学校(現東京外国語大学)、司法省法学校を卒業後、フランスのリヨン大学に学び、『和解論』によってドクトゥール・アン・ドロワ(法学博士)の学位を、リヨン市からヴェルメイユ賞碑を授与され名声を博し、帰国後帝国大学法科大学教授を務めるかたわら、民法・商法の成立に尽くし、「空前絶後の立法家」「先天的な法律家」と称されました。
一方、伊予国宇和島(現愛媛県宇和島市)出身の陳重は、大学南校(現東京大学)で法律を学んだ後、イギリスとドイツに留学し、1888年(明治21)5月7日、箕作麟祥、田尻稲次郎、菊地武夫、鳩山和夫と共に、わが国最初の法学博士の学位を受けました。日本初の民法学者として東京大学法学部の基礎を確立した彼は、大津事件に際し、法律学の立場から、「政府の圧力に屈せず、法に照らして裁判なされるよう」と進言して同郷の児島惟謙を支えました。
父を受け継いで「穂積民法」を確立した長男・重遠
この陳重の民法を受け継ぎ、「穂積民法」を確立したのが、長男の穂積重遠(しげとお・1883~1951)です。「民法のなかで育ったようなものだ」とみずからが語るように、父陳重から学問上多大なる影響を受けた重遠は、東京帝国大学法学部を卒業後、法社会学の先駆者として、判例・史料および実態を重視し、旧慣を重んじつつ将来に適応する規定を置く方針で家族法理論を構築しました。家族法研究で業績を示した重遠は、「日本家族法の父」と称されています。
家族法の分野で多大な功績を残した重遠は、法と道徳の問題を追究し、「法律上の義務をつくしただけではいまだ道徳上の義務をつくしたことにはならず。また法律上の義務を履行しないことはすでに道徳上の悪である」と結論づけています。日本の家族法学はもちろん、法学界にあまねく影響を与えた重遠の広い視野と社会的関心、ヒューマニズムは、母歌子の影響が大きかったのでしょう。
渋沢栄一の長女である歌子は、他者の人格を尊重する慈悲深い面を持つ反面、常に新しい修養を怠らない厳しい人だったと重遠は述懐しています。重遠が高等文官試験に合格した時の歌子の日記には、「予備も筆記も口述も皆第一番にて及第合格なしたる由なり。同人学才抜群なるを喜ぶと共に、慢心を生じてはと取越苦労をなし、帰宅後よくよく重遠に心得方を申聞す」と記されてあることから、いわゆる教育ママであったようです。この母の下、恵まれた家庭環境に育った重遠は、法律の民衆化、社会化に尽力し、平易な法律文を書くことを心がけたそうです。国民が等しく司法制度の保護を受けられるようにと、少額裁判所、家庭裁判所、法律扶助会の制度設置をはじめ、児童虐待防止法(1933年4月)の制定にも尽力しました。
重遠は、イギリスで社会事業と社会教育を目の当たりにして、「結局法律も一つの社会事業であるし、本当に法律が行われるには社会教育に待たねばならぬ」と実感したと述べています。その言葉どおり、1923年(大正12)の関東大震災後、東京帝国大学の学生による被災者救援活動を末弘厳太郎(すえひろいずたろう)教授と共に指導し、これを母体とする東京帝国大学セツルメントを、設立から閉鎖までの間(1924~1938年)、援助しました。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)