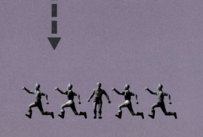-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
司法制度、近代法、司法権独立の父
明治新政府の指導者たちは、日本の近代化に向けてさまざまな分野で力を尽くしますが、旧幕府の負の遺産に頭を悩まされます。なかでも不平等条約は、欧米列強国がこれを維持する口実として、法制が未整備の日本は近代国家となりえないことを挙げたため、明治政府にとって、司法制度を整え、近代法を確立することが急務でした。
不平等条約が完全に撤廃されるのは1911年(明治44)のことです。日本は、開国以来五十余年、明治時代(明治時代は45年間)をかけて、不平等条約の解消にこぎつけました。その第一の功績者は、初代司法卿として司法制度の基礎を固めた江藤新平(しんぺい・1834~1874)です。
 江藤新平(1834~1874)
江藤新平(1834~1874)
佐賀藩出身の江藤は、新政府に出仕して頭角を現し、司法卿や参議を歴任するなかで、司法制度、学制、警察制度などの近代化政策を推進します。権限があいまいな当時の省庁にあって、独立機関としての司法台の設立と司法権の独立を主張した江藤が目指したのは、立法・行政・司法がそれぞれ独立する「三権分立」です。そのため、司法職務の制定、裁判所・検察機関の創設、弁護士・公証人の導入、民法の編纂に努めたのです。このことから、江藤はわが国近代司法体制の生みの親として、「近代日本司法制度の父」と称されます。
江藤の功績とその歴史的意義は、それにとどまりません。明治維新は、士農工商の封建的身分制度を撤廃し、「四民平等」の近代的社会関係によって、全国民に等しく人間としての権利を認めることに非常に大きな意義がありました。日本の歴史上、初めて人権(人民の権利)が確認され、「人間の解放」と「人権の確立」がなされたわけです。明治新政府において、これを推進した江藤の功績は計り知れません。
「国の富強の元は国民の安堵にあり、安堵の元は国民に位置を正すにあり」
江藤はこの言葉どおり、民生安定と人権確保のための優れた制度を設計しました。前述の司法制度の整備は、目的ではなく、人権確立のための手段だったのです。
幕末期の佐賀藩で、一介の書生だった23歳の江藤は、1856年(安政3)、『図と 海策(かいさく)』という長文の時事意見書を執筆します。当時は外国人を排撃せよとの攘夷論が主流でしたが、江藤は、海外との通商で西洋文明に学び、経済、軍事の近代化を図る積極的開国論を主張します。同時代の島津斉彬や橋本左内らと同様に真の攘夷の意味を認識していたわけですが、江藤で際立つのは、民生尊重を主張している点です。それは、攘夷戦争が農民の困窮と荒廃を引き起こすと指摘し、海外との通商を推奨することで生活必需品を行き渡らせ、民生向上に役立てようというもので、これは江藤が生涯を通して貫いた信念です。
1872年(明治5)4月、初代司法卿に就任した江藤は、司法の独立を宣言します。そして、公正な裁判の実現を図り、みずからの目指す司法のあり方を「司法省誓約」五カ条にまとめています。
「一、方正廉直にして職掌を奉じ、民の司直たるべき事
一、律法を遵守し、人民の権利を保護すべき事……」
司法は人民の権利を保護する制度であり、民のためにある。これを理想に掲げ人間解放と人権確立を推進した江藤は、「人権の父」とも呼ばれています。
しかし、江藤は、志半ばにして41年の生涯を閉じました。明治六年の政変で下野した後、佐賀の乱に巻き込まれ、皮肉にもみずからが整備した警察に追われ、みずからが整備した近代司法制度を無視した「非道な裁判」により断罪されるのです。処刑前、「ただ皇天后土の わが心を知るあるのみ」と三度高唱したといわれています。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)