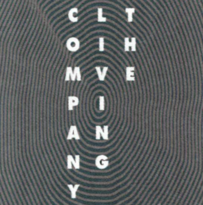殖産興業の父――前田正名
明治政府の殖産興業政策の指導者・大久保利通の右腕として政策遂行を助け、大久保没後、それを継承した人物として、松方正義、品川弥二郎、前田正名(まさな・1850~1921)の三名がよく知られています。松方は後に大蔵省に転じ財政行政で辣腕を振るい、品川は産業組合法の立法化に尽力し、殖産興業政策とは一線を画した功績により、それぞれ「近代日本財政の父」「農業協同組合の父」と呼ばれます(第六回「資本主義の父」、第七回「法曹界の父」参照)。
三人のなかでただ一人、一貫して殖産興業政策の推進に当たったのが薩摩藩出身の前田です。前田は、9歳で緒方洪庵門下の八木称平に師事して洋学を学びながら、師が行っていた琉球密貿易を手伝ったといわれます。1865年(慶応元)、長崎の何礼之(がのりゆき)の語学塾に藩費留学した時、イギリス帰りで薩摩藩外国掛として長崎に赴任してきた五代友厚から大きな影響を受けたと、後年前田は語っています。
薩摩藩イギリス密航留学生(第四回参照)の選抜に漏れた前田ですが、洋行を諦めきれず、1869年(明治2)、兄献吉らと『和訳英辞書』を出版し、念願のフランス留学を果たします。「薩摩辞書」といわれたこの辞書は、明治20年頃まで6回も復刻され、日本人の英語学習に大きく貢献しました。
留学中、各国の経済事情を視察し、農業・産業政策を研究して7年ぶりに帰国した前田は、すぐさま内務卿・大久保にパリ万国博覧会への参加を進言します。そして、これが認められると博覧会事務官として再びフランスに渡り、1879年(明治12)、大蔵省御用掛となり帰国します。この間、大久保が暗殺されますが、前田は、「将来の国家の大目的は、ひたすら殖産興業の任務に献身すべきである」という大久保の遺志を継いで殖産興業政策の一端を担うべく、その後の人生を歩んでいきます。
1881年(明治14)、大蔵省ならびに農商務省の大書記官に就任し、1884年(明治17)には国内産業の実情を調査して、殖産興業のための報告書『興業意見』全三〇巻を編纂します。これは、松方財政による不況下の各産業界の現況と、資本供給、法規整備、地方産業の優先的近代化、政府保護の必要性などの政策をまとめたものです。現在の産業白書の原点ともいうべきもので、経済史研究の基本文献とされています。
しかし、これによって、地方産業の犠牲のうえに軍備を拡張し、政商資本に手厚い保護を加える松方財政グループと対立し、この抗争に敗れた前田は一時非職となります。数年後、山梨県知事として復帰し、農商務相工務局長、東京農林学校長、農商務次官などを歴任するかたわら、全国規模の農事調査を実施しますが、今度は農商務大臣の陸奥宗光と対立し、再び下野します。かつて長崎の語学塾で机を並べ、同門のなかでも特に親しかった二人が、政府高官として対立することになるとは、人生とはまことに不思議なものです。
官を辞してからは、全国をくまなく行脚して、生糸・茶・織物などの輸出産業を中心に地方在来産業の育成と振興に生涯を捧げた前田は、「殖産興業の父」「明治産業の父」と称されています。
「前田行脚」「前田実業」「布衣(ほい・江戸時代の旗本の服装)の宰相」「無冠の農相」と呼ばれるほど、全国津々浦々を行脚し地方産業を振興した前田の所信は、「今日の急務は国是・県是・郡是・村是を定むるにあり」というものでした。これが地方産業の担い手たちを大いに発奮させ、町村是(農村計画・地域計画)運動の潮流を生むのです。
一例を挙げると、これに強く共感した波多野鶴吉(はたのつるきち)は、何鹿(いかるが)郡(現京都府綾部市)の発展のためには、農家に養蚕を奨励することが「郡是(郡の急務)」であると考えます。そして、蚕よう糸さん業振興を目的とする「郡是製糸(現グンゼ)」を設立し、日本を代表する繊維メーカーとして発展するのです。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)