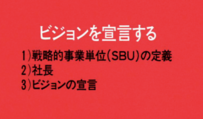第2に、そうした社会の変化が、ほとんどの場合は漸進的にしか起きない「静かな変化」であるということ。大震災のようなメガトン級の出来事であれば即時の対応が余儀なくされる。それが本当に効果的かどうかは別にして、意思決定が強制され、具体的なアクションがとられる。しかし、世の中の変化の多くは、徐々にしか進まない。
「少子高齢化」がそのいい例だ。少子高齢化が進むということ、将来の日本の人口構成が世上言われているような歴史的にも経験したことがないような高齢者への偏りを見せることは99%間違いない事実である。この間違いない事実からして、税と社会保障の一体改革が「急務」となる。そんなことは誰でもわかっている。それが証拠に、10年前から(いや、20年前かな)同じ話を繰り返してきた。だれもが分かっている傾向は、厳密な意味では「環境変化」ではない。そうした大げさな言葉を持ち出すのも恥ずかしくなるような、既定の事実にすぎない。しかし、それがいつまでたっても「将来の話」なので、なかなかアクションが進まない。
第3に、「構造」のもう一つの特徴として、やたらと多くのものごとが絡んでいるということがある。税と社会保障の一体改革とか「国から地方へ」といった国政レベルの話になると、日本の隅から隅までずずずいーと、何から何までが絡みまくり、しがらみまくっている。だから、誰にとっても最適最善の「構造」というのは、定義からしてあり得ない。多くの人が喜べば、それと同じぐらい多くの人が嘆き悲しみ怒りを表明する。
他にもいくつも理由はあるだろうが、この3点だけを考えても、構造改革は難しい仕事であるのは間違いない。いまのところはわりと歓迎ムードでも、そのうち安倍政権に対する批判はバンバン出てくるだろう。なんといっても、歴史上ほとんどの人ができなかった構造改革を目標にしているのだから、そう簡単にうまくいくわけがない。ようするに「抜本的な構造改革!」といった瞬間、「それを言っちゃあおしまいよ……」という話なのだ。
だとすればどうしたらいいのか。構造を構造そのものとして改革しようとする、そこにそもそもの問題があるのではないか。構造改革を「構造改革」としてやらなければいい、そうすれば結果的に構造改革が進む、というのが僕の見解だ。なんだか禅問答じみている話だが、この意味するところについてはまた次回。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)