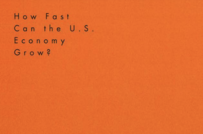キーワード③relivancy
雑誌やラジオが最先端メディアになれるチャンスだってある?
日本の広告コミュニケーションはリーチとフリケンシーという概念で評価されてきました。リーチは到達数ですから新聞の部数とかテレビの視聴率ですね。フリーケンシーは頻度です。ですから、2億円の投資をすれば3000万人の人が週に○回見るCMを流せるみたいな感じでコミュニケーションの価値を測ってきたわけです。もちろん、リーチとフリケンシーの概念は今でも重要なのですが、情報の伝達回路があまりにも多様になった今、レリヴァンシーという概念の重要度が増してくると思っています。
英語をそのまま訳すと「関連性」という意味になるわけですが、「このメッセージは自分のためのメッセージだ」というように、情報の受け手がどれくらい自分と関係があることがらとしてメッセージを受け取っているのかという指標です。どれくらい積極的に情報を受け取ってもらっているのか、その深さと解釈してもいいと思います。
リニアに流れるテレビからの情報は想定外の出会いを受け手にもたらしますが、わざわざ検索して訪ねるウエブサイトや、なにか面白い発見があるかもと期待して再生するYOUTUBEの動画の方がレリヴァンシー度は高いかもしれません。後者は時間を使ってがんばって、見てくれるわけですから。これからコミュニケーションを設計する人は、作るアウトプットが広告だろうが、メディアコンテンツだろうが、商品開発だろうがこのレリヴァンシーを意識せざるえなくなるでしょう。
レリヴァンシーは現代のコミュニケーション設計の必須アイテムなわけですが、実はトラディショナルなメディアと言われる雑誌やラジオはレリヴァンシー度がかなり高い媒体です。「『BRUTUS』には自分向けの情報が載っている」と読者は思っていますし、「ライムスター宇多丸さんの番組はまさにおれにぴったりのラジオだ」とリスナーは感じています。雑誌やラジオは特定のターゲットをつかまえることができるレリヴァンシー度の高い、そしてそのチカラによってコミュニティを形成する「元祖ソーシャルメディア」なのです。
PRパーソンはそんな媒体で記事を書いてもらったり、番組にしてもらうことを目指すのですが、それはまさにクライアントのためにその媒体が持っているレリヴァンシーを拝借する作業をしているわけです。そのチカラがあるから読者は時には必死に情報を得ようとしてくれるわけですから。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)