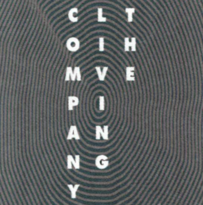PR=パブリシティではない
嶋:日本だとPRの役割がパブリシティになってしまっていますよね。
井口:本来PRはカンヌの審査基準でも言われるように、社会的な態度変容をいかに起こすかが仕事です。パブリシティはそれを担う一部のソリューションにすぎません。
嶋:広告業界の多くの人たちが、ソーシャルメディア時代にPRの重要性を認識し始めているけれど、まだそこが誤解されてる部分がありますよね。PRにとってパブリシティを獲得することは態度変容のための大きなドライブになるわけだけど、別に国際会議を開いても、学会を作っても、イベントを開催しても、そして広告をつくっても態度変容のための手段としてはかまわないわけですよね。クライアントもPR会社もついついPRの成果をパブリシティの広告換算に求めてしまうのもよくないですよね。
井口:カンヌではパブリシティをすごいたくさん獲得しましたっていうだけの仕事は評価されません。PR業界のアワードでは、もうそういったメディアカバレッジをエントリーの書類に書いてくるな、とまで言われています。パブリシティを広告換算して価値を決めようというのは、結局リーチに価値を置いているからで、すなわち広告の代替手段としてしか理解されていないわけですよね。でも、その情報が届けばいいということではないんですよ。そのパブリシティに触れた結果、生活者がどうなったかってことが重要なわけで、量よりもその中身こそが大切なんです。
嶋:受賞作の大半はPR活動と広告活動がインテグレートされたものでした。
井口:そう、PRは広告よりもより上位概念。広告活動、プロモーション活動とより連動して、全体をPRが牽引するべきだと思います。
嶋:実際、仕事を進めるうえでPRと広告の連携って可能なんですか?
井口:企業の組織として、広報と宣伝・マーケティングセクションが縦割りになっているところが一番の課題で、本来二つの活動が連動して、情報連携がされたほうがいいんですけど。まずは、そういう成功事例を小さなケースからでも作っていってより大きな組織にもそのスタイルを啓発し、定着させたいです。実際、大手の企業さんにPRの本来的役割や戦略PRのための理想の体制などを説明すると現場の方々はほぼ全員「なるほど」と理解してくれますが、最後に言われるのは「でもうちの組織を変えるには相当の力業が必要で・・・」といったあきらめの言葉だったりして・・・。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)