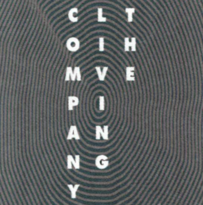嶋:そうですよね。とくに、コンプレックス消費の商品だとソーシャルな場で意見をいうことを躊躇する人もいるかと。
大高:そういうときは、アクティブシニアが興味をもちそうなテーマでコミュニティを立ち上げます。その中で入れ歯の話を自然な流れで聞いていきます。1つ上のレイヤーの概念から入るんです。
嶋:なるほど。質問の仕方、あるいは対話の仕方かもしれませんが、そこにも秘密がある。
大高:はい、これが欲しいとか、明確に自分の欲しいものを話せる人ってそんなにいないわけです。優れたファシリテーターはその発言の中から本当はこの人はこんなことを望んでいるのではという心理を解釈しながら対話を設計していくんです。
嶋:一般的に調査は、フラットに結果だけを見ることが重視されますが。
大高:もちろん、既存の調査方法もいいところはたくさんあります。ソーシャルメディア上では対話によって、人々の深層心理をより引き出すことができます。ファシリテーターが言語化できない欲望を掘り当てるんです。
調査がブランディングになる
嶋:既存の調査、例えばグループインタビューも対話によって生活者の気持ちを引き出すと思うんですが。
大高:既存の調査は、調査側が対象者の属性や数を選べるし、それをクローズドな場所でやっていた。グループインタビューに参加した人は何の企業の何の商品のために呼ばれたのかもわからない。その調査結果を企業が製品開発やキャンペーンにどういかしたかもクローズドです。
嶋:もちろん、企業名をあかさないで話を聞くことで、バイアスがかからないで自由な意見を言ってもらうというメリットもあると思うんですが、VoiceVisionはそれをオープンにやるということですか。
大高:はい、これまでクローズドだった調査をオープンな場で展開するのが私たちの手法のもう1つの特徴だと思います。最初から、「この企業のこの商品の改良のために皆さんの意見を聞きたい」とか、「この商品のキャンペーンのプレミアムグッズを開発するために意見をお聞きしたい」とか最初から正直に全てを話すんです。
嶋:参加する人も企業側が選択できないということですよね。ソーシャルな空間にいる人たちが自由意志で参加するわけですね。企業にとってはある意味、意見をきく人のコントロールが効かないってことにもなる。
大高:そうです。でも、オープンな空間で調査をやることで、参加者に「自分がその商品を良くすることに参加した」という満足感を持っていただける。そして発売前から多くの人の目に触れて、調査自体が企業のブランディングになるというメリットがあります。
嶋:調査することで企業ファンを増やしていく。おもしろいです。でも、企業のマーケティング活動にそんなに積極的に参加してくれるものなのでしょうか。一般の生活者が。
大高:ソーシャルな空間で大事なことは世の中がどう良くなるかって視点です。ですから、企業も自社製品で、老後がどう楽しくなるかとか、夫婦の時間がどう楽しくなるかとか、子育ての問題がどう解決されるかとか、そういう視点で生活者と向き合うことが大事。ファシリテーターもそういう文脈で会話をつくっていきます。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)