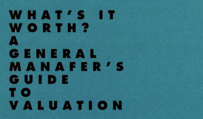ターゲット、サンプルって変なコトバ
大高:わたしはこういう企業と生活者のソーシャル空間での関係を「共創」と呼んでいます。わたしたちが提供するファシリテーションを通じて、企業と生活者が、社会をよりよくするアイデアを生み出す。そういう価値を提供する会社をめざします。
嶋:今年のカンヌの作品をみて、うちの木村が挙げたキーワードのひとつが「ソーシャルグッド」で、自分の挙げたキーワードが「リアクション芸」。まさに、「共創」という概念はその両方を体現していますね。
大高:自分自身への反省として、これまで生活者を「ターゲット」って呼んだり、調査対象者を「サンプル」って呼んだり、当たり前のように使っていました。でも、本当の共創を目指すならそれは少し違和感があるなって最近思うようになりました。
嶋:ちょっと、失礼なんじゃないかってことですね(笑)。そういう意味で、VoiceVisionのやり方は今までとちがう企業と生活者の関係をつくりますね。
食べログのレビュワーさんや、NAVERまとめのまとめ人など、生活者サイドとプラットフォームが大高さんのいうように「共創」するビジネスモデルがたしかに注目されていますね。
大高:そういうプラットフォームになれるようにしたいと思っています。
嶋:VoiceVisionのやり方で成果を出した仕事の事例って教えていただけますか?
大高:例えば、サントリーのプレミアムビール、ザ・プレミアム・モルツの店頭景品開発をお手伝いしました。雑誌「Mart(マート)」の読者との共創だったのですが、いきなり店頭景品のアイディアを聞くのではなく、展開の時期にからめて「いい夫婦の日」をテーマに設定して、読者の考える「いい夫婦」についてディスカッションをしました。その中で読者にとってのいい夫婦は「体験を共有できる夫婦」というインサイトを発掘して、その結果「豊かな食卓体験を写すための『デジカメ三脚』」というアイディアにたどり着きました。通常ビールの店頭景品と言えばビールの味わいを楽しむためのビアカップなどが多いと思うのですが、味より「ビールのある幸せな時間をカタチにする」という今までにないユニークな店頭景品になりました。
嶋:夫婦の時間を楽しむためのビールというコンセプトまでたどりつけても、なかなかその時使う一番便利なグッズを探り当てるのは大変かもしれません。そういう意味ではユーザーが本当に欲しいものをうまく掘り当てている。ファシリテーターの腕によるところが大きいですね。
大高:はい、このような実施事例を次々作って行くと同時に、高いスキルをもったファシリテーターの育成も同時に進めていきたいと思います。
嶋:生活者の声をフィードバックする新しい試みとして期待しています。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)