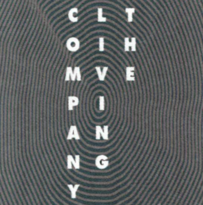仮説を立て検証する、考えに考え抜くアプローチ
それでは、「社会システム・デザイン」のアプローチはどういうものであろうか。これは5つのステップから成り立っている。
まず、取り上げたテーマに内在する中核課題から発生している「悪循環」を発見し、だれもがその通りだと納得する形で明確に定義する。続いて、この状況を大きく変えてしまうような、「悪循環」の単なる裏返しではない「良循環」を工夫し創造する。この「良循環」は現在、世の中に存在していない。当然、「循環」していないから、それを循環させる「駆動エンジン」としてのサブシステムを、費用対効果を勘案しながら3つ程度抽出する。これらのサブシステムに関わる人たちにどういう行動、活動をしてもらいたいかを詳しく説明するため、具体的な行動ステップを書き出していく。そして、わかりにくい場合は、より細かいレベルまで分解し説明するという順序である。言葉で表現することは多いが、政策提言とは違い、「てにをは」をいじってニュアンスや内容を変えてしまうことはできない具体的な行動の集積で出来上がっている。
このように書くと、ステップを踏みながら着実に作業が進行していくように思えてしまうが、実際にはそれはあり得ない。「デザイン」をするということはばらばらの物事を具体的に組み立て統合するという形で課題解決をすることである。しかも、プラモデルを組み立てるように最終の姿が分かっているわけでもない。もっと困ったことに、「社会システム」は建築や自動車のデザインと違って、姿かたちが見えて、触ることができるわけではないのである。
どこにたどり着くのか、たどり着いた姿はどんなのかはまったく分からない。演繹的に考えても、帰納的に思考しても優れた答えにたどり着かない。演繹法は現状に囚われがちで、「経済が長年停滞しているから成長戦略が必要だ」というような「問題の裏返し」的な答えが多く、斬新な発想が出てきにくいのである。また、帰納法の限界は明らかだ。白鳥だけでなく黒鳥もいることが分かったし、白いカラスもたまにはいるのである。
では、どうするか。「デザイン」とは本質的に仮説を立てて検証するアプローチである。英語では「アブダクティブ」なアプローチということもある。これが答えではないかと仮説を立て、それをもとに組み立ててみる。どこかうまくいかない点が見つかる。またもとに戻って新しい仮説を立てて試してみる。また、うまくいかない。また、仮説を立てるということをとことん納得できるまでしつこく、飽きもせず繰り返すのが「デザイン」という作業なのである。
すぐに「良循環」の仮説に飛んではいけない。仮説には優れたものとそうでないものがある。現在めぐっている「悪循環」を徹底的に考え抜くというステップは優れた「良循環」の仮説を作るためにきわめて大事な作業だ。その意味では着実にステップを踏まないといけないのだが、行き詰まりを感じたら、前のステップに帰って、改めて考え直すという作業も必要になるだろう。
すなわち、5つのステップを行ったり来たりしながら繰り返し考えるという忍耐力の必要な作業なのである。完成ということはあり得ない。時間の許す限り考え抜くのである。答えの質は何回仮説を立て、壊したかによると考えてもいいのである。
次回からはステップごとに経験からくるコツも含めて、より詳しく説明する。
(第3回に続く)
【連載バックナンバー】
第1回 「社会システム・デザイン」とは何か







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)