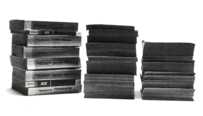-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
プロフェッショナルとして知恵を絞れば絞るほど、消費者のこころを見失ってしまう「差別化の罠」。そのことを、ふとした日常の視点から、思い起こさせてくれる……。ハーバード・ビジネススクールでいま最も注目を集めるヤンミ・ムン教授の処女作『ビジネスで一番、大切なこと』、無料公開連載、第2回。
序
棚に並ぶシリアルは、 どれも同じに見える
近所のスーパーにいる自分の姿を思い浮かべてみよう。今日は食べたことのないシリアルを買ってみたいと思っているが、ハズレはいやだ。さて、どうやって選ぶだろう。ある程度食べ慣れた人であれば、この課題はそれほど難しくないはずだ。
シリアルの置いてある棚に直行し、子供向けや極端に甘そうなものを視界から追い出し、グラノーラや高繊維など気になる数点に絞り込む。レーズン入りや箱が気に入らないものをはじくと、最後の1箱が決まる。よほどのこだわりがない限り、ここまでものの数分もかからないだろう。
このアプローチの賢明さは注目に値する。あなたはマーケターが製品カテゴリーを分析するがごとく、商品を特徴によってサブカテゴリーに分け、さらに下位カテゴリーに分類している。一連の流れるような無意識の行動は、まるでシリアル博士のようだ。
さて、火星人が同じ課題を与えられたとしよう。きっと一筋縄ではいかないはずだ。優れた知性があったとしても、棚に並ぶ無数のシリアルはどれも同じに見えるだろう。
それも仕方のないことだ。プロは違いに注目するが、素人は類似点に目が行く。ざっくりとグルーピングするにも一苦労、ましてや微細な違いをとらえて選別するフィルターなど持っていない。どこからがそのカテゴリーなのか、始まりも終わりもよくわからない。このように、買い物は単なる経験にとどまらず、現象学的にもとらえられる。
他の製品で試してみても結果は同じだろう。歯磨きのクレストとコルゲートの違い、ホンダとトヨタの違いを外国人や子供に説明できるだろうか。私たち夫婦がスポーツ用品チェーンのフットロッカーに行くと、夫はすぐさま店内を自由に歩き回る。一方の私は、このカテゴリーは門外漢。店の片隅で区別のつかない商品の山を呆然と眺めることになる。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)