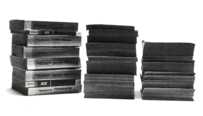-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
競争が過激化すると差別化はより細分化し、結果、消費者から見てほとんど違いが見えなくなる。まるで誰もが没頭しながら、誰も1人勝ちできない「鬼ごっこ」のようだ――。ハーバード・ビジネススクールでいま最も注目を集めるヤンミ・ムン教授の処女作『ビジネスで一番、大切なこと』、無料公開連載、第4回。
自覚はなくても、同じ方向を目指している
子供の頃、牛乳をどんどん飲めと言う先生がいた。なぜだか、牛乳が知性を育てると考えていたようだ。根っからの教育者だったこの先生にとって、知性ほど尊いものはなかった。
時折、生徒が単刀直入に尋ねた。「先生、知性って何ですか」。その都度、答えは違っていた。
「知性とは、赤ちゃんの最初の言葉よ」
「知性とは、今朝、算数の時間にヒョンジュが言った冗談のこと」
「知性とは、3人の兄弟が手をつなぐこと」
「知性とは、黄色」
先生の答えは私たちを混乱させた。30数年が過ぎた今、その理由を考えてみると興味深い。私たちは明快な答えを求めていた。先生はいつも生徒に率直に接してくれていたが、生徒にしてみれば、こういった答えは的外れに思えた。正直、腹立たしくすらあった。
今では私も、この先生に共感するようになっている。その後の年月で、表現という行為は非常にデリケートなものだとわかったからだ。物事の真髄を掘り下げようとすればするほど、適切な言葉を慎重に選ばなくてはならない。幸い言葉は無数にあり、無限の組み合わせが可能だが、相手の想定を超えてしまえば解釈は不可能になる。
大人になって、私はこの両側にいる。ワイン評論家の「どこか刺激的だが知的なアピールがある」「口をつけたときのメントールとユーカリの風味」「後味はアカシア蜜やバニラの香り」といったフレーズを聞いても、何が何だか皆目わからない。新作映画の気どったレビューにもいらだちを感じる。自分の言葉に陶酔していて、読者が本当に知りたいことに答えていない。確かに役者は上手で、照明は大胆だったかもしれない。しかし、映画は面白かったのか。見る価値はあるのか。
毎年私の授業には、200人もの学生が登録する。彼らがどんな学生かと尋ねる人は、賢くてウィットに富み、親切で活発、といった類の答えを期待しているだろう。押しつぶせるほど柔らかいとか、毎日水やりが必要、なんて答えは予想していないはずだ。優れた表現は、受け手にわかる次元で特徴をとらえるものだ。そうでなければ、受け手は描かれた対象を頭の中にうまく位置づけられない。
それは承知の上で、もっと学生たちを鮮やかに表せる的確な表現ができないものかと思う。そして、語彙の問題に立ち戻る。個人や集団のような複雑な対象を描く場合、使える言葉は無限にある。不快、風変わり、辛らつ、か弱い、騒々しい、活発など、ありすぎるぐらいだ。
だからこそ、表現には一定の枠組みが必要なのだ。言葉の使い方に秩序ができるし、何らかの観点を共有すれば、それに則って特徴を描写できる。語彙の多さに翻弄されることもなくなる。
性格検査を例に考えてみよう。様々な測定方法があるが、基本的には支配性(支配的―従属的)と社交性(社交的―非社交的)の2つの尺度で表せる。
この種の測定ツールは、膨大な情報を単純化してくれる。4つか5つの尺度を用いる性格検査は多いが、「非社交的で従属的」といった大雑把な2次元の指標でさえ、面白いほどよく当たる。
もっと具体的に表現することもできるだろうが、基本は同じだ。まっすぐ核心をとらえている。これが優れた描写方法の第1の特徴だ。








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)