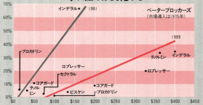-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
本誌2013年11月号(10月10日発売)の特集テーマ「競争優位は持続するか」に合わせ、MBA必読の古典『企業成長の理論[第3版]』の抜粋を紹介する連載第2回。1959年の初版、1980年の第2版を経て、1995年に第3版を発行。その間に何が起きたのか、ペンローズ自身が綴る「第3版への序文」を2回にわたって紹介する。
著者ペンローズによる「第3版への序文」
企業の行動、成長、組織構造、経営上の諸問題について、ながらく多くの議論が行われてきた。最も時期が早くかつ重要な議論の1つは、アルフレッド・マーシャルがPrinciples(『経済学原理』)とIndustry and Trade(『産業と商業』)で展開したものである。1937年、コースは彼の古典的論文‘The Nature of the Firm’(「企業の本質」)を『エコノミカ』に発表した。この論文は、その後しばらくは関心を寄せられなかった。本書初版が1959年に出版されてから数年の間に、いくつもの重要な研究が登場した。それらの研究のなかでは、私自身のいくつものアイデアと類似のアイデアが、他の研究者によってそれぞれ独自に展開されている。企業の成長を決定づける諸要因を扱った初期の2つの著作であるチャンドラーのStrategy and Structure(『組織は戦略に従う』)とマリスのEconomic Theory of Managerial Capitalism(『経営者資本主義の経済理論』)は、それぞれ1962年と1964年に出版された。チャンドラーの著書は私の著書が世に出る前に完成していたのだが、その歴史分析をまとめ上げていく際に使われた分析枠組みは私自身の研究と驚くほど合致しており、ほとんど同じ概念や非常によく似た用語が多々使われている。一方、マリスは私の研究を念頭におき、謝辞でも触れてくれているが、彼自身の研究と基本的な議論は以前から構築されてきたものである。また、彼の研究は「経営者資本主義」における企業の役割に関して、私の研究と一致はするが大きく異なるアプローチを用いている。同書は私の研究を拡張し、かつ修正し、大いなる前進を果たした。これらに続く多くの研究についてここで言及することなどとうていできない。ただ、比較的見過ごされてしまったものの卓越した先駆的業績であるG・B・リチャードソンの論文については、あえて言及しておきたい。1972年に『エコノミック・ジャーナル』に発表された彼の‘The Organization of Industry’は、それに続く研究が大いに期待された論文である。
20世紀の中頃まで新古典派の「企業の理論」、言い換えれば、完全競争市場と相対価格とパレート最適の資源配分の理論は、受容された一連の命題というクーン流の意味において、1つの「成熟した科学」とみなされてきた。この分野の専門家たちは、十分に確立された数学上・言語上の手法を含む厳密な伝統的理論が鍛え上げられた。しかし、彼らは制度を扱わなかった。彼らは、科学としての経済学においては依然としてきわめて強力なカルチャーを形成し、経済理論の教育を支配しているが、彼らの経済学の定義は、アルフレッド・マーシャルの『経済学原理』第1巻(8th edition. 1920)の冒頭にある「日常生活を営んでいる人間に関する研究」という定義とは大きく異なっている。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)