成長の理論
1950年代当時、企業成長の分析に取り組むにあたって、私はある問いに答えを出したかった。それは、いかなる企業にもまさにその本質のなかに、自らの成長を促進し、また、その成長の率を必然的に制限する何かが存在するだろうかという問いである。そのためには明らかに、「内側」の備わった企業の定義、すなわち、アルフレッド・マーシャルやE・A・G・ロビンソンのような産業構造を研究する経済学者の用いた定義や、企業を1つの組織として扱うその他の分野の研究者たちの定義により近いものが必要であった。
企業成長の理論の中核は、非常にシンプルに表現できる。われわれはまず企業の機能を問い、そこから企業についてのふさわしい定義を導き出した。分析の対象は、(他のタイプの企業にも応用できるかもしれないが)事業会社に限定した。このような企業の経済的機能は、市場に製品やサービスを提供して利益を上げるために、人的資源やその他の資源を獲得し組織化することとシンプルに仮定した。したがって、企業は、1つの管理の枠組みのなかに集められた資源の集合であり、その境界は「管理上の調整の範囲」および「権威あるコミュニケーションの範囲」によって決まると定義づけられた。かりにこのような企業が、調整が不可能になるような規模にまで巨大化すれば、この定義は成り立たなくなり、後述のようにその組織の成長は別の方法で分析されなければならないだろう。事業会社の成長の理論が、金融持株会社やその他の同様なグループに適用できるかは明らかではないが、あるいは可能かもしれない。
現代経済における大企業の経営者や取締役たちは、自らの存在を株主のためだと考えているという仮定がある。私は、その背後にある理屈にもそれを支持する根拠にも、何ら感じるところはなかった。つまるところ、1950年代においては、企業にコミットしないタイプのオーナー経営者によって運営される企業は、今日ほど目立った現象ではなかった。その当時適切に思えた仮定は、40年ほど経った今では明らかに不適切である。株主としての金融機関の役割は、財務管理機能に果たす取締役の役割についてと同様に、今日ではより注意深く分析する必要がある。取締役たちは、ラゾニック(1992)が明らかにしたように、企業の成長よりも、高額の報酬、ストック・オプション、黄金の手錠、ボーナスなどによる彼ら自身の金銭的な分け前に関心がある可能性も大いにある。こうしたことは当時では当たり前とは思えなかったため、私は「経営者企業」と呼ばれる企業を分析の対象とした。すなわち、それは、企業の長期の成長に責任を負った経営陣によって運営される企業であり、株主の機能は株式資本の供給を保証する以上のものではない。配当は、企業の株式への投資を誘うのに十分でありさえすれば事足りた。
同じ仮定にしたがって私は、経営者はその役割上、企業の活動の有利な拡張に何より関心をもつとの仮定もおいた。利益は、拡張──言い換えれば成長──に必要な条件として扱った。それゆえ成長は、経営者が利益に関心をもつ主たる理由となる。さらに、企業に留保できる利益が多ければ多いほどよい。なぜなら、留保利益は資金調達の相対的に安価な源泉である。経営陣は、資本市場を満足させておくのに要する水準以上の配当を株主に支払おうなどとは考えない。
このような仮定は、私が企業成長の理論を構築した際、この理論の1つの本質的部分であった。少なくともアングロ‐アメリカ的コンテクストにおける多くの巨大企業では、今日これらの仮定が当時と同じようには適用できなくなるほど、企業の成長率に対する新たな経営上の制約が生まれている。
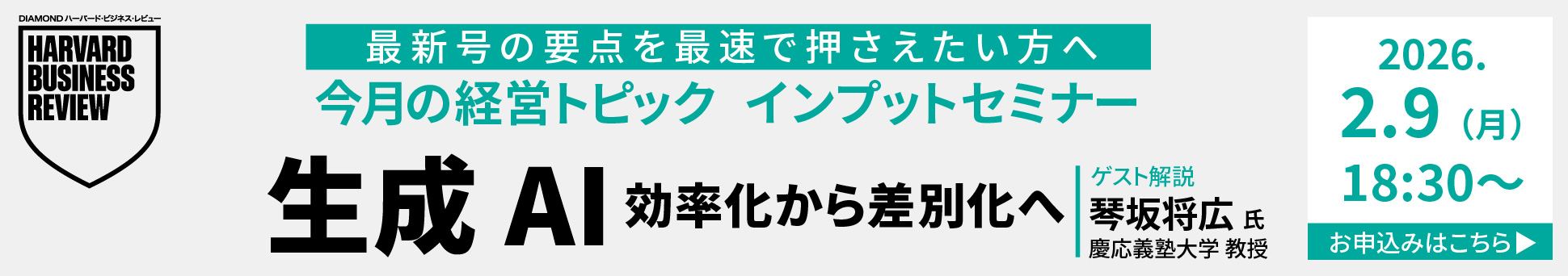





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









