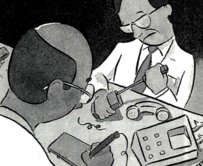-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
整理・清掃・整頓という3Sは、その内容が極めてシンプルかつ理解容易であるがゆえに工場文化の創造にもつながる。グローバル化のいま海外工場で3S活動を続けることが、日本の「ものづくり」文化と現地文化との融合を促進し、現場発の新たな「ものづくり」を創造する。
「ものづくり」という概念装置
「ものづくり」という言葉が頻繁に使われるようになってから、10数年が経過しました。意外に思われるかもしれませんが、「ものづくり」という言葉は、1990年代の後半以降、世の中で盛んに使われるようになった用語です。経済産業省が主導する「ものづくり基盤技術振興基本法」なる法律が公布されたのが1999 年ですし、ものつくり大学という名称の大学が創立されたのも1999年です。日本経済新聞社が発行している日経4紙において、「ものづくり」という用語が使われた記事件数の推移を見ると、1997年以降、急速に使用頻度が高まっていることが確認できます。
しかし、改めて「ものづくり」という言葉が指し示す対象はどのようなものでしょうか。類似語として、以前から「製造」や「生産」という言葉は存在しますが、本質的な違いは何でしょうか。なぜ我々は、時として“熱く”語る時に、「ものづくり」という言葉でなければリアリティを感じないのでしょうか。また、「日本のものづくり」と言った時に、そこに含まれる範囲はどこまでなのでしょうか。「日本企業の」という意味や「国内製造拠点の」という意味、あるいは「日本人作業者の」という意味にも解釈できます。
このように考えてみると、「ものづくり」という言葉は大変都合の良い言葉である反面、何が日本のものづくりに含まれ、何が含まれないかという境界は極めて曖昧です。しかし、だからといって、この言葉がまったく意味のないものだとは思いません。むしろ、日本のものづくりの将来について我々が議論する際には、みなが実体として同一の対象を認識していると感じており、ある種のリアリティを持って議論しています。それでは、なぜこのような錯覚が生まれるのでしょうか。
実は、日本のものづくりという曖昧な分類・範疇化がリアリティとして機能するのは、日本のものづくりではない外部との差異が強調されている時であり、日本のものづくり内部の同一性・均一性は必ずしも目指されていません。つまり、逆説的ではありますが、日本のものづくりという言葉は、企業のグローバル化が進展する中で、日本のものづくりの独自性や特殊性がともすれば希薄になり、競争力が相対的に低下してきたが故に、以前にも増して外部との差異化を積極的に図る目的から頻繁に使用されていると考えられます。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)