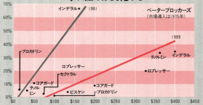生産資源の集合体としての企業
管理組織は、その内部で働く人々の活動に凝集性を与える。このことは、分析の目的上そのような集団をそれ以外のすべての集団と区別することの根拠となる。さらに、われわれが事業会社と呼ぶ集団の活動は、製品やサービスの生産や販売のために生産資源を利用することとの関連によっても区別される。したがって、企業は1つの管理単位というだけではなく、生産資源の集合体でもある。その生産資源は、管理上の決定によって、さまざまな用途や時期に配分される。この観点から企業の機能を考える場合、企業の規模は、用いる生産資源の何らかの尺度によって最も適切に測定される。
企業の物的資源は有形のものからなり、プラント、設備、土地および天然資源、原料、半製品、廃棄物、副産物、そして最終製品の在庫さえもが含まれる。これらのなかには、生産工程のなかですぐに完全に使い果たされるものもあれば、耐久性があり、長期にわたって実質的に同じサービスを生み続けるものもある。また、生産のなかで1つまたはそれ以上の中間製品に変換されるものもある。それら中間製品はいったん生産されれば、それ自体を企業の資源とみなすことができる。市場で直接に調達されるものもあれば、企業内で生産され、企業の外では購入も販売もできないものもある。これらの企業が購入したり、リースしたり、あるいは生産したりするものはすべて、企業の業務に不可欠であり、また、それらの利用方法や性質について、企業は多かれ少なかれ精通している。
企業には、利用可能な人的資源、すなわち、不熟練および熟練労働者、事務、管理、財務、法律、技術および経営に携わるスタッフも存在する。長期契約で雇用されている従業員は、企業にとって実質的な投資といってよい。目的によってはこれらの従業員は、工場や設備のように多かれ少なかれ固定的ないし耐久性のある資源として扱うことができる。たとえ彼らは企業に「所有されて」いなくても、このような従業員が彼らの能力の絶頂期に企業を去れば、企業は資本損失に似た損失をこうむる。このような人的資源は、たとえ彼らのサービスがある時点では十分に活用できなくても、かなりの期間にわたって雇用される。このことは、日給あるいは週給の労働者にあてはまることもあるかもしれない。彼らもまたしばしば、企業の1つの永続的な「部分」として考えられ、資源としての彼らのサービスの喪失は企業にとってコストをともない、言い換えれば、機会の損失をもたらす可能性がある。
厳密にいえば、生産プロセスにおける「インプット」は資源そのものではなく、あくまで資源が提供できるサービスにすぎない。資源によって生み出されるサービスは、それらが用いられる方法の関数である。すなわち、まったく同じ資源が、異なる目的や方法で用いられたり、異なるタイプや量の別の資源と組み合わせて用いられたりすると、異なるサービスないしサービスの集合をもたらす。資源とサービスの間の重要な差異は、それらの相対的な耐久性ではなく、むしろ、資源は潜在的なサービスの束からなり、大部分がその用途とは独立して定義されるが、他方のサービスは、「サービス」という言葉自体がある機能やある活動を意味しており、用途と独立して定義できないということにある。後述するように、個々の企業の独自性の源泉は、大部分この差異のなかに見出される。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)