そして、構造的イノベーションのさらに上にあるのが、マネジメント・イノベーションです。これは人間が働く、その方法自体を新しくすることです。これに成功すると、永続的な競争優位を得ることができます。
かつてゼネラルモーターズは部門組織構造を打ち立てて、その後40~50年にわたって勝ち続けましたし、トヨタ自動車もカイゼンによって30~40年間他社を寄せつけなかった。今日では、オープン・ソース型開発がこれまでにない方法で人々をコーディネートしています。
マネジメント・イノベーションを起こすためには、どこに着目すればいいのでしょうか。
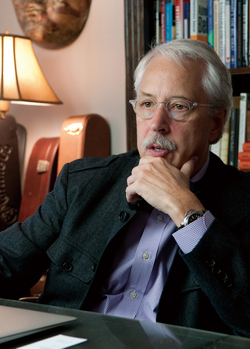
形と機能とを切り離してとらえることが必要です。たとえば、コンパクト・ディスク(CD)事業をしていて、これを「音楽産業に携わっている」と勘違いしてしまうと、別の企業が音楽をまったく違った方法で届けるやり方を編み出して、未来を先取りされてしまいます。CDはあくまでも形であって、機能は音楽を届けることです。つまり、形に捕われてしまうとすぐに時代遅れになってしまうのです。
マネジメントにも同じことがいえます。いま我々が知っているマネジメントは、前時代から受け継いだ特定のタイプであって、ヒエラルキーと官僚主義、手順主義によって構成されている。しかし、その特定の形に目を奪われてはなりません。
私はマネジメントを非常にシンプルに「生産的結果を生み出すために、リソースを動員かつ組織化するために用いるツールと方法」と定義します。人を集めて目的を達成するために、どんな方法とプロセスを採用するのかということです。目を向けるべきは、マネジメントの機能、つまり個々人では成せないことを、集団で効果的に達成しようという目的のほうです。
マネジメント・イノベーションの
実験方法
教授は以前、マネジメント・イノベーションの例としてアメリカの食品会社モーニングスターを引き合いに出されましたね(注2)。
同社には上司がおらず、工場作業員も含め社員全員がマネジャーで、ROIも協力して管理します。社員が自身の裁量で必要なものを購入するのに会社の金を使うことも許され、また就業評価は社員同士のピア・レビューで行われます。
同社では、社員間の関係を組織化し調整するために、「クルー」という方法が用いられていますが、ヒエラルキーのない組織でも、こうしたツールはやはり必要なのでしょうか。
もちろんです。目的はアナーキーを生み出すことではなく、自由とコントロールをどう両立させるのかということですから。要は、クルーのようなものを、各企業が独自につくって実験してみることが大切なのです。なぜなら、マネジメント1.0からマネジメント2.0への変遷は一晩で起こるのではなく、ジャーニー(旅)のような長いプロセスだからです。
現代の製造業型の組織も、小さなイノベーションを続けてきたことで、いまの姿になった。ただ、その目的が効率性と大量生産という点で、現在とは異なっているということです。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)





