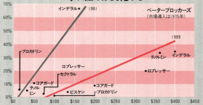-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
1999年、オークション・サイト〈ビッダーズ〉のサービスから始まったディー・エヌ・エー。2005年に東証マザーズ上場、2007年に東証1部、瞬く間に〈Mobage〉で世界展開を図る大企業となった。ほとんどのベンチャー組織が、その成長に伴って成熟化を迎えてしまう。はたして同社は、起業家精神を保ち続けることができるだろうか。そのためには、「ヒト」ではなく「コト」に集中する組織であれ、と南場智子氏は説く。
「すべき」より「やりたい」
「正しさ」より「情熱」
編集部(以下色文字):一般にいわれる優秀な人と、アントレプレナーシップを持った人との違いは何でしょうか。
南場(以下略):それは「すべき」と「やりたい」の違いではないでしょうか。アントレプレナーシップを持つ人は、「やりたい」という強い意志を持つ人です。企業にとって「やりたい」と言ってくる人は非常に大切です。

南場智子(Tomoko Namba)
1986年4月、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。88年、マッキンゼーを退職。90年、ハーバード・ビジネス・スクールにてMBA取得後、マッキンゼーに復職。99年、株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)を設立。同年、マッキンゼーを退職し、DeNA代表取締役社長に就任。2011年6月、取締役就任。近著に『不格好経営──チームDeNAの挑戦』(日本経済新聞出版社)。
PHOTOGRPHY:Aiko Suzuki
ディー・エヌ・エー(DeNA)も企業規模が大きくなり、知名度が上がるにつれて、何万もの人が入社を希望してくれるようになりました。いわゆるエリートも増えています。彼らは「こうすべきだ」という理由をロジカルに説得力をもって説明できるのですが、はたしてこの人には自分が「こうしたい」という情熱があるのだろうかと考えてしまうのです。
もちろん、ヘッドクオーター部門には優秀な人も必要です。でも、「こうやりたい」と強く主張し、理由を問われても「細かいことはともかく俺はこうしたいんだ」とウオンツを情熱的に訴えられる人は、一般的な優秀な人とは明らかに種類が異なる。
アントレプレナーシップで重要なのは、正しい道を選択することより、選択した道を成功させることです。どんな選択肢であれ、必ず壁にぶち当たりますが、壁を打ち破るにはチームの力が必要です。その力の源泉は、「正しさ」ではなく「情熱」にあるのです。
アントレプレナーシップを持つ人がリーダーの場合、「何がなんでもこれをやりたい」という情熱がチームに共有されているので、目の前に壁が出現しても、メンバーは強い意志で壁に挑んでいきます。壁を打ち破るのは、その圧倒的なエネルギーです。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)