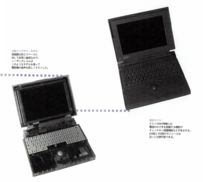これで両者の食い違いが明らかになった。プロジェクトチームの計画は非常に明確であったが、彼らはそれを実行する理由や前提について検証していなかった。たしかに、多くのイノベーションの最終的な目的は、経済的なリターンを生むことである。だがこのチームが苦労のあげく気づいたように、イノベーションに取り組む理由は金銭以外にもさまざまにある。たとえば、従業員の士気向上、社会貢献、あるいはブランドの強化などだ。
金銭的利益が最終目的であるかどうかにかかわらず、プロジェクトを始める前に明確にしておくべきことがもう1つある。取り組みを評価する方法だ。これはできるだけ厳密にする必要がある。最終的な売上目標はいくらなのか。達成期限はいつか。営業利益率はどの程度を目指すのか。
社内ベンチャーでは、イノベーションに取り組む理由とその評価方法が後回しとなることがあまりに多い。この傾向は特に、新規事業の開発ないしインキュベーション部門に顕著である。まさに、映画『ショーシャンクの空に』でティム・ロビンスがモーガン・フリーマンに言うセリフ、「必死に生きるか、必死に死ぬか」と同じだ。企業内でイノベーションに携わる者は、「必死にイノベーションを起こすか、さもなければ自分たちの存在に疑問を持たれるか」の二者択一にとらわれている。
この問題に対処するため、一部の企業はプロジェクト開始前に趣意書の作成をチームに義務づけている。そこでは次のような項目が詳細に記される。プロジェクトの戦略的意図(理由)、具体的な目標(方法)、検討すべき戦略上の要素(例:ターゲット顧客、販売チャネル、提供方法、サプライヤー/パートナー、市場参入の方法など)、避けられない不確実要素、必要な経営資源(人・金)、誰がどの意思決定を担うかという役割、戦略上の重要なマイルストーン、次にプロジェクトが審査を受ける時期、などである。
最後にアドバイスをもう1つ。イノベーションへの体系的な取り組みや条件の設定に対して、善意を持って異を唱える社内のお偉方には注意したほうがよい。「わが社は何に対してもオープンだ」(イノベーションは自由に進めるべきだ)と言うのは気分がよいだろうが、私の経験上、それは決してその人の本心ではない。後々でやり直しを強いられるのを避け、無駄な時間を節約するために、ゲームのルール――特にイノベーションの「理由」(戦略的意図)と「方法」(具体的目標)は最初から明確にしておこう。
HBR.ORG原文:The Two Questions to Ask Before You Innovate July 10, 2013
■こちらの記事もおすすめします
イノベーションのための組織をつくる、10のヒント
包括的(BOP)ビジネスをやるか、やらないかを決める
イノベーションの実現に不可欠な、9つの成功要因

スコット・アンソニー(Scott Anthony)
イノサイト マネージング・ディレクター
ダートマス大学の経営学博士・ハーバード・ビジネススクールの経営学修士。主な著書に『明日は誰のものか』(クリステンセンらとの共著)、『イノベーションの解 実践編』(共著)などがある。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)