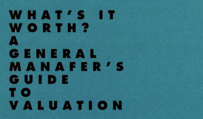神田 先生は、トップ・ビジネススクールの一つであるペンシルベニア大学ウォートン・ビジネススクールで、人気No.1の講義を15年以上続けています。50カ国以上の政財界のリーダーたちを指導した実績を持ち、ベストセラー本の著者でもあり、ニューヨーク・タイムズ誌で記者をしていた1986年には、ピューリッツァー賞を受賞されました。
これらの功績は交渉から得たものではなく、先生の能力と努力の結果だと思いますが、交渉術が結果を後押しした場面はありましたか。
ダイアモンド 私は、交渉術を広く定義しています。相手と友だちになりたい、というそれほど難しくない場面でも、他の誰かと合意を得るときに必要な、対人関係における基本過程だと捉えています。
社会はコミュニケーションで成り立っていて、人間は相手を説得する能力を持っています。子どもに早く寝なさいと言ったり、情報を相手から引き出したり、ビジネスパートナーとの駆け引きなど、どれをとってもまったく同じプロセスが要求されます。
そこには目標を定めるという作業、相手の立場に立つこと、そして相手を満足させながら、目標達成のために正しいツールを使用するという作業が発生します。私にとってはこの作業の繰り返しでした。
ピューリッツァー賞も交渉術の成果

経営コンサルタント・作家
上智大学外国語学部卒。ニューヨーク大学経済学修士、ペンシルバニア大学ウォートンスクール経営学修士。大学3年次に外交官試験合格、4年次より外務省経済部に勤務。戦略コンサルティング会社、米国家電メーカーの日本代表として活躍後、1998年、経営コンサルタントとして独立。コンサルティング業界を革新した顧客獲得実践会(のちに「ダントツ企業実践会」、現在は休会)を創設。同会は、のべ2万人におよぶ経営者・起業家を指導する最大規模の経営者組織に発展、急成長企業の経営者、ベストセラー作家などを多数輩出した。1998年に作家デビュー。現在、株式会社ALMACREATIONS代表取締役、公益財団法人・日本生涯教育協議会の理事を務める。
神田 とても重要なお話なのでもう少し詳しくお聞きします。たとえば、先生はピューリッツァー賞を受賞されましたが、それは交渉術とは関係ないようにも思えますが、いかがでしょうか。
ダイアモンド そう思われるかもしれませんが、ところが大いに関係があるのです。私は、人から情報を得るために、その相手を説得することができていました。その情報は私にしか提供しなかった情報であり、相手が私の達成したかったビジョンに同意してくれたから提供してもらえたものです。
リーダーシップなしに、第三者から信頼を得ることはできません。指導力も大事ですが、信頼を得ることができれば、相手は必ず同意してくれます。
ハーバード大学法学大学院に入学して1週間ほどした頃、ハーバード・ネゴシエーション・プロジェクトのメンバーと会って、自分がジャーナリストとして長年情報収集の交渉をしていたことにはじめて気がついたのです。ハーバード・ネゴシエーション・プロジェクトのメンバーは、交渉のプロセスを意識しています。
自分の周りで起こっていることを意識すれば意識するほど、人とのつながりが生まれ、目標達成がしやすくなります。そのため私は、周りで起こっていることをとことん意識しなさい、と教えています。
神田 相手の言葉や行動を通じて、この人は何を言いたいのかをしっかり捉えることが必要だということですね。
ダイアモンド そうです。もし誰かに怒鳴られたり脅されたりしても、なぜそんなに怒っているの、と冷静に問うことです。怒りの背景にあるものは何かを知りましょう。もしかしたら、あなたとは何の関係もないことで怒っているかもしれません。さらには、相手が怒っている原因を聞いてあげることで、その人と友人関係を結べることだってあるかもしれませんよ。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)