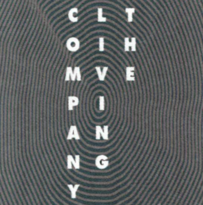神田 先生の著書『ウォートン流 人生のすべてにおいてもっとトクをする新しい交渉術』(集英社)では、日本企業を例にいくつかの具体例を紹介しています。たとえば、会議には同僚と出席しがちな日本人に対して、アメリカ人は一人で臨むことが多いのですが、ふたを開けてみると、日本人は複数で出席することでお互い取ったメモを確認し合うという作業をしている点です。
ダイアモンド より多くの見解を知ることで、何をするべきかをはっきり知ることができます。この部屋にいる一人ひとりの見解が違うとしたら、最終判断を下す前に、その一つひとつを知る必要があります。もしかしたら、ある人の見解を知ることで、やり方を変えるかもしれません。世界中の交渉の場で問題となっていることの原因は、両者がお互いのことを知らなさすぎることです。
あなたが私の取引相手で、価格設定について合意できないとしましょう。でも、合意できない理由は価格とは関係ないかもしれません。まったく別のことに起因している可能性があります。会話を通してそれが何かを突き止めることができた時に、価格の問題も解決するでしょう。
神田 取引先との関係が非常に緊迫していて、部下が相手と話すのも嫌がる時に、上司としてどう対応すればいいですか。
ダイアモンド 取引先が聞く耳を持つ第三者を、交渉に出向かせることです。あるいは、上司となら話すという姿勢が相手にあるなら、上司が出向いて両社の関係が緊迫している理由を聞くことです。「なぜ腹を立てているのですか。理由を聞かせてもらえませんか」。それでも状況が改善しない場合は、第三者を利用します。妻が私に怒っている時に、交渉術を発揮して状況を改善してくれるのは12才の息子です。第三者を利用しない手はありません。
相互の協調性は価値を生まない
神田 いまのお話は企業間だけにとどまらず、国同士の関係改善にも役立ちますね。

ダイアモンド その通りです。ウクライナ情勢を例に挙げます。90年代にウクライナの大統領だったレオニード・クチマを仲裁人として選任していれば、事態は軽減していたと思います。クチマは西にもロシアにも愛されていた人物です。現在、彼は80才を超えていますが、それでも大きな力を発揮したでしょう。オバマ、プーチンやメルケルは争いをやめて、誰もが尊敬する仲裁人を利用するべきです。第三者を利用するのは紛争解決に役立つ手段なのです。
神田 日本人はもともと、相手との協調性を大事にします。よって先生の著書に紹介されている12の法則を読めば、すぐにこの交渉術を実践できると思っていました。ただ、先生の話し方や会話の運び方に触れることで、いかに相手とつながることが大事なのかを、さらに理解することができました。
ダイアモンド そうですね。しかし、協調性は価値を生み出すものではないことも知ってください。研究結果によると、より多くの議論が、より多くの収益をもたらすことがわかっています。お互いの相違点を理解したうえで行う必要がありますが、大事なのは協調性ではなく、相手を尊敬する気持ちなのです。相手と合意を得られない時は、その意見の違いそのものを互いに尊敬します。お互いに学び合うことで、必ず良い結果が得られます。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)