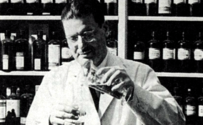これらの研究結果に積み重ねる形で、我々は最近の研究で次の点を検証した。危機の自主公表が効果的である理由は、「古いニュースはたいしたニュースではない」と見なされるからではないか。つまり、自社に不利な情報を先んじて公表すれば、人々はその後に続く批判的な報道を、古いニュースと受け止める。その分、関心も減るということだ(英語論文)。
最初の実験では、参加者たちに一流新聞紙から抜粋した一連の記事を読んでもらった。その中には架空の記事が1件混ぜてあり、某企業の危機が第三者によって明らかにされたことを伝えている。この批判記事に参加者がどの程度注目するかを、視標追跡を用いてひそかに測定した。
この作業に先立って、参加者のうち半数は別の架空記事も見せられていた。同じ某企業が、自社に不利となる出来事を公表し、危機を招いたみずからの責任を認めた、という内容だ。残り半数の参加者は、それとは無関係の記事を見せられていた。そして実験の最後に、各参加者にその企業の評判を判定する質問票を配布した。
結果はこうであった。企業が自主公表したという記事を事前に読んでいた参加者(「先制公表」条件)は、読まなかった参加者(対照条件)よりも、その後に与えられた批判記事を読む時間がはるかに少なかったのだ。ここから示唆されるのは、先制公表によって、批判報道に対する消費者の関心は明らかに減じるということである。
加えて、企業の評判に関する判定結果によれば、消費者(実験参加者)が批判報道に注目した場合でも、その注目が評判に与えるダメージは、先制公表によって緩和されることが示された。
その一方で、危機の第一報が当該企業によるものではない場合は、第三者による批判記事への関心は高まり、結果として評判へのダメージが大きくなるおそれがある。
これらの結果は、コモディティ理論の立場から説明できる。「すべてのモノは、その入手可能性に基づいて価値が決まる」ということだ。「企業の危機に関する情報」というコモディティが希少な場合は、その価値が高まる。したがって、目新しい情報は古いニュースよりもいっそう注目を浴び、人々の評価や態度により大きな影響を及ぼすのだ。
ただし我々は、企業の危機に対する消費者の関連や関心の度合いが、必ずしも一様ではないことも認識している。たとえばVW車の所有者は、そうでない人に比べ、排ガス不正問題に関するどんな情報にもはるかに高い関心を示すだろう。
次の実験ではこの点を検証した。関連度の違いによって、先制公表の効果が変わるのか、である。具体的には、初回の実験を再現しつつ、今回は企業の危機と個々人との関連度にバリエーションをつけた。参加者の半数は、自分に関係の深い危機シナリオを受け取った。残りの半数は、内容は似ているが自分との関わりはほとんどないシナリオを受け取った。
結果はこうなった。危機への個人的な関連度によって、たしかに先制公表の効果は異なる。ただしそれは、企業が危機の自主公表を怠った時のみに当てはまるのだ。企業とその出来事に深く関連している消費者は、自主公表されなかった危機に関する批判記事を、きわめて高い関心を持って読んだ。しかし関連度が低い消費者は、第三者が明らかにした危機にそれほど注目しなかった。
そして、危機を先制公表した企業については、消費者個々人の関与の度合いにかかわらず、批判報道への関心は低かった。
上記の結果によれば、先制公表が最も効果を及ぼす対象(先制公表されなかった場合の批判報道に、最も敏感になる人々)は、忠実な消費者層(関連度の高い人々)ということになる。これは重要なポイントだ。なぜなら、窮地にある企業にとって最も重要な存在は、忠実な消費者層に他ならないからである。
企業は重大な危機に直面している時、世間の誰にも気づかれないことを願い、事態を隠したい誘惑に駆られるかもしれない。だが既存の論文と我々の研究結果をふまえれば、それは愚策である可能性が高い。臭いものに蓋をしようとすれば、やがて危機が表面化した時にいっそう注目を浴びることになる。そして、批判報道への注目が評判にダメージを与える。
メディアに先んじて自主公表すれば、外部の批判に対する関心も、それに続く評判へのダメージも抑制できる。つまり不利な情報の開示は、倫理的に最善の道であるだけでなく、戦略的に最も賢明な選択肢でもあるのだ。
HBR.ORG原文:Companies Fare Worse When the Press Exposes Their Problems Before They Do August 22, 2016
■こちらの記事もおすすめします
企業が正しく謝罪する方法
セラノス事件が突きつける、ストーリーテリングの暗黒面
アン=ソフィー・クレイズ(An-Sofie Claeys)
ルーヴァン・カトリック大学(ベルギー)メディア研究所の助教。コーポレートコミュニケーションを担当。研究の中心テーマは組織のクライシスコミュニケーション。自主公表、非言語サイン、共感などを含む。
ベロリーン・コーバーグ(Verolien Cauberghe)
ゲント大学(ベルギー)パースエイシブ・コミュニケーション・センターの准教授。説得的コミュニケーションを担当。研究の中心テーマは、さまざまな状況(広告、コーポレートコミュニケーション、ソーシャルマーケティング)におけるに説得的メッセージの効果。
マリオ・パンデレーラ(Mario Pandelaere)
バージニア工科大学の准教授、およびゲント大学(ベルギー)の教授を兼務。いずれもマーケティングを担当。研究の中心テーマは説得、消費者の意思決定、物質主義。『ジャーナル・オブ・コンシューマ・リサーチ』誌の編集委員、および『インターナショナル・ジャーナル・オブ・リサーチ・イン・マーケティング』誌のシニアエディターも務める。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)