リッジは学びへのコミットメントに真摯となるあまり、全社員に「マニアックの誓い」を立てさせている。これは、彼いわく「学習マニア」になることへの固い誓いであり、文言は以下のとおりだ。
「私は行動を起こし、質問をし、答えを得て、意思決定することを、自分の責務とします。誰かが私に教えてくれるまで待つことはしません。知る必要があれば、質問するのが私の責任です。『もっと早く教えてほしかったのに』と腹を立てる権利は、私にはありません。他者も知っておくほうがよい、と思える何かに私が従事している場合、それを他者に伝える責任があります」
WD-40という会社は、こうした学習至上文化の土壌としては似つかわしくないようにも思える。同社は華やかなブランドとは言い難い。ただし、それなりに象徴的な存在ではある。車の整備や家の修繕をする人、あるいは単に軋み音やサビを取り除きたい人ならば、ほとんど誰もが、ガレージや流し台の下に例の明るい青色と黄色の缶を備えているはずだ。
実際、ギャリー・リッジが1997年にWD-40のトップを引き継いだ当時、同社の主力製品は米国世帯の5分の4で使われており、国内にあるほぼすべての採掘場、工場、建設現場に普及していた。
新CEOはすぐに、製品の広い普及は幸福でもあり災いでもあると気づいた。
WD-40はまさに米国人の生活の一部と化し、ほぼカルト・ブランドとなっている。一方で、同社は一芸にしか秀でていない存在でもあった。製品は基本的に1つで、販売地域は国内が大半だ。株式利益のほぼ100%を配当金の支払いに充てていた。なぜなら、他に金の使い道を知らなかったからだ。『バロンズ』誌の2001年の記事を引用すれば、「WD-40はカルト製品だが、カルト銘柄とはいえない。過去の成功そのものが、同社を最終的に失敗へと向かわせていた」のである。
時間を一気に現在まで進めよう。
WD-40の製品はいまや176ヵ国で販売され、欧州の売上高だけでもリッジのCEO就任時の総売上高を超えている。新しいブランドと製品をいくつも立ち上げてきた。株価は2009年以降ほぼ3倍となり、創業以来初めて時価総額10億ドル企業に仲間入りした。最近の株価は120ドルに迫り、時価総額は17億ドルに近づいている。これは、同社にとって未知の領域だ。




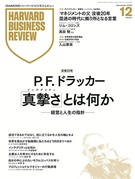
![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









