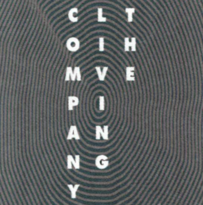社会の仕組みは、虚構で出来上がる
安宅:そう思います。今の話を聞いていて思ったのは、今アメリカで売れていて、日本にも上陸した『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳、河出書房新社)という本のこと。これは必読です。ハラリは、人間を人間たらしめた能力は、虚構構築能力だと喝破している。たとえば、会社なるものは存在しないと。我々全員がここにダイヤモンド社(編集注:対談はダイヤモンド社で行われた)があると信じることによって、ダイヤモンド社が存在する。すべてそうです。法律も存在しない。全員の中で法律という共通の枠組みをはめ込むと便利だからみんなで信じようということで法律があるわけです。すべてが虚構空間でできている。伊賀さんが言った患者と周囲の人が高い価値だと感じる部分も、そういう意味では虚構ですね。
伊賀:今、安宅さんが「虚構」と呼んでるのは、まさに私が『生産性』に書いたビジネスイノベーション、非技術的なイノベーションの話ですね。なんだけど、たくさんの人が信じる新たな虚構をつくるのは簡単なことではありません。
安宅:ものすごく難しい。でも、共通の虚構を積み上げることで、人間は社会制度のすべてをつくり、巨大な仕組みを構築してきたとハラリは書いている。その虚構構築能力こそが、人類が現在の礎をつくった時期と同じぐらい大事になってきていると思います。
伊賀:そうですね。そして新たな虚構が提案され、多くの人がそれを信じ始めると、過去にみんなが信じてきた社会制度としての虚構がアップデートされて覆されていくんです。
その典型例が結婚制度。結婚制度って、これまでの技術的な制約条件下で考えると、種の保存のためにベストな虚構だった。だからここまで普及して社会通念にまでなってきたわけですけど、フランスなど欧州では既に事実婚的な新たな虚構制度が提案され、そちらのほうが支持を集め始めています。
生物にとって種の保存は究極の目的ですが、それにもっとも適した虚構、つまり社会制度が何かというのは、環境や利用できる技術が変わればそれに応じてアップデートされていくのが自然なこと。
古い虚構が機能しなくなっているのに、「次はこれでいこう」という新たな虚構を提案できないと、社会も企業も停滞してしまう。少子化問題の根幹もそこにある。そういう意味で私が『生産性』の中で書いたビジネスイノベーションを起こす力というのは、まさに虚構構築能力ってことですよね。
安宅:そう。僕が書いた「イシュー」と伊賀さんが書いた「ビジネスイノベーション」は、「へそ」と「虚構」なんです。だって戦争なんてすごいじゃないですか。まったく論理的ではないのに、虚構に押されて全員で猛進していく。それまでは隣の人に石をぶつけることでさえ叱られていたのに、戦争では1人でも多くの敵を殺せと言われる。言っていることが支離滅裂。でも虚構を信じさせることで、あのようなことが起こってしまうんです。
伊賀:どの国も「人を殺してはいけない」という法律を持っているのに、国際社会全体では、戦争という武力による問題解決手法が認められてしまってる。しかも、捕虜の扱いや化学兵器使用の制限など細かいルールを山ほどつくることで、総体では「紛争解決のために暴力を使うこと」にお墨付きを与えてる。こんな虚構を受け入れさせてしまうなんてホントすごい。
安宅:すごいことだと思います。
伊賀:世の中を進歩させていくのが新たな虚構の提言だとすると、今の社会常識を一生懸命覚えることではなく、壮大な新しい虚構を妄想するために発想を解き放つことのほうが大事ですよね。そして時代遅れになった虚構がアップデートされることで、社会の生産性が一気に上昇する。
安宅:そうですね。虚構を生み出す力が生産性を高める最後のカギになると思う。これが先ほどのあるべき姿の見極めにおいても、解を出すのも大変な問題解決においてもカギになります。
※バックナンバー・続きはこちら(全4回)→[第1回][第2回][最終回]
【著作紹介】
イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」
(安宅和人:著)
MECE、フレームワーク、ピラミッド構造、フェルミ推定…目的から理解する知的生産の全体観。「脳科学×戦略コンサル×ヤフー」トリプルキャリアが生み出した究極の問題設定&解決法。コンサルタント、研究者、マーケター、プランナー…「生み出す変化」で稼ぐ、プロフェッショナルのための思考術。
ご購入はこちらから!
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
生産性―マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの
(伊賀泰代:著)
「成長するとは、生産性が上がること」元マッキンゼーの人材育成マネジャーが明かす生産性の上げ方。『採用基準』から4年。いま「働き方改革」で最も重視すべきものを問う。
ご購入はこちらから!
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]










![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)