時間と空間にしばられない働き方が副業・兼業の幅を広げる
――改めて伺いますが、時間と空間にしばられないことで、働き方にどのようなメリットが生まれますか。
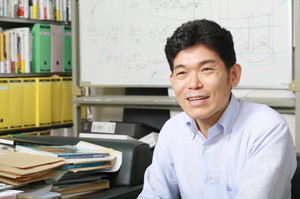
たとえば、多くの人びとがよりよく働けていないのは、通勤時間をかけて出社し、朝から夜まで会社にいなければならないからです。何等かの制約があり、それが無理な人たちもいます。子育て中の人や親の介護が必要な人です。それ以外の理由でも、地方に住んでいながら東京の仕事をしたい人もいますし、海外にいても日本の仕事をしたい。その逆のパターンもあるでしょう。
時間と空間にしばられなければ、子育てや介護中であっても働くことができますし、地方にいながら東京の仕事をこなしつつ、地元に貢献することも可能です。
もう1つ重要なのは、これまで副業が認められなかったのは、時間と空間の制約があったからだと思います。ですから、平日の夜か、土日しか副業はできませんでした。本業をフルで行い、プラスαで副業をやるというのでは長時間労働になってしまい、どうしても限界が生まれます。週に3日は本業、残りの2日は副業といったバランスの取れた働き方が副業や兼業のあるべき姿ではないでしょうか。時間と空間にしばられない働き方は、過重労働に陥ることなく、副業や兼業の幅を広げてくれると期待しています。
――雇用する側としては、まだまだ本業と副業の線引き、副業・兼業に対する容認の判断が難しそうです。
雇用先と従業員との間で利害相反にならないような仕組みやルールづくりが不可欠です。テクノロジーに合わせて働き方を変化させることが必要と言いましたが、副業・兼業についても同様です。働き方改革の芽が出てきているうちに制度整備に早めに着手することが、今後、副業・兼業が当たり前の時代を迎えたときの準備になります。経営者にとってこれは大きなチャレンジです。
――働き方改革の先にある、企業と個人と未来、IoT、AI時代の新しい働き方について伺います。
企業は永続的な組織ではなく、プロジェクトベースで運営されていく時代を迎え、個人は、安定的な組織に所属しつつ、それとは別に副業・兼業でベンチャー事業も手がける――。そんな時代がやって来るかもしれません。日本人は安定志向が強いですから、安定的な組織に7割、ベンチャー事業に3割といった配分でコミットしていくのが未来の一つの姿でしょう。ベンチャー事業からイノベーションが生まれるかもしれませんし、たとえ失敗しても、マネジメントの経験は本業に活かすことができます。
(構成/堀田栄治 撮影/宇佐見利明)




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)





