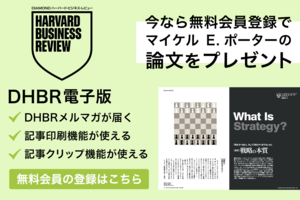AIの分析には問題設定と
フレームワークが必要
――ビジネス分野でのAI活用ではどのような研究をされていますか。
イトーキの研究所と「会議の会話データ分析」を行なっています。会議室での会議の音声をすべて録り、会議のテーマについて話している「代表度」とテーマ以外について話している「発散度」の2つの指標で分析します。さらに、それに議論の停滞、探索、深掘り、合意形成というタグ付けをしていきます。
そうすると、通常は停滞、探索、深掘り、合意形成のサイクルを繰り返し、会議が回っていることがわかります。しかし、時間が経つにつれ、停滞、合意形成の繰り返しだけになり、探索や深掘りのための会話が少なくなっていることもある。そんなときは発言や参加を促したり会議を止めたりすれば、時間の有効活用になるわけです。そういうファシリテーションをアルゴリズムにやってもらう可能性もあるでしょう。
また、このような内容の会議のときは、この人を呼んだほうがアイデアが出やすいといったこともわかってきます。今まで何となく決めていた会議のメンバーも、データに基づいて人選することができるようになるのです。異なる部署、未経験の業務であっても、その人の個性や感性が役立つかもしれません。
ビッグデータという言葉にとらわれてしまうと、とにかくデータをたくさん集めるという発想になりがちですが、実際にAIで分析をするには問題設定とフレームワークを決めることが必要です。その中で目的をもって有効なデータを集め続け、分析し続けることが大切なのです。
変化を検知することが
今の時代のデータ分析
――データの在り方、捉え方も時代とともに変わってきていますね。
かつて新聞が情報収集の中心だった時代は、新聞にデータが「ストック」されていました。テレビやラジオといった電波が中心だった時代は、データが流れてくる「フロー」に。そして、インターネットの時代になると、WEBサイトのコンテンツを見に行く「ストック」に戻りました。
今はモバイルの時代になり、再び「フロー」に変わっています。フェイスブックやツイッターは、毎回最新の画面に変わってゆき、情報が次々と流れているのです。
「ストック」の世界では、どれだけ多くのデータを蓄積できるかが分析力の源泉になり、そこから傾向を分析していました。一方、「フロー」の世界では、必ずしもデータの量は必要なく、データの変化を検知することが重要になる。誰かが普段と違うことを言ったとか、普段と違う行動をしたといった変化が分析の鍵となります。
例えば、製品については今までは買った、売ったというデータしかありませんでした。しかし今は、製品にセンサーをつければ、どう使われているかがわかる。そうでなくても、ツイッターなどで使われ方が見えるようになっています。そういう意味では、お客様に近づきやすくなり、お客様と一緒に製品を開発していくというサイクルがつくりやすくなりました。