アイデアを生み出せる人材の育成が重要に
――基礎研究に留まらず、幅広い産業分野に応用可能な技術を開発されており、企業とコラボレーションによって、さらなる進展が期待できそうですが、社会・経済課題の解決、あるいは業務の付加価値向上に向けたビッグデータの利活用を促進するには、何が必要でしょうか。
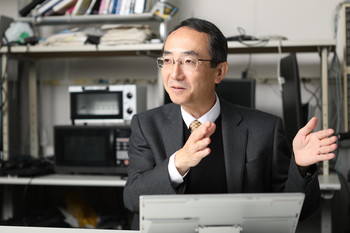
いままでは、大学で論文的に正しい成果が出れば、産業界にそれをインプリメントすれば、割とそのまま成功するケースが多くありました。しかし、ビッグデータの世界は、パラメーターのチューニングの問題があり、かつ特徴量をどう選んでいくかは非常に大きなポイントになります。昨今のディープラーニングでは、多くのデータを学習することによって、特徴量を取り出すことをやろうとしていますが、現実には、そんなに多くのデータがあらゆる領域で存在するわけではないので、実際にデータをお持ちの企業と相談して、研究を進めていく必要があります。
そうした企業には、すでにデータに関する知見はお持ちですから、「こういうデータには、こういう特徴がある」というフィードバックをいただくことで、我々のほうでチューニングができると考えています。この方法では膨大なパターンを試す必要がありますが、データに対するノウハウや知見をお持ちの企業と大学がコラボレーションすることで、パターンを絞り込んだうえで実験できますし、いろいろな大学と組むことで、異なるやり方を試すことも可能になるでしょう。
あとは、ニーズをどこに設定するか。大学側が主導で考えたニーズは、実際の世のなかでは役に立たないことも多いので、ニーズ自体は企業側から積極的に発信していただきたい。それは、大学とコラボするしないにかかわらず、です。いろいろな形で情報発信していただいたほうが、研究も広がっていくと思います。
――AIやビッグデータ、IoTといった革新的なデジタル技術が我々の生活やビジネスにもたらすインパクトとはどのようなものでしょうか。
生活やビジネスを便利にしていくという方向では、そうしたデジタル技術が積極的に活用されていくことでしょう。一方、世のなかでいわれているように、人間がAIやロボットに置き換えられてしまうというのは、いまの技術では無理ですね。単純作業や物理的にものを動かすという部分はロボットが活躍するでしょうが、コアな部分、人間がしっかりアイデアを考えるところは、これらに代替されるものではありません。そういった意味で、大学としてはアイデアを出せるような学生を育てていきたいという思いは強くあります。
もっとも、究極的には、我々がアイデアと呼んでいるものも、ある方向性やある仕組みによって導き出されるものかもしれません。何がアイデアなのか、我々は基本的に経験に基づいて意思決定し、行動しているのですから。我々人間は、雰囲気を読み取ることができますよね。五感を使って空気を読む。残念ながら、そうした仕組みはデジタル技術にはありません。でも、面白いテーマですから、そういった領域にも機会を見つけて挑戦したいと思います。
(構成/堀田栄治 撮影/宇佐見利明)






