日本企業の課題、経営とのかい離を埋めるには
日本企業はデータ活用を進める部署と、経営陣との間に意識の乖離が大きく感じる。経営者にデータ活用の重要性を説くにはどうすればいいか。
長谷川氏いわく、「データ分析で得た判断が、経営判断にすべて通じるわけではないという認識の違いに乖離があるなら健全だ」。データ分析で予測できる答えは限界がある。経営者はデータでは補えない広い視野で判断を求められるからだ。
ただ、経営者の無関心や無理解を放置してはいけない。「残念ながら、数学や技術の知識が求められるため、耳を貸さない経営者は多いが、データ活用部署はわかりやすく説明する努力が必要だ」と指摘しつつ、「経営陣にはエンジニアになれとまで言わないが、踏み込んで学んでほしい」と語る。
河本氏は、「データやAIを活用した意思決定を経営に生かすことは至上課題となりつつある。その意味でデータ活用部署と経営陣との間には密なコミュニケーションが必要で、断絶があってはいけない」と語りつつ、「一方で、データ偏重が進むことで起きる弊害もある。データで説明することが目的化して、本来すべき意思決定ができなくなってしまっては本末転倒だ」と注意を促す。
もう一つ、実務上の困り所としては、「有用なデータがない場合はどうすればよいか」というものがある。
この点について河本氏は、「まず、入手可能なデータで何とかすることを考えるべきだ。直接的に取得できる情報以外に、背後に隠れているとか、間接的な因果関係があるデータもある。現場との対話で見つかることも多い」のだという。
さらに「他の部署や現場の協力を仰げない」という悩みも多いだろう。長谷川氏はアップル時代を振り返り、他のエンジニアの協力が欠かせなかったが動いてくれなかったとき、得た結果を上層部に一緒に発表しよう」と、協力者のベネフィットを考えて熱心に口説いたという。
この問題の派生形としては、「規模が大きく改善効果が高いが非協力的な部署と、飛び地で規模も小さいが熱意をアピールしてくる部署、どちらと組むべきか」というものもある。
河本氏はずばり「協力的な部署と連携して成果を挙げることに注力すべき」と語る。「そこで挙げた成果を、全国の担当が集まる会議などでアピールする。続けていれば、導入の気運が高まる"潮目"が必ず到来する」とその理由を挙げた。
会場の来場者とも盛んな質疑応答がなされたが、多くの日本企業に共通する悩みとしては、「なぜ米国のようにデータ活用が進まないのか」という点に尽きるだろう。
長谷川氏はベソスの例を改めて挙げながら、「創業者や創業マインドの不足が一因だ。経営者に強い哲学やパッションがあってこそデータは活きる」。
河本氏も深く同意しつつ、「日本でも、中小企業の創業社長のような強い情熱を持ち、未来を切り開こうとする経営者ほどデータを活かせる」と補足した。いずれにせよ、AIの活用が進めば進むほど、データでは分析できない「不確実で非論理的な事象」を判断できる経営者の重要性は増す。それができない経営者は、やがてAIに取って代わられる。「今後はそうした格差が拡がっていくのではないか」と締めくくられた。
【著作紹介】
『THE ONE DEVICE ザ・ワン・デバイス――iPhoneという奇跡の“生態系”はいかに誕生したか』
ブライアン・マーチャント 著、倉田幸信 訳
【日本語版への解説】「アップルに脈々と受け継がれる、技術革新のバトン」長谷川貴久(元Apple本国Siri開発者)
「iPhone を創ったのは、スティーブ・ジョブズ」――誰もがそう思っている。だが、ジョブズの役割は、iPhone 誕生までの壮大な物語のほんの一部にすぎない。その開発にまつわる話は、Apple 社の秘密主義により、明かされないままだった。 iPhone は驚くほど多くの人々や組織の「発明の集合体」である。様々な大学やスタートアップ企業、研究所、政府の助成金、さらにその生産には、ほぼすべての大陸の鉱山労働者、中国を筆頭とする何十万もの工場労働者が関わっている。 秘密のベールに包まれた開発の過程を要素分解し、執念で辿っていく。SONY 幹部らが地団太を踏み、海外の競合も度肝を抜かれた iPhone 誕生秘話を描き尽くした力作!
お買い求めはこちら
[Amazon.co.jp] [楽天ブックス] [e-hon]


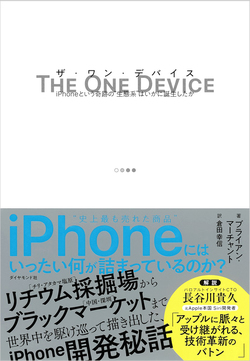





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









