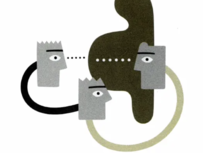景気後退に備えて今、何をすべきか
特集以外では、時代を映すHBR論文として一押しが、「不況期を生き延びるために企業は何をすべきか」です。
話は2000年初頭、ネットバブル崩壊寸前の社債発行で難を免れたアマゾン・ドットコムの事例から始まります。同様に景気後退懸念が強い今、社債市場が活況です。
運用先に困っているマネーの供給側と、低金利のうちにフリーキャッシュフローを多めにしておきたい企業の需要側とがマッチして、債券市場に資金が移動しているようです。また、米国では、低利率で起債して得た資金で、自社株買いを行い、株価を高めようとする企業もあるようです。
この論文では、負債圧縮を推奨する他、不況時の設備投資策や不況後のことを考慮したリストラ策など、行うべき施策を、過去に勝ち残った企業の分析をもとに提案していて説得力があります。
もっと長期の視点から経営と投資の方向性を提案する論文が、「機関投資家がESG投資を最重要視する理由」です。世界トップクラスの資産運用会社やアセットオーナーの43社を調査したもので、原タイトル"The Investors Revolution"の実態を表しています。
この分野は変化が激しいうえに、経営には多大な影響を与えます。背景にある考え方や変化の経緯がわかりづらいという方にお薦めの書籍が、『ビジネスパーソンのためのESGの教科書 英国の戦略に学べ』(黒田一賢著、日経BP)です。一連の変化で先行する英国で、ESG関連機関に7年間勤務した著者が、なぜ英国なのか、を歴史的経緯から説明します。
重商主義国家間の争いを優位に進めるとともに、世界で最初に産業革命を果たした英国は、高い工業生産力や世界貿易、植民地支配によって巨額の富(資本)を蓄積。その富の運用のために金融分野でイノベーションを続け、世界の金融センターとしてのロンドン"シティ"を構築します。
一方、労働者の権利も他国に先駆けて確立し、生活保障のための保険や年金制度が開発され、その運用機関が発展。また、"霧のロンドン"で知られる工業化による公害、それに対する環境保護活動や市民意識が芽生え、ESG関連のNGOもシティに結集するようになります。
資本を「いかに効率よく成長させるか」と同時に、「いかに社会のために機能させるか」の両面で、英国は歴史的に世界をリードしてきているのです。『ビジネスパーソンのためのESGの教科書』では、英国をベンチマークしながら、日本の金融制度の課題や江戸期から培った社会文化の優位性を分析し、日本が今後進むべき方向性を示します。今年5月に発行されたばかりで、直近のコーポレートガバナンス・コード改訂など最新動向とその影響も押さえていて、この分野の理解は深まります。
ところで、市場主義思想や小さな政府志向が強い米国では、ESG問題を資本運用に結び付けることへの抵抗感が根強くあります。ESG問題を考慮した資本運用がアウトパフォームする(市場全体よりよい)という実証研究はいくつかあるのですが、それはあくまで過去の話です。
今回の論文で示される、レピュテーションリスクなどへのリスクマネジメントやミレニアル世代の社会貢献志向がESGを支持するという考え方は一理ありますが、アウトパフォームする論理的理由としては弱いように感じます。ESG関連投資は、景気後退を迎えても、過去と同じような相対的によい運用結果を残せるのか、注目されます。
最後に宣伝です。弊誌『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』のアドバイザー、児玉教仁氏が著した『グローバル・モード 海外の相手を動かすビジネス・ミーティングの基本』(ダイヤモンド社)が9月19日に発売されます。
児玉氏は、グローバル・リーダーの育成を担うグローバル・アストロラインズ社の代表で、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)ジャパンのアドバイザリー・ボードメンバーでもあります。三菱商事での14年間の勤務やHBSでの留学(同校MBA取得)の経験を基に、文化の違いを踏まえて、外国人と活発に議論するためのノウハウを存分に披露しています(編集長・大坪亮)。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)