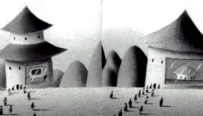●価格設定とプロモーション
売上高の減少に直面し、収益や売上総利益を維持するために、マネジャーは価格を上げたいという誘惑にかられる。なぜこれが悪手なのか、理解するのは難しくないだろう。景気後退によって、以前よりも消費者の価格感度が高くなっているため、ほんのわずかな値上げであっても、売上げをさらに押し下げることになるからだ。
結局、価格を上げてもすぐ値引きすることになり、効果を相殺してしまう。しかも、価格を頻繁に上げ下げすることは裏目に出ると、研究が示している。値上げを行った企業は、値上げを行わなかった企業に比べて失うマーケットシェアが大きいのだ。
●広告によるコミュニケーション
企業の大半が景気後退期にブランド広告を削減している間に、広告予算を維持あるいは増額できれば、広告の声が届く範囲は広くなる。
日用消費財メーカーのレキットベンキーザーの例を見てみよう。2008年の世界金融危機を端緒とする景気後退期に、同社はマーケティングキャンペーンを開始した。厳しい景気状況でも、高価格で優れた性能を備えたブランドを消費者に買い続けてもらうことを目指したのである。
競合他社がマーケティング費用を削減している時期に、レキットベンキーザーでは広告支出を25%増やした結果、売上げは8%、利益は14%上昇した。同じ時期に、競合他社の大半は10%以上の利益減を発表していた。レキットベンキーザーは、広告をコストではなく投資と見なしたのである。
景気後退期の広告コンテンツは、消費者が直面している困難な状況を反映しなければならない。不景気のまっただ中にある消費者は、ブランドに連帯感を示してほしいと思っている。
景気後退期にブランド広告で成功するためには、ユーモアや感情を注ぎ込むのに加え、消費者からの問いに答えなければならない。すなわち、「どうすれば消費者の助けになるか」である。
コカ・コーラの例を見てみよう。2020年、同社は広告予算を割いて、コロナ禍の最前線で働く人々の仕事ぶりを紹介した。影の英雄たちを取り上げた、一連のミニストーリーを制作したのである。
背景にはコカ・コーラのブランドがさりげなく入っている。これまでもこれからも、よい時も悪い時も、コカ・コーラは常に消費者のそばにいることを訴求したのである。
シンガポール航空も、同様の戦術を使った。新型コロナウイルスの感染拡大で地上にいることになった客室乗務員たちを、地元コミュニティの役に立てるように配置転換したことを紹介したのである。
客室乗務員たちはそのスキルを、ケア・アンバサダーとして活用した。患者のバイタルサインを測定して看護師を補助する乗務員もいれば、食事の注文を取ってそれを配る乗務員もいた。交通の要所では、人の流れを誘導して交通整理をしたり、安全な距離を保つガイドラインに従えるよう支援したりした。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)