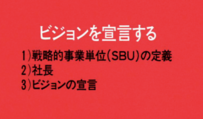-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ビジネスの世界がソフトウェアを中心とした変化を遂げる中、自社がどのような製品・サービスを提供するかにかかわらず、組織のアジャイル化が強く求められている。しかし実際には、製品開発に携わるチームはアジャイルでも、それ以外の部門では従来のやり方がまかり通る場合が少なくない。しかし、HRや財務のように組織のインフラともいうべき領域こそアジャイル化し、ソフトウェア主導のビジネスをサポートする基盤となるべきだ。本稿では、組織全体が本当の意味でアジャイル化するに何をすべきかを論じる。
ソフトウェアが世界を飲み込んだ。そして、新しく多様な産業を吸収し続けるうちに、ビジネスのやり方まで変えてしまった。いまや、誰もが「ソフトウェアビジネス」の中にいて、自分たちがどのような製品・サービスを提供するかにかかわらず、組織を構築し管理する方法の見直しを迫られている。
筆者がマネジャーに、組織レベルで「アジャイル」を実践しているかと尋ねると、ほとんどは「イエス」と答える。しかし少し掘り下げてみると、アジャイルなのは製品開発チームだけ、それもソフトウェアエンジニアリングの領域に限定されていることが多く、それ以外の部門はアジャイルでないことがほとんどだ。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)