
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「弱い紐帯の強さ」理論の因果関係を検証する
次に仕事を探す時のために、あなたは誰とつながるべきか。この問いに対する答えを見つけるため、筆者らは2000万人を対象とする複数の大規模ランダム化実験のデータを分析し、異なるタイプのつながりがキャリアの流動性に与える影響について調査を行った。
分析結果については2022年9月に『サイエンス』誌に掲載されたが、「最も強いつながり」、つまり直近の同僚、親しい友人、家族は実際に、新たな転職先を見つけたり、実際に仕事を得たりするうえで、最も役に立たないことが明らかになった。「弱いつながり」、つまり交流の機会が少なく、距離を置いた知り合いのほうが大きな助けになる。
さらに掘り下げると、新しい仕事を見つけるうえで最も助けになるつながりとは、「やや弱いつながり」である傾向が見られた。ふだんは接する機会が頻繁ではないが、
今回の分析結果からは、つながりの強弱(実際につながりを持つ前に、どれだけ共通の知り合いがいるか、その数に基づいて測定)と、求職者が何らかのつながりのある組織に転職する可能性との関係が明らかになった。
弱いつながりが仕事探しに役立つという知見自体は、新しいものではない。スタンフォード大学教授で社会学者のマーク・グラノヴェターが1973年に発表した画期的な論文で、この概念を初めて示し、ある人のネットワークが就職にどう影響するかを詳しく説明した。それ以来、「弱い紐帯の強さ」として知られるようになった理論は、社会科学で最も有力な理論の一つとして、情報拡散や産業構造、人間の協力に関するネットワーク理論の基礎を成すようになった。
グラノヴェターの仮説は長年にわたり、大きな影響力を持ち続けてきたが、その因果関係について大規模なデータを用いた決定的な検証は行われてこなかった。なぜならば、人のネットワークは仕事とともに進化するため、この理論を検証するのに必要な大規模実験を行うこと自体、極めて困難だったためだ。
また、それゆえ、この領域における研究のほとんどが相関分析を用いたものであり、実際に弱いつながりがあったから転職できたのか、あるいは2変数の関係を歪める第3の因子として、年功や会社の急成長といった交絡因子があったからなのかを知ることが難しかったこともある。

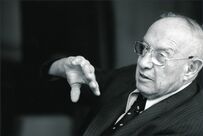








![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









