
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「いま買うべきかどうか」を決める要因
旅客機のチケットに始まり、靴下に至るまで、商品の過去の価格推移に関して詳細な情報を提供するオンラインショッピング・プラットフォームが続々と登場している。しかし、そのような情報は、消費者の購買の意思決定にどのような影響を及ぼすのだろうか。
筆者らは、この問いに対する答えを明らかにするために、米国と欧州のビジネススクールの学生および成人労働者の計5000人以上を対象に、一連の実験を行った。具体的には、さまざまな価格変化が、旅客機のチケット、テレビ、ブルートゥース・スピーカー、水筒の購買意欲に及ぼす影響について検証した。
いずれの実験においても、すべての被験者に同一の商品情報を提示した。ただし、それまでの価格変化の方向(価格が上昇してきたか、下落してきたか)と価格変化の頻度(値上げと値下げの回数)に関する情報については、異なる条件を用意した。それらの情報を示したうえで、その商品を「いま買いたいと思うか」を尋ねた。すると、いくつかの傾向が一貫して見えてきた。
まず、現在の価格が過去の価格よりも安い場合、消費者は「いま購入したいと思う」可能性が高い。現在の価格が好条件だと思うからだ。同様に、現在の価格が過去の価格よりも高い場合、「いま購入したいと思わない」可能性が高い。現在の価格が好条件だとは思えないからである。
たとえば、他の条件がすべて同じ場合、ある商品の価格が現在100ドルで、先週は200ドルだったとすれば、「いま購入したいと思う」可能性が高い。現在の価格が過去の価格に比べて、ずっと魅力的に感じられるためだ。逆に、現在100ドルの商品が先週は50ドルだったとすれば、購入を差し控える可能性が高い。現在の価格が過去の価格に比べて、魅力が乏しく感じられるためである。
しかし、価格変化の頻度という要素が加わると、話はもっと複雑になる。筆者らの研究では、これまでに3回以上、同じ方向の価格変化があったという情報が示された場合、消費者は「今後も同じ方向への価格変化が続く」と考える可能性が高くなる。これに対して、ある方向への価格変化が1回もしくは2回しか起きていない場合には、「逆の方向への価格変化が起きる」と予想するのだ。
つまり、現在100ドルの商品が、2週間前には200ドル、1週間前には150ドル、昨日は125ドルだったとすれば、消費者は「今後も値下がりが続く」と予想する。その結果、購入を控える可能性が高まる。
しかし、現在の価格が100ドルで、2週間前の価格が200ドルだったという情報しかない場合、もしくは2週間前には200ドル、1週間前には50ドル、現在は200ドルと推移しているという情報を示された場合には、消費者は「また値上がりするだろう」と考えて、「いま買うべきだ」と判断する。

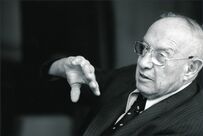




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









