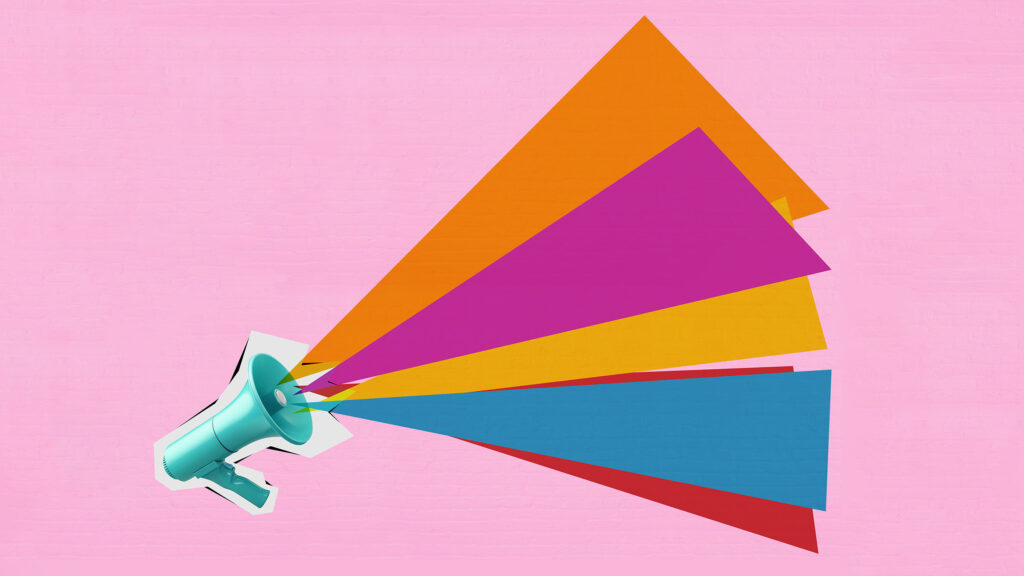
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
企業は社会問題への立場表明を
どう考えるべきか
社会を揺るがす事件が次々と起き、それが多種多様なメディアで大きな議論を巻き起こす現代。この世界に生きるリーダーにとって、コミュニケーションはソフトスキルではなく、必要不可欠なコンピテンシー(成果に直結する能力)だ。
そうしたリーダーたちが対応に最も悩む問題の一つが、「企業として、時事問題や最新の事件について立場表明をすべきか」だろう。米製薬大手ファイザーのサリー・サスマン最高コーポレートアフェアーズ責任者は、新著Breaking Through(未訳)で、そのヒントとなる枠組みを示している。本稿は、同書から一部を抜粋し、その内容を紹介する。
* * *
来る嵐に備えるのが、私たちリーダーの仕事だ。しかし、全方角に目を配るのは困難であり、起こりうる事態をすべて予見するのは不可能である。実際、そのようなことはできない。どれほど概要説明書や非常時対応計画、論点メモを作成しても、あらゆるシナリオを想定することなど絶対に無理なのだ。私がそれを実感したのは、2016年米大統領選の結果を受け、非常に多くのイシューにもみくちゃにされた時だった。
大方の予想を裏切って、ドナルド・トランプ大統領が誕生することが明らかになると、あらゆる問い合わせが洪水のように押し寄せてきた。大統領就任式の翌日にワシントンで予定されている「ウィメンズマーチ」を、ファイザーは支持するのか。科学者が保守派の科学的事実を無視した政策判断(気候変動やワクチン対策など)を批判
そこで私は立ち止まった。一つひとつのイシューについて会社の立場を表明したり、その是非を議論していたらきりがない。そこで時事問題について、事前に合意しておいた基準に基づき見解を示す、または示さない決断を下す枠組みをつくることにした。
考えてみると当然だ。それ以外の会社の大きな選択、たとえばいつ投資をするか、生産性をどう評価するか、リスクをどう計算するかなどは、事前に合意された一連の基準やハードルに基づき決定される。ところが、社会問題にいつ、どのように踏み込むかについては、はるかに漠然としていた。これは私の専門領域だが、財務や製造、法務などの分野のような厳格なルールがなかった。
そこで経営委員会のメンバーたちが、その判断基準づくりを手伝ってくれることになった。私たちは役員室に集まって、ブレインストーミングを開始した。率直に言うと、同僚たちの見解に耳を傾けるのはつらかった。コーポレートアフェアーズというものをわかっていない意見もあった。科学者や弁護士、会計士もいた。でも、私は自己防衛的な反応を示さないよう努めた。そして、同僚たちの意見にじっくりと耳を傾けたからこそ、さもなければ壁をつくって切り捨てていたかもしれない人たちからの優れた提案を聞くことができた。
彼らは皆頭がよくて、経験豊富なリーダーだ。彼らのインプットがあれば、私が考える枠組みはより強固になるに違いない。そこで、私は自分のエゴを抑えて、彼らの意見のメモを取り始めた。古臭いやり方だが、効果的だ。
私たちが構築した枠組みは、5つの問いから成る。
1. そのイシューは我が社のパーパスと関係があるか
この問いは、あらゆるイシューに意見表明をするのを防ぐ有意義なブレーキになる。すべての文化的な問題や社会運動に見解を示す必要はない。そもそも多くの場合、沈黙は金だ。
ほとんどの消費者は、あらゆる社会問題について、ファイザーであれ他の企業であれ、企業がどのような立場を取っているのか考えることなどない。ただ、ある企業の事業と関連があるイシューについては、その企業がどのような立場を取っているのか知りたいと思う。大企業では、社会的に議論を巻き起こしているあらゆる問題について、擁護者あるいは批判者がいるものだ。
だが、個人の関心が企業の方針を支配すべきではない。それに、すべてのイシューに同等の重みがあるわけではない。あまりにも多くのトピックについて声を上げると、当事者意識が低下する。また、会社としての立場を表明しすぎると、消費者は耳を傾けるのをやめてしまう。自社のパーパスに沿ったイシューに主張を集中させよう。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









