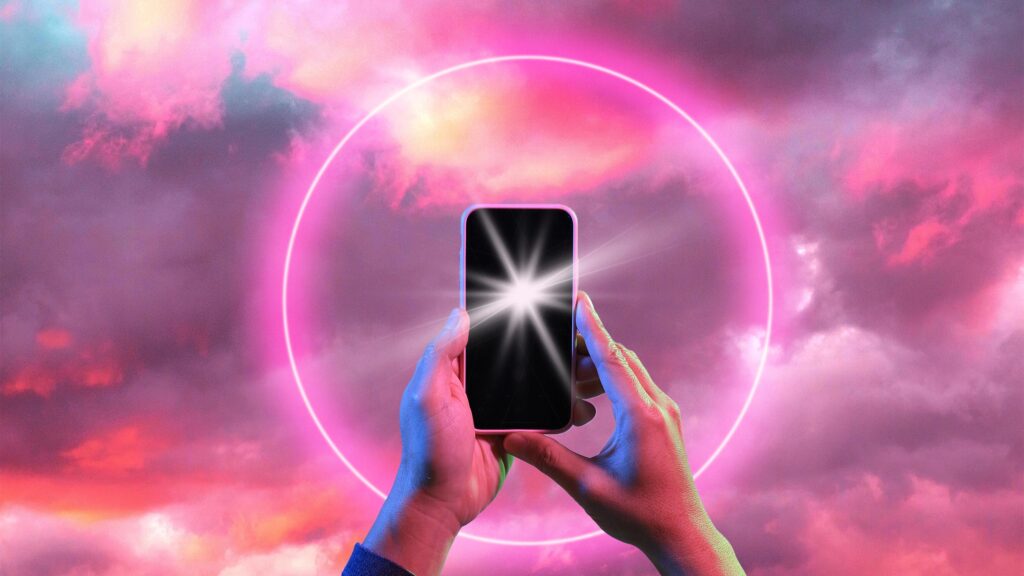
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
イーロン・マスクやザッカーバーグが示唆
この10年余り、アジアにおけるテック分野のエコシステムは、「スーパーアプリ」によって支配されてきた。スーパーアプリとは、ウィーチャット(WeChat)、アリペイ(Alipay)、メイトゥアン(Meituan)などのように、一つの統合アプリで膨大なサービスを提供するプラットフォームのことである。これに対し、米国では、類似のサービスが分散したまま存在し、多様なアプリやウェブサイトがそれぞれ限定的な機能を提供している。
しかし、最近のトレンドは、この違いが変化しつつあることを示唆している。イーロン・マスクは、ツイッターを買収した際、その買収で「万能アプリ」の開発が加速すると明言し、ツイッターが「ウィーチャットの対抗馬」になる可能性に言及した。マーク・ザッカーバーグもメタ・プラットフォームズとワッツアップ(WhatsApp)について同様の抱負を語っており、マーケットプレイスとチャットのプラットフォームを統合した「スーパーアプリのような構想」について述べている。
ウィーチャットの月間アクティブユーザーは10億人、アプリ上の「ミニプログラム」は100万以上存在する。こうしたプラットフォームがアジアで成長したことを考えれば、米国テクノロジー企業のリーダーがその後に続きたいと考えるのも無理はない。しかし当然、米国市場はスーパーアプリが発展した市場とは大きく異なる。成長の道筋や市場の位置付け、法規制、技術、文化的背景が大きく異なるのだ。そうした点を踏まえると、米国でも何らかのスーパーアプリが開発される可能性はあるが、それは真にスーパーというよりはスーパー「的な」ものになる可能性が高い。
スーパーアプリとは
スーパーアプリは、モバイルデバイスやウェブブラウザからアクセスでき、日常生活や普段の商取引に役立つ多様なサービスを提供する。共通の決済プラットフォームを利用し、アプリ内のデータを活用することでニーズに合わせてサービスを組み立てることが可能な単一のアプリであり、広く採用されている。
提供するサービスは、SNSやメッセージング、交通機関や旅行、病院の予約、フードデリバリー、資産管理、Eコマースサイト、ビデオゲームなど、数え切れないほどある。一つのカスタマージャーニーの中に複数のサービスを組み込めるため、ユーザーエンゲージメントの向上だけでなく、強力なネットワーク効果とスイッチングコストによって、ユーザー、売り手、広告主の囲い込みにもつながっている。
また運営各社は、アプリのクローズドプラットフォームの中で収集された、多種多様なユーザーデータにアクセスできる。このデータを分析することで、消費者の細かな嗜好の把握、広告のターゲティング、おすすめ商品や割引、価格、ロイヤルティ報酬のパーソナライズ、クロスセリングの促進などを行い、大きな価値を生み出すことができる。
興味深いことに、スーパーアプリは、提供するサービスによって、企業収益への貢献度に差がある。たとえばメイトゥアンは、ホテルや旅行の予約で利益の大部分を得ているが、ユーザートラフィック(サイト訪問回数)の大部分はフードデリバリーサービスから得ている。同様に、アリペイは少額融資から利益を得ているが、低額か無料の決済サービスを通じてユーザーの大半を獲得している。スーパーアプリのモデルは、補完的なサービスを戦略的に組み合わせ、価値を創造し、ユーザーの獲得を可能にする。その方法として、実質的なロスリーダー(採算度外視の客寄せ商品)のサービスが使われることが多いのだ。
スーパーアプリはアジアを席巻しているが、米国では普及していない
スーパーアプリは、この10年で、東アジア、東南アジア、そして西アジアの一部を席巻した。その多くは、低所得国が起源である。中国のウィーチャット、アリペイ、メイトゥアン、インドのペイティーエム(PayTM)、タタニュー(Tata Neu)、インドネシアのゴートゥーゴジェック(GoTo GoJek)、ベトナムのザロ(Zalo)などである。
アジアの富裕国でもスーパーアプリは普及している。韓国のカカオトークは、ウィーチャットより1年早い2010年に設立され、国内人口の87%をアクティブユーザーに持つ。韓国生まれで東京に本社があるLINEは、日本で広く利用されている。マレーシアで創業したグラブ(Grab)は、本社が置かれたシンガポールで普及している。
一方、アジア以外では、機能的に類似したサービスを提供する個別のアプリは数多くあるが、米国ではスーパーアプリ型の統合プラットフォームはまだ出現していない。なぜ米国では、アジア型のスーパーアプリが普及していないのだろうか。それには、以下のような要因がある。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









