
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
論文で読み解く、没後20年を迎えるドラッカーの慧眼
2025年11月11日で、没後20年を迎えるピーター F. ドラッカー。その慧眼は、数多くの経営者やビジネスパーソンの指針になってきた。さらに、今日のように混迷を極め、分断の進む時代においては、ドラッカーの言葉の数々が私たちの生き方にヒントを与えてくれる。
そこで今回編集部では、『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』(DHBR)2025年12月号の特集「P. F. ドラッカー 真摯さとは何か」を企画するに当たって読者にアンケートを実施し、ドラッカーが『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)に寄稿した34本の論文から、いまこそ読み返し、次の世代にも読み継がれてほしいと思う論文を挙げていただいた。得票数の最も多かった論文はDHBR2025年12月号で全文を、読者からの得票と識者からの推薦があった編集部おすすめの論文3本は抄訳を掲載している。
本稿では、アンケート結果をランキング形式で紹介するとともに、読者が語るドラッカーの各論文の読みどころ、影響を受けたフレーズや内容を解説する。さらに、編集部がおすすめする論文も2本紹介したい。
※アンケートは、DHBR電子版会員を対象に、2025年7月20日~8月3日に実施した。
5位「プロフェッショナルを活かす」
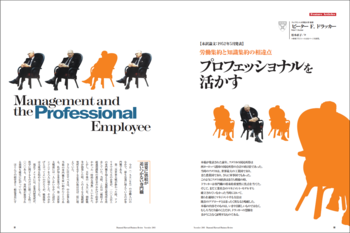
論文「プロフェッショナルを活かす」(DHBR2003年11月号掲載)
5位には、同数で4つの論文が選ばれた。まず1つ目の論文が「プロフェッショナルを活かす」だ。この論文は1952年に記されたもので、工業社会の経営モデルすら存在しなかったその頃にあって、ドラッカーが専門職の将来的な重要性を喝破し、その管理方法について提示した点でも画期的だった。第2次世界大戦後の当時、専門職への需要は高まる一方だったが、その行動様式への理解不足から、優秀で希少な多くの専門職が非効率的な働き方を強いられていた。本稿では、企業との間に生じる摩擦を解消するためにはどうすればよいのかを説いている。
以下、投票していただいた読者の声を紹介しよう。
「現在外資系企業で人事職(HRBP)に従事している。『専門職には、従来のあらゆる人事管理の方針、手法、手順を適用してはならない』とあるが、もはや一般職と専門職という区分では十分でなく、各職群の中でも専門性が細分化されており、時には職種ごとに評価などを含めた人事管理を検討しなければいけない時代にあると思っている。この点で、この論文で述べられている内容は大きな示唆を与えてくれる」(40代男性、東京都、その他、総務/人事、課長職)
5位「人事の秘訣:守るべき5つの手順」
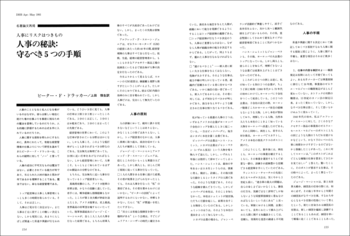
論文「人事の秘訣」(DHB1993年4-5月号掲載)
5位に選ばれた2つ目の論文が、1985年の論文「人事の秘訣:守るべき5つの手順」だ。
人事の決定は、影響が大きく、取り消しもきかない。本論文では、人事にうまく取り組むには、4つの原則に従い5つの手順を守り、それにつきものの問題を理解することが重要だと説いている。
「自分が人事総務部長であるからというのもありますが、非常に影響を受けました。特に人事の失敗で、『後家づくり』ポスト、つまり有能と思われる人材が立て続けに失敗しているポストは廃止すべきというのは感銘を受けました。現実的には、なかなか難しいですが、事実だと思います」(50代男性、東京都、製造業、総務/人事、役員)
「(論文の中で記されているように)「あれがこの会社で出世する方法だ」と頷かれるようであってはならない。やがてみんながうまく立ち回ろうとするようになる。そして、そのような行動を取らせる会社を恨む。事実、追従家となるか、あるいは辞めていく。実際、自分自身が会社を去った」(50代男性、愛知県、運輸/エネルギー関連、経理/財務、部長職以上)
5位「マネジメントの新たな役割」
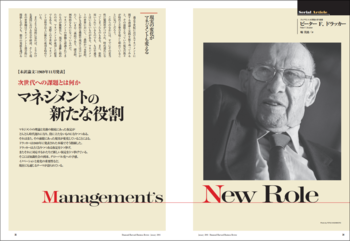
論文「マネジメントの新たな役割」(DHBR2004年1月号掲載)
同じく5位に選ばれたのが「マネジメントの新たな役割」だ。
ドラッカーは1969年に発表した本論文の中で、マネジメントの理論と根底にあった仮定が、現実の変化によって時代遅れになりつつあると指摘した。そのうえで、時代の間尺に合わなくなってきた仮定を5つ挙げ、それに対する新しい仮定を5つ挙げている。同論文では、知識社会の到来、グローバル化への予感、イノベーションと変化の重要性など、現在にも通じるテーマが語られている。
「マネジメントを科学的なアプローチで分析していて、現在のビジネスにも通用する」(50代男性、東京都、金融/証券/保険、マーケティング/調査、課長職)
「『マネジメント力を生み出すことができたケースは数少なく、ただしこれらのケースが急速な経済発展に成功している。経済力ではなく人間力の問題だったのだ。人間力の醸成と方向性がマネジメントの課題となる』とあるように、行き着くところ人間力が占めるところが大きいと感じている。この人間力はすぐに身につくものではないため、若いうちから人間力を涵養するほかない。そのための仕掛け、仕組みづくりが喫緊の課題である。まさにその課題解決に向けて、志高いメンバーを招聘し着手したところである」(50代男性、東京都、金融/証券/保険、総務/人事、部長職以上)
5位「意思決定の秘訣」
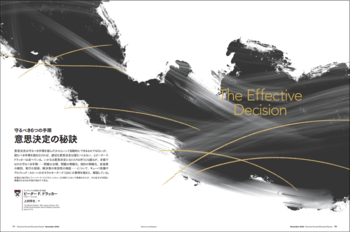
論文「意思決定の秘訣」(DHBR2024年11月号掲載)
5位の4つ目の論文として、「意思決定の秘訣」が選ばれた。意思決定は守るべき手順を踏んだからといって自動的にできるものではないが、踏むべき手順を踏まなければ、適切な意思決定は望むべくもない、とドラッカーは述べる。いかなる意思決定にもリスクは伴うとも語るが、本論文ではその守るべき手順──問題の分類、問題の明確化、目的の明確化、妥協策の峻別、実行の担保、解決策の有効性の検証──について、キューバ危機やアルフレッド・スローンのゼネラルモーターズ(GM)の事例を踏まえ、解説している。
「意思決定のプロセスが明確に整理されている」(50代男性、神奈川県、製造業、経営企画/事業開発、部長職以上)
「意思決定に至るプロセスをモニタリングする仕組みが重要。人間は間違えるが、その後の経営環境の変化の結果であれば、また、その意思決定を修正することも可能になる。この考え方は、現在のコーポレートガバナンス改革で、最も難しい『取締役会の企業強化』をどのように進めるかの本質論にもなっている。コーポレートガバナンスでは、間違えた経営者を、社外取締役が中心となって組成する指名報酬委員会に新しいCEOを選ぶ権限を与えることで克服しようとしているが、その委員会のメンバー構成とその委員会の判定能力の客観的な指標には確たる評価システムは存在していない。そんな課題も考えさせてくれる論文である」(60代以上男性、東京都、経営者)
4位「マネジメント:未来への課題」
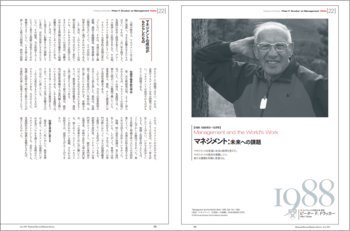
論文「【抄訳】マネジメント:未来への課題」(DHBR2010年6月号掲載)、初出「マネジメント 21世紀への挑戦」(DHB1989年1月号)
4位には、「マネジメント:未来への課題」が選ばれた。本論文は1988年に記されたもので、マネジメントが急速に社会と経済を変えた点を指摘しており、マネジメントの歴史を俯瞰したうえで、マネジメントとは何かを的確に説明している。
「(この論文から得られることは)大きく2点ある。1つ目は、マネジメントの本質は『人』であるということ。たとえ、ITやデジタル化、AI導入が進んでも、知識労働者や現場スタッフが成果を出せる風土・構造をつくることが幹部の最大のミッションである。『個の力×チーム力』が最大化される環境整備が不可欠であるということ。もう一つは、現場の変化と学習が最大の競争力であるということ。デジタル化・AI活用の時代だからこそ、『現場が学び、変化し続ける力』が競争優位の源泉となる。経営幹部は『学習する組織』を目指し、常に訓練・アップデート・振り返りを仕組み化しなければならない」(50代男性、東京都、流通/小売業/外食、技術/研究開発、部長職以上)
3位「経営者の真の仕事」
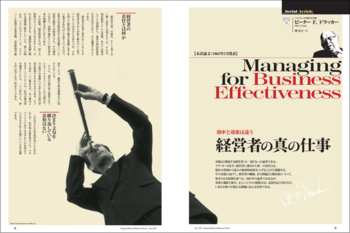
論文「経営者の真の仕事」(DHBR2004年4月号掲載)
3位には、「経営者の真の仕事」が選ばれた。本稿は1960年代に記され、書籍『創造する経営者』の一部となった論文である。ドラッカーはまず、経営者に課せられた第一の責任とは、現有の資源から最大の経済的成果を挙げることだと指摘する。その実現に向けて、経営者の職務、また問題点と解決策について、基本となる原則を述べている。1963年の論文ではあるが、事業の選択と集中、正しいコストの把握方法、意思決定と実行など、いまなお私たちが抱える課題に応える内容である点も読みどころだ。
「ドラッカーの『経営者の真の仕事』を再読し、『経営者の仕事の核心は成果を上げること』に尽きるとあらためて認識します。単なる業務管理や人事評価に留まらず、成果を通じて社会や組織、自身に価値を生み出す使命を、ドラッカーは明快に提起している点は、発表されてから年月が経っていますが、内容としては極めて新鮮に感じます。特に、職業倫理が揺らぎやすい現在、ドラッカーの『意思決定』『優先順位の設定』『時間管理』『貢献への執着』という行動原則が、迷いなく責任を実行する力を私たちに与えていると感じます」(60代以上男性、神奈川県、専門職)
「経営者の仕事を分析、配分、意思決定の3つに整理したところは、複雑で多様な要素に惑わされがちな特に現在のような複雑な時代において、常に頭の整理につながる整理方法だと思う。自身がかつてハーバード・ビジネス・スクール(HBS)でMBA課程にいて、毎日何十ページのケースを読んでいたが、各ケースの個別性に惑わされていたことを思うと、ドラッカーの特異な類型化・普遍化はあらためて貴重だと思う」(60代以上男性、千葉県)
DHBR2025年12月号では、3位になった同論文の抄訳を掲載している。記されてから60年以上が経過してもなお、現在私たちが抱える課題に応えてくれるこの論文をぜひお読みいただきたい。
2位「経営者の使命」
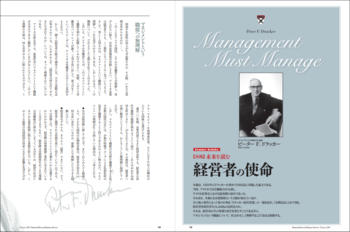
論文「経営者の使命」(DHBR2009年2月号掲載)
2位に選ばれたのは、「経営者の使命」だ。本稿は、1950年にドラッカーが初めて『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)に寄稿した論文である。当時、アメリカでは労働組合が台頭し、アメリカ産業史における混沌期の最中だった。そのため、本稿にも労使関係という文脈が流れているが、その後の著作で私たちが知る「ドラッカー経営思想」の一端を垣間見ることができる。経営者を経営者たらしめるものは何なのか。それはまず、経営者がその役割と責任を果たし、リーダーシップを発揮すること。そして、マネジメントという職能について、社会が正しく理解することであるとドラッカーは指摘する。
「経営者が社会に対して何ができるか、何をすべきかを論じたところが印象に残った。貢献をキーワードに経営者のあるべき姿を明らかにした、経営に携わるすべての人が読むべき論文」(60代以上男性、神奈川県)
「経営者には、経営者としての心構えや意識、日頃から取り組んでおくべき必要な事柄があるかと思いますが、重責を担うに当たって(この論文に記されている内容は)必読であると考え、選択しました」(40代男性、埼玉県、一般社員)
1位「プロフェッショナルマネジャーの行動原理」
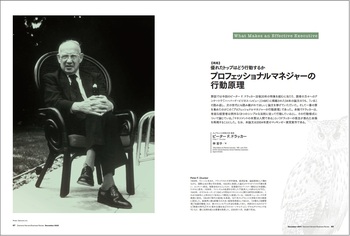
論文「プロフェッショナルマネジャーの行動原理」(DHBR2025年12月号掲載)
今回の読者投票で1位に選ばれたのは、2004年のマッキンゼー賞も受賞した「プロフェッショナルマネジャーの行動原理」だ。偉大な経営者と呼ばれる人々の中にも、カリスマもいれば、退屈な人物もいる。気前のよい人もいれば、けちな人もいる。とはいえ、有能な経営者たちは例外なく、8つのシンプルな法則に従って行動していると説いているのがこの論文だ。有能かつ業績に優れた経営者であるには、どのような行動様式が必要なのかを考えるきっかけになる。実際に、この8つの法則が印象に残っているという読者からの推薦の言葉が多数寄せられた。
「(論文で触れられている内容が)現在の経済・世界状況においてもいえることだと思いました。(有能な経営者の8つの習慣の一つにある)『正しいことを成し遂げること』が私の価値観とも合い印象に残っています。その『正しさ』は状況や条件により変わってくるものなので、それを踏まえて考え、舵を取ることがマネジメントなのだと受け取っています」(40代女性、東京都、製造業、購買/資材/物流、課長職)
「最も印象に残っているのは、『有能な経営者は、今日最も一般的に使われている意味での「リーダー」である必要はない』の部分。8つの習慣はすべてが納得できる内容であり、現在でも変わらないものである」(60代以上男性、神奈川県、製造業、デザイン/設計、一般社員・職員)
「経営者のみならず、有能な人物を観察していると常に内省を怠らず、正しいことなのか否かで判断し、実行できる状態にまで落とし込み責任を負う姿が目に飛び込んでくる。それでいてチャンスを掴むためのアンテナは張っており、いつでもチャンスをつかめるように生産性の向上に手を抜かない。そして(この論文でドラッカーが語っているのと同様に)「私」ではなく常に「我々」を主語にして語っている。こういう人から学び、伝える側に立っていきたいと思っている」(40代男性、東京都、通信サービス、情報システム、係長・主任)
「有能な経営者の8つの習慣は、いまでも色あせることのない本質を描いていると感じるからです。特に、(8つの習慣の一つである)『チャンスに焦点を当てる』は、成長マインドセットのカルチャー醸成に取り組んでいる自分自身にとって、物事を見る目を変えるリフレーミングの重要性を再認識させられます。問題や変化に直面するたび、『できないことではなく、できることに集中』というセルフトークをします」(50代女性、東京都、製造業、総務/人事、部長職以上)
DHBR2025年12月号では、1位になった同論文を全文掲載している。ぜひこの機会にあらためて読み直していただきたい。
編集部おすすめ「多元化する社会」
ここからはDHBR編集部がおすすめしたい論文を2本紹介する。まず一つ目が「多元化する社会」だ。
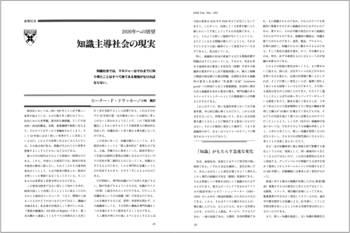
論文「多元化する社会」(初出「知識主導社会の現実」<DHB1993年3月号>として掲載)
米HBRでは1992年に、日本版は1993年3月号に「知識主導社会の現実」というタイトルで掲載された。DHBR2025年12月号で、ドラッカーの人生と思想について解説した田中弥生氏は、この論文にある「もし歴史を参考とするならば、今日のこの転換期は、2010年、ないしは2020年まで続く」という一節を紹介している。ドラッカーは同論文で、この転換期において「その詳細を予想することは危険である。しかし、今後いかなる問題が登場するか、いかなる領域にいかなる課題が存在するかについては、すでにかなりの程度を明らかにできる」と述べており、30年も前に今日の様相を予期していたことがわかる。
DHBR2025年12月号では、「多元化する社会」の抄訳も掲載しているので、ぜひご一読いただきたい。
編集部おすすめ「自己探求の時代」
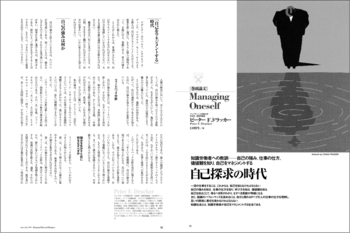
論文「自己探求の時代」(DHB1999年6-7月号掲載)
もう1本、自己成長を目指す読者にDHBR編集部がぜひおすすめしたいのが、1999年に記された論文「自己探求の時代」だ。
ドラッカーは、同論文で50年にも及ぶ職業生活を送る人々に対し、誰もが自己をマネジメントする重要性を説く。ドラッカー自身も50年続けてきたという、フィードバック分析によって自己の強みを知ることができ、自分が行うべきことが明らかになると述べている。
「『最初に知っておくべきことは、読んで理解する人間か、聞いて理解する人間か、ということである』というフレーズは印象に残っている。自分自身が、耳からの情報だと理解に時間がかかるが(理解できないことすらある)、文字のコミュニケーションだと一瞬で伝達・理解できる(記憶にも残る)ことに最近気づいたため。組織においてこういったことに各々が気づかないままだとコミュニケーションの速度・質はかなり落ちると考える。組織の成果にも大きくかかわってくるので互いに知っておくべきとても重要なことだと感じる」(30代、兵庫県、医薬品/化学製品製造、技術/研究開発)
DHBR2025年12月号では、「自己探求の時代」の抄訳も掲載しているので、ぜひご一読いただきたい。
* * *
ドラッカー論文は、記された年代にかかわらず、現在にも通じるテーマを扱い、また参考になる考え方を示してくれている。以前ドラッカー論文を読んだという人も、まだドラッカー論文を一度も読んだことがないという人も、この機会にあらためてドラッカーの思想に触れてみていただきたい。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









