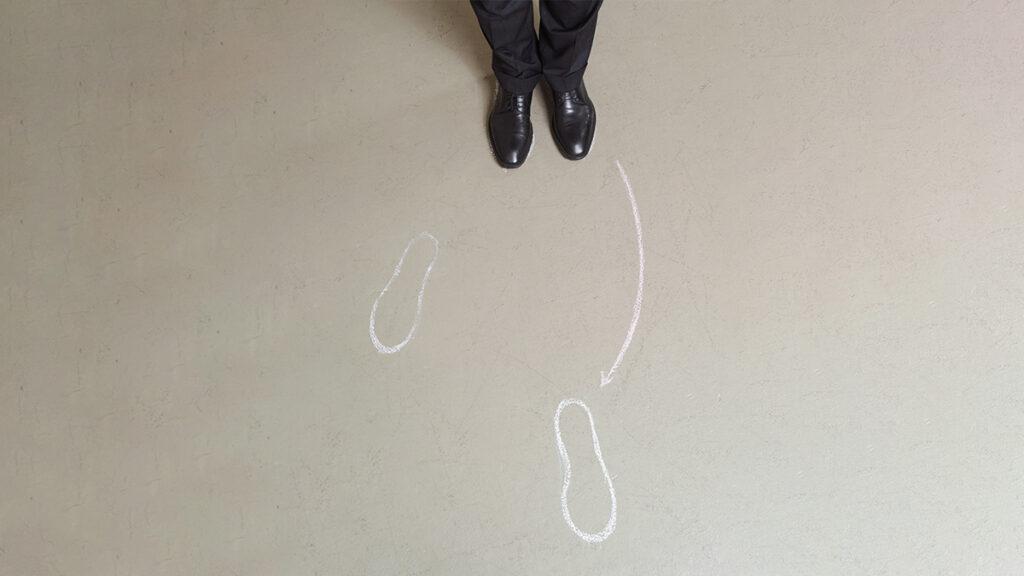
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
社員たちの関わり方と上級幹部の役割
変革のマネジメント(チェンジ・マネジメント)の要諦の一つは、「ステークホルダーを関与させること」である。つまり、その変革によって影響を受ける人たちを変革のプロセスに参加させることが望ましい。ゼネラル・エレクトリック(GE)の有名な「変革促進プロセス」(CAP)は、それを「コミットメントを引き出す」という言葉で表現し、HBS名誉教授のジョン P. コッターが提唱する8段階の変革プロセスでは、「変革を推進する連合体を築く」ことと「ボランティア部隊を集める」という言葉でその重要性を強調している。
コンサルティング会社のマッキンゼー・アンド・カンパニーは、どれくらいの数の人たちを変革のプロセスに参加させるべきなのかを調べたことがある。その調査によると、社員の少なくとも7%は、変革のいくつかの側面に当事者として関わらせるべきだという。
しかし、大勢の人を変革のプロセスに関わらせることにより、物事が加速するのではなく、減速してしまう場合は、どうすればよいのか。筆者のコンサルティング経験からいうと、中規模企業では、そのような状態に陥る危険が常について回る。特に、社員にあらゆる情報を開示して、社員が高い「帰属意識」を抱く組織文化を育もうとしている企業では、そのリスクを見過ごせない。
社員は、自分が会社のステークホルダーだと感じていれば(それ自体は好ましいことだ)、変革の内容について自分にも発言権があってしかるべきだと考える。しかし、すべての人が満足する変革などありえない。そのため、大勢の人をプロセスに参加させると、意思決定に長い時間を要したり、何も決められない状態に陥ったりする。
一つの会社の例を手短に紹介しよう。あるテクノロジー企業は、世界で約1800人の社員を擁していたが、成長が停滞し始めていた。戦略コンサルタントの指摘を受けて、この会社の幹部チームは、ソフトウェアの法人向けの販売にいっそう注力すべきだという点で意見が一致した。
すべての社員に自社の最新の状況を知らせるという組織文化に則り、同社のCEOは新しい戦略目標と、その変革がもたらす影響全般を社員集会で説明した。その後、プロダクト部門、オペレーション部門、セールス部門、マーケティング部門で多くの社員が参加するチームが設けられて、法人向けの売上げを増やすための具体的な計画が話し合われた。
しかし、このようなチームに参加した人たちは、誰もがみずからの職と、部署の予算および組織を守りたいと考えていた。その結果、どのチームから提案された計画にも、新しい取り組みに注ぎ込むリソースを増やすのと引き換えに、既存のどの活動を取りやめたり、先延ばしにしたりすべきかという提案は含まれていなかった。社内の誰もが法人向けの売上げを増やすことの重要性は理解していたのに、その目標に向けた実質的な前進はほとんどなかった。
これは、けっして特殊な例ではない。数カ月前、筆者はあるビジネスリーダーの話を聞いた。その人物の会社では、政治的要因と規制関連の要因により、ある国における顧客との取引を打ち切る必要に迫られていた。このリーダーは、社内に大規模な特別チームをつくって、この変革により影響を受ける顧客を洗い出し、変革が会社にもたらす財務面の影響を調べ、サービスを「打ち切り」にするためにどのような技術サポートが必要かを明らかにするという任務を課した。しかし、特別チームは、自分たちが何をすべきか、それをどのように行うべきかについて、なかなか合意に達することができなかった。
セールス部門は、大口顧客の契約をほかの国に移して、売上げを維持すべきだと主張した。しかし、オペレーション部門は、そのためには多くの手続きが必要になり、その一つひとつについて官庁の承認を受けなくてはならないという懸念を示した。プロダクト部門は、その方針を採用した場合に、残るすべてのプロダクトの提供を継続できるか定かでないと言い、検討のための時間が欲しいと述べた。一方、財務部門は、契約をほかの国に移すべき顧客と、サービスの提供を打ち切るべき顧客の線引きの基準を確定するため、財務モデルをつくりたいと考えた。こうして、一言でいえば、この会社は袋小路にはまり込んでしまったのだ。
このような事例を見ると、社員の関与を増やすことは変革のマネジメントに壊滅的な悪影響を生むので避けるべきだ、という結論に飛びつきたくなるかもしれない。CEOなど、一人の上級幹部がほかの全社員に対して、どのように行動すべきかを言い渡すほうが手っ取り早いようにも思える。そうすれば、いわば「船頭多くして……」という事態は避けられるだろう。

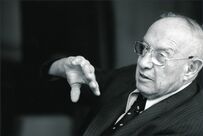




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









