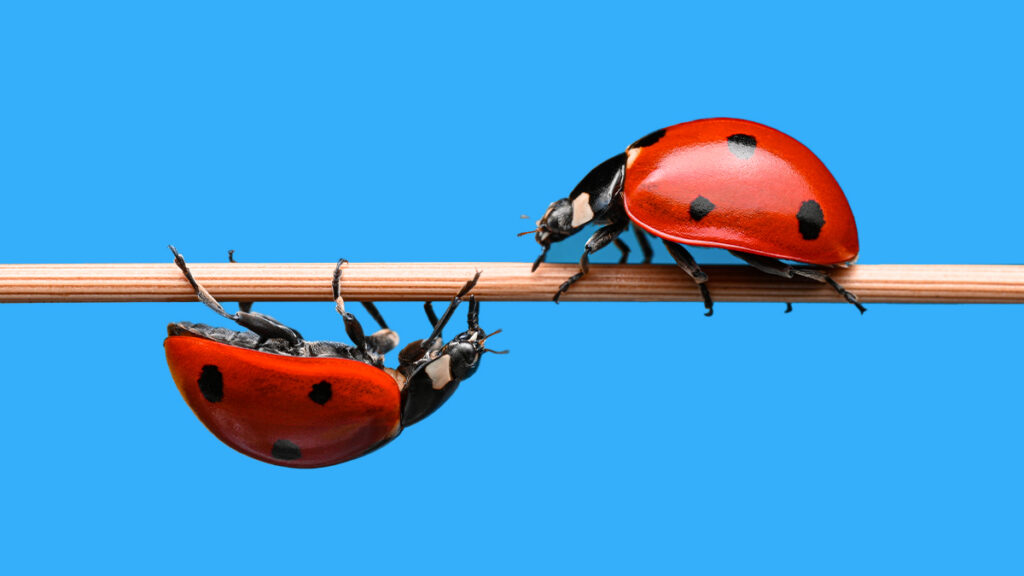
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
新たな選択肢をつくり続ける重要性
筆者らは、最近のHBRの論考で、企業は先の読めない変化の激しい世界において、ラディカル・オプショナリティ(徹底した選択性)を前提とした経営戦略を採用する必要があると主張した。それは、予測不能な状況に置かれることを想定しながら、将来の成功の基盤になりうる新たな選択肢をつくり続けるという考え方である。
しかし、企業はなかなかラディカル・オプショナリティを実現することができない。なぜなら、選択肢をつくるにはコストがかかるからである。可能性の検討は、高いコストとリスクを伴い、複雑性を増し、過剰な冗長性をもたらしかねない。さらに、経営資源の限界、特に資本コストの増大がさらにハードルを高くしている。
前述した論考で述べたように、これには、戦略に付き物だったトレードオフを打破することに加え、戦略に対する考え方、コミュニケーション、リーダーシップに関する新たなアプローチも必要となる。本質論として、我々は、もはや戦略が単一の不変のロードマップではなく、まったく新しいプレーブックを必要とする「可能性のポートフォリオ」であることを認めなければならない。このラディカル・オプショナリティという新たな世界で成功するために、マネジャーやリーダーは、以下のことを受け入れる必要がある。
アイデアの非両立性と不整合性
企業や個人は、複数の計画やタスクに同時に取り組んでいる。通常、これらの活動自体は大きく異なるものであっても、基本的には一つの戦略や将来像に合致しているという前提がある。
しかし、「可能性のある複数の未来の状態」に応じた選択肢を用意している組織では、場合により、補完的でない、あるいは両立しない選択肢を同時に追求する必要がある。
たとえば、エヌビディアは、コンシューマー向けにグラフィックカードを販売しているが、クラウドベースのサブスクリプションサービスも構築している。後者を使えば、遠隔地から処理能力の高いグラフィックツールにアクセスし、ゲームやその他のソフトウェアを(エヌビディアが搭載されていない)デバイスにストリーミングできる。この場合、たとえばストリーミングの待ち時間を短縮するなどの問題を解決すると、エヌビディアのクラウドベースのサービスの魅力は増すが、従来のハードウェアビジネスの魅力は、直販とのカニバリゼーションにより低下する可能性がある。
選択性を高めるには、このような相容れない選択肢を持つことの潜在的な利点を認識する必要がある。たとえば、収入源が多様化することによるレジリエンスの向上や、
将来の勝者になるには、同様のやり方で、不整合を選択的に受け入れることが必要だ。未来に関する多様な説を受け入れ、その結果生まれた「可能性の樹形図」の枝々を検討し、未来の展開を見据えながらフォーカスとリソースを移動させるのである。
未来に対する見解が多様であることは、組織のステークホルダー内の整合にも影響する。「同じ船に乗る仲間」のイメージは魅力的だ。みんなで息を合わせて漕げば、それだけ早く効率的にゴールにたどり着ける。しかし、不確実性が高い世界では、目的地がどこなのか、あるいはその船が目的地に行くための最適な選択肢なのか、必ずしもわからない。
つまり、完全なる整合を目指すことは、もはや正しいこととはいえない。先の見えない未来に対して、企業は多様な(現実)認識と(未来)視点を育み、それらを社内でぶつけ合い、掛け合わせのイノベーションによって新たなアイデアを引き出し、企業の将来性を高めていく必要がある。
物語の多重性と不統一性
我々は便宜上、複雑な現実を単純化し、魅力的なストーリーを描いて戦略を語ることがよくある。しかし、将来に向けて、潜在的に相容れない複数の選択肢を追求するとなると、単一不変の戦略的物語に頼っていられなくなる。むしろ、複数の選択肢を追求し、途中で切り替えられるようにするためには、複数のストーリーとその書き換えを認め、共有することが必要になる。
たとえば、マイクロソフトは称賛を浴びたここ数カ月のAI戦略において、自社のソフトウェアがコーチ、アシスタント、自動化エンジンの役割を果たすことを強調する発言をしている。そのストーリーの中には、人間を明示的に登場させたものもあれば、そうでないものもある。これらのストーリーがすべて同時に、同じ文脈で、同じオーディエンスに対して現実になることはありえないが、マイクロソフトは、状況が急速に発展する中で、物語も、提供する製品やサービスも継続的に進化させる能力によって、適時性を保つことができている。
このような多重の物語から成る世界では、企業は、一貫して安定した物語の実現という目標(誠実さの証のように見なされてきた)を手放し、代わりにバリエーションと変化を受け入れる必要がある。
ルイス・ガースナーは、「一貫性のないコミュニケーション」を成功させた一人である。1993年4月にIBMのCEOとして招聘された彼が、投資家やマスコミに「IBMにいま最も必要ないものは、ビジョン」であり、合理化と実行に注力すると宣言したのはよく知られている。しかし実際には、「企業がインターネットを活用したビジネスを展開できるようにする」という新たなビジョンを推進した。就任後1年も経たないうちにこのビジョンを公表し、その直後に5億ドルの広告キャンペーンを打って、IBMがこの分野の先駆者となるきっかけをつくったのである。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









