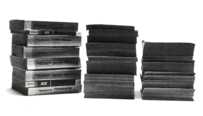-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
循環型経済への移行を妨げる数々の障壁
世界経済はいまだに、原材料の採取→生産→消費→廃棄という直線的なプロセスで動いている。地球上の資源が有限であることを考えると、このような状況には問題があると言わざるをえない。しかし、循環型経済(サーキュラーエコノミー)への移行はまだ実現したとは言いがたく、企業が自社のバリューチェーンで用いた資源を回収したり、リサイクルしたりするようにはなっていない。実際に移行できれば、何兆ドルもの価値をもたらすにもかかわらず、だ。
循環型経済への移行を妨げる障壁としては、使用済み製品の残存価値が小さいこと、資源の回収が難しいこと、資源の分別・処理に要するコストが途方もなく大きいこと、リサイクルされた製品や資源のトレーサビリティが乏しいことなどが挙げられる。
この分野におけるイノベーションと学習を加速させるために、ハーバード・ビジネス・スクールの「デジタル・データ・デザイン(D3)研究所」はこのほど、循環型経済をテーマにしたイベントを開催した。このイベントでは、起業家やビジネスリーダーたちが集まり、先に挙げたような障壁を克服して、まったく新しい市場とビジネスモデルをつくり出すために、どのようにデジタルツールと人工知能(AI)を活用すべきかについて情報交換した。
このイベントを通じて、より循環型経済を実現するための3つの主要な方法が見えてきた。その3つの方法とは、製品を長く使うこと、資源の効率を高めること、そしてリサイクル資源を活用することである。
製品を長く使う
1つ目の方法は、製品が用いられる期間を延ばすことだ。そのためには、たとえばシェアリングエコノミーのプラットフォームを活用したり、中古品や長期在庫品の再生(リファービッシュメント)を推し進めたり、製品の耐用年数を向上させたりすればよい。
企業が製品の寿命を延ばすために実践している取り組みの一つは、製品の残存価値を大きくするためにソフトウェアの「(無線通信を経由した)OTAアップデート」を行うというものだ。
iPhoneは、そのよい例といえるだろう。アップルのスマートフォンであるiPhoneは、中古市場で売買されている約3億台のスマートフォンの何と80%を占めている。ハーバード・ビジネス・スクール「D3研究所」の前述のイベントで、携帯通信大手のスプリントとソフトバンクグループインターナショナル(SBGI)のCEOを務めたマルセロ・クラウレが語ったところによると、その主な理由は、このスマートフォンで用いられているオペレーティングシステム(OS)である「iOS」の「前方互換性」にあるという。ユーザーがアップルのアプリのエコシステムにアクセスすれば、アップルがリリースする新しい機能をすべて利用できるようになっているのだ。その結果として、スマートフォンの中古市場でiPhoneが高い人気を誇っているのである。
ソフトウェアのOTAアップデートは、スマートフォンだけでなく、ほかの多くの製品でも当たり前のものになり始めている。その点では自動車も例外ではない。中古品の残存価値を向上させ、製品が用いられる期間を長くするためには、このような方法もあるのだ。
製品の寿命が長くなると、売上げを増やす妨げになる可能性があるという理由で、企業は自社製品を計画的に「陳腐化」する戦略を採用すべきだという考え方も根強くある。しかし、今日の有力企業は、製品の耐用年数を延ばすことを利益に転換できるビジネスモデルを築くことも可能だと考えている。具体的には、製品を長く使えるようにすることにより、新しい消費者との接点を確立し、顧客満足度を向上させ、さまざまなサービスを提供するモデルである。実際、アップルでは、サービス部門の会員数が9億3500万人を数えている。同部門の年間売上高は800億ドル近くに上り、粗利益はハードウェア部門の2倍近くに達している。
製品が用いられる期間を延ばすためのもう一つの方法は、「プロダクト・アズ・ア・サービス」(PaaS)のモデルを採用するというものだ。製品の所有権は企業が保持し続け、消費者はその使用料を支払うという形態である。データ関連のテクノロジーとトラッキングテクノロジーが進歩して、質の高い情報を入手しやすくなったことにより、このビジネスモデルの採用が昔より容易になっている。
たとえば、スーパーサークルという会社は、ファッション産業で循環型経済を実現するためのデジタルインフラを開発した。顧客の購買データと、倉庫・流通システムを統合し、衣料品のライフサイクルを追跡することを可能にした。この会社の共同創業者である起業家のクロエ・ソンガーによれば、同社はリフォーメーションのような人気アパレルブランドとパートナーになって、新しい顧客体験を生み出したという。顧客が衣料品を返却すると、返金や割引を受けられるようにしたのだ。さらに、そうやって回収した衣料品を集めて、リサイクリング企業に販売するための物流インフラの構築にも取り組んだという。消費者を長寿命製品の一時的な所有者と位置づけることにより、顧客を取り込むための幅広い可能性が開けてくるのである。
資源の効率を高める
2つ目の方法は、より少ない資源で製品をつくるというものだ。これは、多くの企業にとって目新しい考え方ではない。生産プロセスで生じる廃棄物を最小限に抑えることを特徴とする「リーン・オペレーティング・モデル」を追求してきた企業も少なくないだろう。しかし、近年、AIやその他の革新的なテクノロジーが飛躍的に進歩するのに伴い、この領域でも新たな可能性が生まれつつある。
たとえば、前述の「D3研究所」のイベントでは、起業家のシェリー・シューが設立したSXDゼロ・ウェイストがAIを活用して、衣料品のダミーをデザインし直した事例が紹介された。その新しいデザインでは、衣料品が消費者に届く前の製造工程で無駄になる生地を減らすことを目指した。これにより、セーター、ワンピース、ズボンの製造工程で生地の無駄がほぼゼロになり、コストも約55%減らすことができた。これまでのデザインでは、10~30%程度の無駄が生じるのが一般的だった。
起業によるソリューションが実を結ぶためには、ファッション産業の事例のようにそれがコスト削減につながる可能性があること、そして無駄の多い旧来型のプロセスを見直す必要があることを法人顧客に理解させなくてはならない。そのために時間を費やす必要があるのだ。
最先端のサイエンス、エンジニアリング、テクノロジーを活用する「タフ・テック」の領域でも、サプライチェーンが資源に及ぼす影響を和らげるために、既存のサプライチェーンで採用できる「単発」のソリューションを生み出せる可能性がある。
その例としては、GALYという会社の創業者であるルシアーノ・ブエノの取り組みを挙げることができる。GALYでは、旧来型の農業よりも80%少ないリソースしか用いずに、ラボで細胞から綿をつくっている。こうしたタフ・テックの領域でのイノベーションにおいては、イノベーションを成し遂げるまでに長い時間がかかり、成果を拡大させるために繰り返し試みる必要があることを投資家に啓蒙しなくてはならない。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)