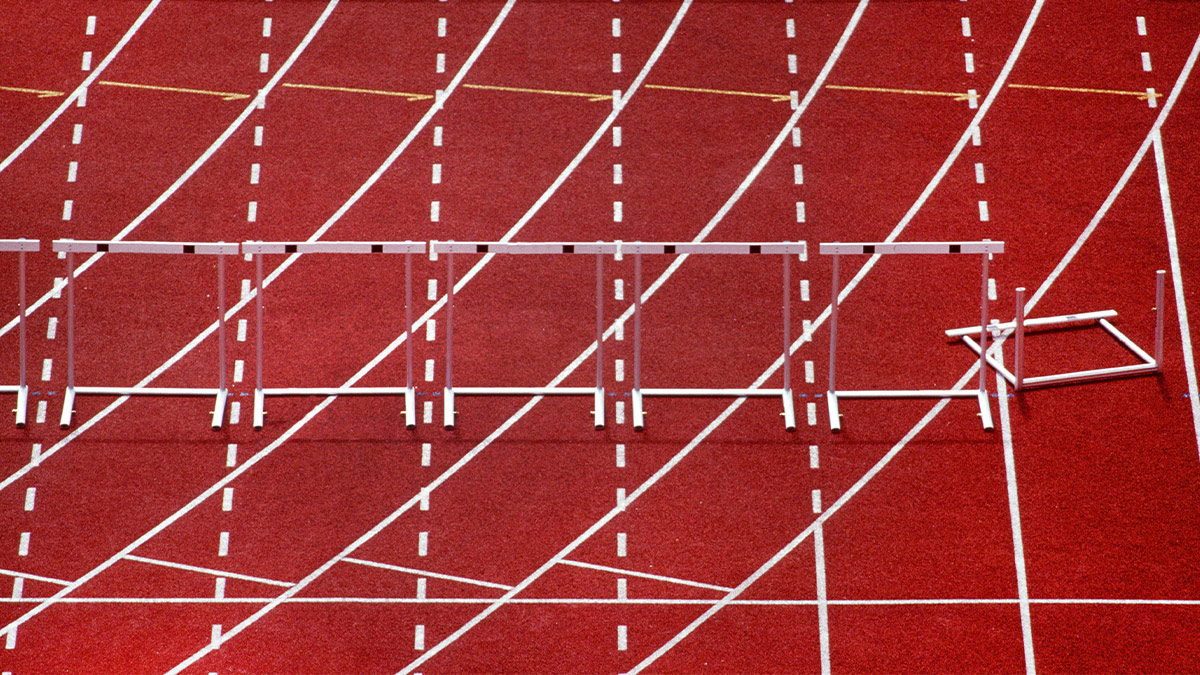
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
メンバーが不安な時、リーダーは何をすべきか
チームのメンバーが会社の未来に不安を抱いている時、リーダーがチームのモチベーションとエンゲージメントを保つことは容易でない。リーダーは、メンバーを安心させ、力になりたいと思う半面、メンバーに責任を持たせ、会社が前に進むために各自に求められる役割を果たしてもらいたいと考えている。
では、誰もが雇用の安定に対してストレスを感じている状況で、リーダーはどうすればチームの生産性を維持できるのか。昇給や昇進を行うという選択肢が存在しない時に、どのような職業上の成長の機会をメンバーに提供できるのか。そして、今日のように不確実性が高い時期に、どうすればメンバーが燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥ることを防げるのか。
専門家はどう考えているのか
昨今、働くことはますます過酷なものになっている。人員削減や新規採用の凍結を発表したり、予算を削減したり、プロジェクトを一時停止したり、リモート勤務の継続を認めるか、オフィスへの出勤再開を義務づけるかを決めかねたりしている企業もある。
このような状況で、従業員はストレスを感じており、マネジャーは「板挟みになったように感じている」と、『会社でやる気を出してはいけない』の著者で、リーダーシップ研修会社モジョ・モーメンツのCEOであるスーザン・ファウラーは指摘する。「(マネジャーたちは)結果を出し、生産性を高めなくてはならないという重圧を感じている半面で、メンバーのモチベーションを高めるために必要なものを提供できるだけの権力や権限を持っていないと感じている場合もあります」
上層部の期待に対処しつつ、チームのメンバーに対して正当な行動を取ることこそ、最も優先すべき課題だと、Both/And Thinking(未訳)の著者で、デラウェア大学アルフレッド・ラーナー・カレッジ・オブ・ビジネス&エコノミクスの教授でもあるウェンディ・スミスは言う。「メンバーのキャリアと私生活の両面で、理にかなった形でマネジメントとサポートを行わなくてはなりません」
不安と不確実性をすべて取り除こうとすることは現実的でないが、メンバーを後押しし、エンゲージメントを抱かせるような環境をつくることは可能だと主張するのは、パデュー大学ミッチェル E. ダニエルズ・ジュニア・スクール・オブ・ビジネス教授のエレン・コセックだ。「雇用の安定は保証できなくても、チームのコラボレーションを強化し、職場をより楽しく、出勤したくなる場にすることはできます」。本稿では、そのための具体的な方法を紹介しよう。
自分を大切にする
「マネジャーも従業員であることに変わりはありません。仕事のストレスが強まっている時には、マネジャーであるあなたも当然、ストレスを感じています」と、コセックは言う。しかし、緊張を強いられる日々が続いているからといって、ストレスに完全に押し潰されてはならない。キャリアの安定について心配したり、自分の職が時代遅れになるのではないかと気にかけるのは、当たり前のことだが、それが原因でマネジャーがチームに悪影響を及ぼすことはあってはならない。
「緊張を強いられる状況であなたが自分を大切にしていなければ、その悪影響は部下にも波及します」と、コセックは言う。そこで、ストレスに対処するためのメカニズムと手堅いサポートシステムを持っておくことが不可欠だと、スミスは指摘する。「コーチやセラピスト、メンターの力を借りて、自分が感じている不安を徹底的に検討しましょう」。自分自身を思いやり、気遣うことを通じて「マネジャーとして、より目の前のことに集中し、自信を持ってみずからの役割に『没頭』できるようになります」と彼女は語る。
難しいことを率先して話題にする
やっかいな問題に触れないでおくほうが楽に思えるかもしれないが、研究によると、チームが直面している不確実性と不安から目を背ければ、むしろ問題を悪化させる可能性がある。
スミスは、リーダーがチームのメンバーにそうした問題を率直に話すよう促し、リーダー自身がその手本を示すことを勧めている。「リーダーが『私はいま不安と恐怖を感じています。あなたも同じように感じているのではないでしょうか』と言えれば、メンバーへの深い共感を示す行動として受け取られます」
難しい話題について率直に話し合うことは、互いの間に信頼関係を育む効果があるかもしれない。しかし、そのような会話が不平不満の吐き出し大会になることは避けたほうがよい。成長と発達の恩恵に光を当てて、メンバーに希望を持たせるようにすべきだ。
「みんなが不安を抱いていることを認めつつ、そうした感情にじゃまされないようにすべきです」と、スミスは言う。「成長するのは簡単なことではありません。でも、それは好ましい経験なのです。みんなで苦しい経験を一緒に乗り切ることに価値があります」
現実的でありつつも、前向きなトーンを打ち出すべきだと、コセックは言う。「たとえば、このように言えばよいでしょう。『いまはレジリエンスを発揮すべき時期です。私たちが厳しい状況に適応する能力を持っていることを実証しましょう』」






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









