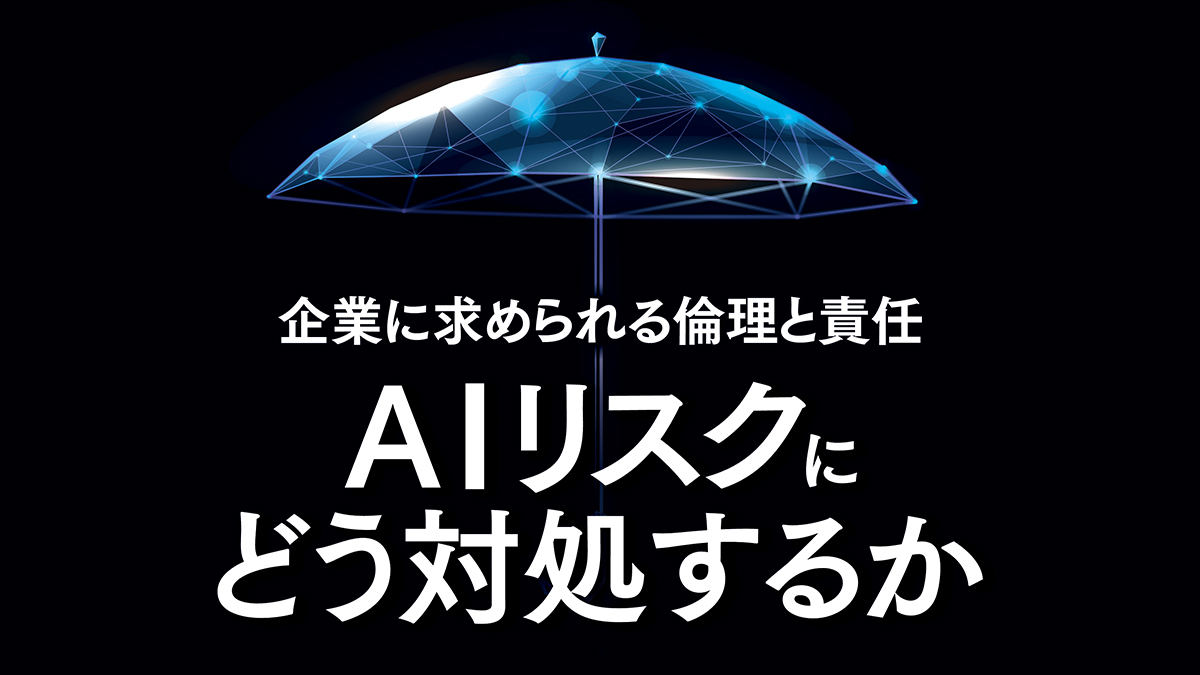
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
AI活用 vs AI倫理
「AI活用」と「AI倫理」という言葉が並んだら、「活用」に目が向くのではないでしょうか。「倫理」というと敬遠されがちですが、AI(人工知能)の活用を真剣に考えているビジネスリーダーほど、AI倫理は無視のできないテーマです。
いま、プライバシー侵害、虚偽情報の拡散、児童に対する不適切なコンテンツ提供など、AIがもたらす負の側面に注目が集まっています。その対応を怠った企業は、社会的信用の失墜や損害賠償金の支払いなど、その責任に応じた高い代償を払わなければなりません。
そこで、特集「AIリスクにどう対処するか」では、AIの倫理的リスクと対処法、そして企業の責任について考察します。
特集1本目「テクノロジーの進歩がもたらす『倫理的悪夢』を回避せよ」は、10年にわたり倫理の研究を行ってきた筆者が、企業にとっての最悪シナリオである「倫理的悪夢」について述べます。AIや量子コンピューティングなどの新興テクノロジーにおいて、そのブラックボックス化を防ぐことがビジネスリーダーの責務であると強調します。
特集2本目は『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)読者からの8つの質問に答える「責任ある企業としてAIをどう活用すべきか」です。AI導入における準備の方法やその意思決定の透明性をいかに確保するかなど、企業がAIの倫理的リスクを回避するための具体的な方策を探ります。
特集3本目は、「テック業界が大切にすべき価値観は何か」です。世界中でAI開発競争が進む中、テクノロジー業界のリーダーはどのような価値観で意思決定をしているのでしょうか。また、それが倫理的な枠組みにどのような影響を与えているのでしょうか。6人の専門家に尋ねました。
特集4本目は「人にまつわるデータを倫理的に取り扱う方法」です。データの取り扱いにおいて非倫理的な行為が発覚すれば、企業は大きな損害を被ります。人にまつわるデータの課題に焦点を当て、解決策について具体的に論じます。
特集5本目は「人間とAIの相互理解が、社会に創造性と安全性をもたらす」です。ゲームAI開発者の三宅陽一郎氏は、デジタルコンテンツ制作現場における生成AIの可能性と課題を明らかにし、その根本的な解決策として、人とAIが互いの行動に影響を及ぼし合う「世界」をつくる意義を述べます。統一した世界観があることで、AIを制御するAIが誕生し、倫理的な課題を克服できるのです。
企業の倫理的な責任について社会の追及が厳しくなる中、AI活用を考えるリーダーこそ見過ごしてはならない特集号です。ぜひご一読ください。
なお、今号のテーマについて語る無料イベントも開催いたします。ご興味のある方は気軽にご参加ください。
(編集長 小島健志)





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









