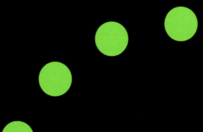-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「E負債」を用いて炭素排出量を追跡する
炭素排出量を削減する責任は、基本的に化石燃料を抽出し、精製し、販売する企業にあると、多くの活動家が見なしている。一部のカーボン・ディスクロージャー基準は、プロダクト(市場で提供される商品やサービス)の消費によって発生する川下のすべての排出量の推定値(顧客、顧客の顧客、そのまた顧客から発生するもの)を企業が年次報告書で発表することを求めており、実質的にこの世界観を謳っている。
ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)のロバート S. キャプランと筆者が「気候変動の会計学 Ⅲ:『消費者による排出量』開示の3原則」(DHBR2024年12月号)で論じたように、このアプローチには問題がある。特に、川下に関する報告要件は、同じ排出量を複数回カウントすることを求めているに等しい。さらに、川下の消費を推定することは非常に困難なので、企業は旧来からある、業界や地域の平均消費量推定値に依拠して報告を作成することが多い。つまり、排出量の面で自社が競合他社よりも劣っているのか優れているのかがわかっていないのだ。
さらにもう一つの欠点がある。化石燃料の生産者を重視するあまり、広範囲の企業経済の排出量削減の責任を見逃してしまうことだ。たとえば、プロフェッショナルサービス企業が業務の脱炭素化の可能性を綿密に検討するインセンティブは、相対的に小さい。たしかに、多くの企業はグリーンイニシアティブ(環境保護の取り組み)を謳うが、その取り組みのインパクトを厳密に測定することができない。
だが、さらによい方法がある。
キャプランと筆者はもう一つの論文(「気候変動の会計学」DHBR2022年4月号)で、「E負債」という堅牢な会計の枠組みを紹介した。それはサプライチェーンにおける企業の炭素排出量を追跡するもので、企業が以前から業務のフロー(主な収益とコスト)とストック(資産と負債の価値)の追跡で用いる手法に多くの点で似ている。このシステムでは、企業は原材料を購入する際にサプライヤーから体化排出量を取得し、価値創出で直接的に発生した排出量を加算する。そして、成果物を販売する際にこれらの合計排出量を顧客へと移転する。このシステムは、企業が直接的な排出量とサプライヤーから取得する排出量の両方を削減する方法を見つけ出すインセンティブを与え、炭素の体化排出量がより少ない成果物を顧客に提供できるようにする。またこのアプローチは重複集計を回避し、企業が脱炭素化を競い合うように背中を押す。
E負債は本来、セメント、鉄鋼、鉱業、自動車部門の大企業など、以前から炭素排出量の容疑者と見なされてきた企業に適している。特に欧米で営業している場合、顧客は排出量の少ないプロダクトを積極的に購入すると思われ、政府はグリーンな製造に気前よく助成金を提供し、環境問題に対する地域住民の関心は高い。しかしE負債は、世界の辺境で活動するある小規模なプロフェッショナルサービス企業にも有効であることが明らかになった。この企業の経験は、競合他社との差別化の根拠として業務の脱炭素化を検討している、他のサービス部門の中小企業(SME)にロードマップを提供できるだろう。
いつもの「容疑者」ではない
2022年末のクリスマス休暇中、専門的セキュリティサービス企業、IDGの設立者兼会長のイアン・ゴードンは、カーボンオフセットとして購入を検討している大規模森林プロジェクトの確実性を調査していた。だが、満足のいく確証が得られなかった。ゴードンは、実際にどれだけの炭素が隔離されるのか確実にわからないのに、なぜカーボンオフセットに金を出す企業があるのかと首を傾げた。そして、さらに詳しく調べるうちに、偶然、E負債アプローチを知った。興味をそそられたゴードンは、主にアフガニスタンのような危険な地域で活動する彼の会社がE負債のパイロットプロジェクトを実施するとしたら何が必要かと、筆者に問い合わせてきた。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)