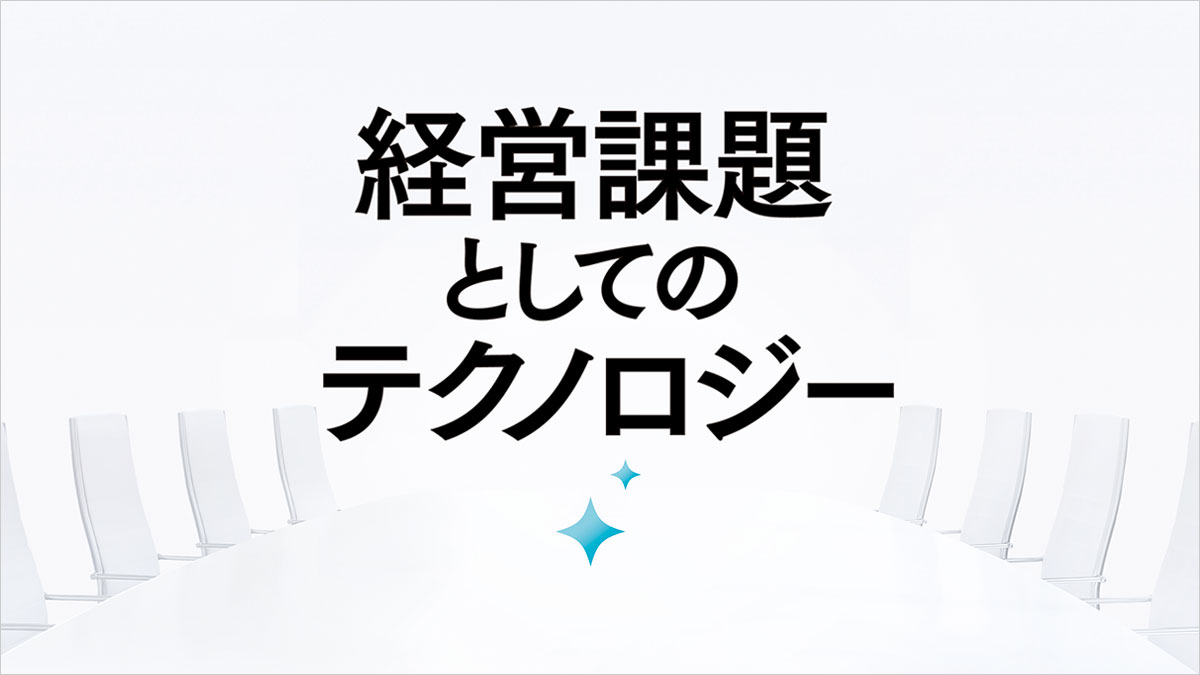
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
テクノロジーの進歩で変わる経営のあり方
今日普及している「マネジメント」という概念が生まれたのは1900年前後といわれていますが、以来、経営のあり方はテクノロジーの進歩が特徴づける時代の変遷とともに大きく形を変えてきました。
1910年代頃からオフィスに電話が普及し始めると、ビジネスにおけるコミュニケーションは格段に迅速になりました。1960年代にはメインフレームコンピュータの導入が進み、企業内における情報管理の効率化が実現。1990年代にはインターネットが普及し、電子メールとウェブサイトがビジネスの中心となりました。2010年代はソーシャルメディアの影響が増し、マーケティングや顧客対応においてもSNSが重要な役割を果たすようになりました。
そしていま、2020年代。生成AIと自動化の加速により、業務プロセスの最適化が企業の競争力を左右するようになってきました。そう、IT業界は言うに及ばず非テクノロジー企業にとっても、この流れに「乗らない」という選択肢はないのです。今号の「経営課題としてのテクノロジー」という特集タイトルには、編集部のそのような思いを込めました。
特集1本目は、2013年に発表した共著論文「雇用の未来」で、米国における雇用の47%が自動化されうると予測して世界的な議論を巻き起こしたオックスフォード大学マイケル・オズボーン教授へのインタビューです。あれから10年以上が経過したいま、機械学習を専門とするオズボーン教授は何を危惧し、これからの社会のあるべき形をどう捉えているのでしょうか。
続く2本目「企業が新たな技術に向き合う時、取締役会が果たすべき役割」では、非テクノロジー企業が新たなテクノロジーの出現に効果的に対処する方法として、テクノロジー委員会の設置を提唱しています。
「リーダーがAI導入プロジェクトを成功させるために必要なこと」と題する3本目は、業務へのAI導入を進めるにあたり、いかに従業員全員を巻き込むことが重要であるかを説いています。
そして4本目「生成AIとの協働を実現する3つのスキル」では、AIと人間が協働する新たな時代を勝ち抜くために「融合力」というコンセプトを提示しています。
これらの特集論考を読むほどに、業界を問わずすべての企業が対処すべきイシューが浮かび上がってくるはずです。ぜひ今号のDHBRを端緒に、あなたの組織でも議論を深めてください。
(編集長 常盤亜由子)





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









