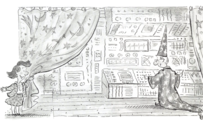-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
見過ごされやすい「曖昧な脅威」
組織に対する脅威には、2つの異なる形態が存在する。明確な脅威と、曖昧な脅威だ。明確な脅威とは、明白であり、かつ差し迫っているものである。たとえば、化学工場で警報システムが危険なガス漏れを検知した場合、問題は明確であり、対応策の特定も容易である。すなわち、施設を避難させ、ガス漏れを封じることである。
しかし、曖昧な脅威は認識するのも対処するのも難しい。たとえば、同じ工場で作業員が特定の場所で断続的にかすかな臭いに気づいた場合、軽微なガス漏れを疑う者もいれば、通常の操業による残留ガスと考える者もいる。センサーは異常を検知せず、検査でも目に見える問題は確認されない。差し迫った危険はないように見えるが、時間の経過とともに、軽い症状や不快感を訴える従業員が増えていく。兆候は入り混じっており、最善の対応方針は明確でない。
明確な脅威は迅速な行動につながることが多いが、曖昧な脅威は見過ごされる傾向がある。だからこそ、人々が曖昧な脅威の不確かな警告のサインをどのように捉え、なぜ行動をためらうのか、そして、始めは明白ではないが重大な被害をもたらすおそれのあるこの種の脅威への備えを怠らないために、組織ができることは何かを理解することが重要だ。
「曖昧な脅威」への対処が難しい理由
筆者らの調査で、曖昧な脅威には3つの特徴があることがわかった。第1に、曖昧な脅威は複雑で、原因が不明確または多面的であるため、判断が困難である。従業員は、それが真の問題なのか、それとも一時的な異常なのか、特定するのに苦労するかもしれない。第2に、それらは予測不可能であり、結果が不確実なため、緊急性を判断することが難しい。最後に、それらは前例がないことが多く、従業員が対応の指針とすべき過去の事例を持たない。
これらの結果が示唆するのは、脅威には明確さの程度に幅があり、真に明確な脅威は稀であるということだ。ほとんどの脅威は、何らかの曖昧さを含んでいる。このことは、曖昧さが異なる脅威に対して、個人やチームはどのように対応すべきか、という重要な問題を提起している。この問いに答えるため、筆者らはさまざまな業界の従業員と管理職102人に、異なる脅威をどのように認識し、対応するかを尋ねた。
脅威が明確な場合、誤った解釈をする余地はほとんどない、と回答者は答えた。従業員は危険を認識し、準備について率直に話し合い、素早く解決策をブレインストーミングした。たとえば、ある化学エンジニアリング会社の従業員は、職場で安全性に関する事故が増加したことを振り返った。そのサインは明確で、原因が保護装置の不適切な使用にあったことも明白だった。そのため、安全プロトコルの再設計やコンプライアンスの強化といった解決策を容易に特定することができた。
対照的に、曖昧な脅威は、問題が存在するのかどうかに関してしばしば意見の相違を生む。あるエレクトロニクス企業の従業員は、サブコンポーネントの機能不全という初期兆候が、その複雑さゆえに当初は無視されたと話した。最初の不具合は単発的なものと思われたため、チームはそれが大きな傾向の予兆ではないと考えた。また、前例のない問題だったため過去の類似事例を参照することができず、その深刻度や適切な対応を判断するのに苦労した。その結果、問題が重大な危機に発展するまで対処できず、最終的に重要な顧客を失ってしまった。
しかし、なぜ彼らは少なくともその問題に注意を促すことすらしなかったのか。
従業員の沈黙という問題
曖昧な脅威がもたらす課題に対処するためには、従業員は問題の兆候が現れた時点で、いち早く声を上げる必要がある。しかし、脅威が曖昧であるほど、従業員は沈黙する可能性が高くなる。石油とガスに関するコンサルティング会社の従業員と管理職436人を対象に実施した調査では、掘削、海底処理、圧力制御といった作業のリスクの高さから、従業員は技術的な危険を示す曖昧なサインに頻繁に遭遇していた。こうしたサインの曖昧さが増すにつれ、従業員は声を上げなくなることが繰り返し確認された。
そこで、さまざまな業界の従業員1193人を対象とした一連の心理学的実験を実施した。ある実験では、参加者は化粧品の新製品のR&Dチームのメンバーとして、現実的なシミュレーションに参加した。筆者らはベータテストの段階で曖昧な脅威を導入した。顧客は、わずかな肌荒れのような軽度かつ不明瞭な症状を訴えたが、それは良性の可能性もあれば、深刻な健康リスクを示している可能性もあった。このような曖昧な状況では、従業員はリーダーに従う傾向が強いことがわかった。自分で問題を分析したり懸念を表明したりするのではなく、上司が状況に対処することを期待していた。
なぜこのようなことが起こるのか。有力な要因の一つは、「認知的過負荷」である。従業員は複数の責任を担っており、曖昧な脅威を評価するには多大な精神的労力を必要とする。その結果、従業員はより管理しやすい仕事に集中するようになる。さらに、伝統的な職場の構造において、意思決定はリーダーの責任であるという前提を強調し、従業員は疑問を呈する以上に実行することを期待されている。こうして、脅威を理解するためにリーダーに依存することで、従業員はみずから曖昧さに対処する負担を軽減している。
この依存が問題なのは、最も有能なリーダーであっても曖昧な脅威を見落としたり、チームの製品やプロセスの弱点を見誤ったりする可能性があるためである。一方、こうした製品やプロセスに日々接している従業員は、不確実な状況を乗り切るのに役立つ重要な洞察を持っている可能性がある。皮肉なことに、従業員のエンゲージメントが最も必要とされる状況において、彼らは関与を控えがちになり、組織が危機的な局面で脆弱になることを、筆者らの調査結果は示している。
企業が従業員に警戒を促す方法
曖昧な脅威は明確な警告サインなしに出現し、従業員はその対処をリーダーシップに依存する中で、企業は、従業員が常に警戒を怠らず関与し続けるよう、どのように促すことができるだろうか。筆者らが勧めるのは、組織、リーダー、従業員の3つのレベルにおいて、的を絞った行動を取ることである。
組織:警戒する文化をつくる
企業は、「失敗にこだわる」文化を構築することで、曖昧な脅威という課題にうまく対処することができる。これは、小さなミスであっても積極的に分析するマインドセットを育てるものである。筆者らが行ったインタビューでは、従業員はこの考え方の重要性を強調し、さらに時間をかけてリスクを徹底的に評価すべきだったと指摘している。
このアプローチのリーダーが、トヨタである。同社の「アンドン」は、作業員が自分の持ち場で問題を発見した時に紐を引いたりボタンを押したりすると、視覚的な警告表示板が作動するシステムであり、従業員は問題の兆候があればすぐに生産を停止することができる。トヨタはこれを、業務の妨げではなく責任として捉え、早期の警告が重視される文化を強化している。従業員に対し、ニアミス(ヒヤリハット)を分析し、安定した状況でも警戒を怠らず、声を上げることを奨励することで、組織はリスクが拡大する前にそれを把握することができる。
リーダー:脅威を入念に調べるよう従業員を訓練する
リーダーは、不確実な状況に備え、脅威を認識して対応するために必要なスキルを従業員に提供するうえで、重要な役割を果たす。インタビューの回答者らは、構造化テスト(シミュレーション、ストレステスト、管理された訓練など、現行システムの脆弱性と準備態勢を評価するもの)が、組織の障害を防ぐのに役立ったと強調した。
ネットフリックスは、「カオスエンジニアリング」によってこのコンセプトをさらに推し進め、意図的にシステム障害を起こしてレジリエンスをテストしている。そのためのツール「シミアン・アーミー」の中でも特に「カオスモンキー」は、ランダムにシステムを混乱させ、脆弱性を検出し、適切な対応策を議論するように従業員を訓練するものである。こうしたトレーニングを制度化することで、企業は従業員にリアルタイムの脅威検知スキルを身につけさせることができる。
従業員:重要な時はリーダーシップに異議を唱える
従業員自身も、必要に応じてリーダーに対して異議を唱えることで、曖昧な脅威に対処する役割を果たす。インタビュー回答者の何人かは、問題を疑った時に上司に反論しなかったことを後悔し、さらなる調査を主張すべきだったと述べている。
エヌビディアは、「知的な誠実さ」、つまり、ためらわずに物事をありのままに言う能力を強調することで、従業員にこの考え方を奨励している。従業員は、反発を恐れずに発言し、決定に異議を唱え、変更を提案することが期待されている。このアプローチにより、エヌビディアはイノベーションの最前線に立ち続け、プロジェクトが軌道に乗らない時は、従業員の洞察に基づいて素早く方針転換をしている。
* * *
不確実な環境で成果を挙げる組織は、状況が明確になるのを待つのではなく、トラブルのかすかな兆候さえも積極的に探知し、行動に移す。重要なのは、警戒心をリーダーのみでなく、あらゆる階層の従業員が共有することである。疑問を呈し、リスクを予測し、早期に行動する文化を構築することで、企業は曖昧な脅威を負債から競争優位へと転換することができる。混乱が避けられない世界においては、危機が発生してから対応するのではなく、積極的にリスクを特定する組織こそが先行し続けることができる。
"Why Employees Stay Silent When They See Warning Signs of a Problem," HBR.org, April 07, 2025.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)