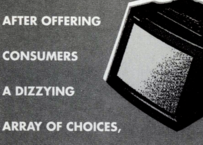-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
プロダクト思考は非プロダクト部門にも適用できる
最も基本的な定義によると、「プロダクト」とは、組織が価値を提供し、それを回収する手段である。日々、プロダクト開発に携わるチームにとっては、「プロダクト」や「顧客」という言葉の定義は比較的わかりやすいものだろう。ジェットエンジンであれ、保険契約であれ、オンラインバンキングアプリや携帯電話のサービスであれ、それを購入して使用する最終顧客がいる(時には購入者と使用者が異なる場合もある)。プロダクトチームは、その顧客のことを深く理解しようと努め、組織のプロダクトやサービスを継続的に改善することで、顧客の成功を支援しようとする。
これこそが、組織のアジリティ(敏捷性)の核心である。つまり、プロダクトを改善し、顧客の行動を観察・測定し、その改善を続けるべきか、それとも別の取り組みに進むべきかを判断するのだ。学習が早ければ早いほど、改善も早くなる。プロダクトチーム、特にデジタルプロダクトチームは、こうした原則を本質的に理解している。
だが、あなたがプロダクトに関わっていない部門に属していたら、どうだろうか。たとえば、人事部で教育や開発を担当しているとしたらどうか。あるいは、法務部門でサイバーセキュリティポリシーの策定を担っているとしたらどうか。それでもあなたは「プロダクト」をつくっているといえるのか。顧客はいるのだろうか。組織全体にアジリティをもたらすことに信念を持っているなら、この2つの問いに対する答えは、いずれも「イエス」である。
すると、次の問いが生じる。それは、どのようにして自分が価値を提供したとわかるのか、あるいはその価値を回収できたと判断できるのかというものだ。多くの場合、こうしたチームは「目標」や「施策」の達成によって成功を測ろうとする。たとえば、「新しい学習管理システムを導入できた。だから成功だ」「新しいサイバーセキュリティポリシーをベンダーに提供できた。よくやった」という形で。
しかし、それが本当にその方策や取り組みの最善策だったといえるのだろうか。
この問いに答えるには、あらゆるプロジェクトや施策、ポリシーに「プロダクト思考」を適用する必要があると私は考えている。そうすることで、プロダクトやテクノロジーとは直接関係のない部門──人事、財務、法務、ロジスティックスなど──も、「成果物重視の考え方」から脱却し、プロダクトチームに根づいている「アジャイルで顧客中心の視点」に近づけるのだ。
人事部門にプロダクト思考を取り入れるとどうなるか
次のような例がある。人事部門のビジネスパートナーが、全社向けの新しい学習管理システム(LMS)とトレーニングカリキュラムの設計、評価、調達、導入を任されたとしよう。彼らはこの任務に真面目に取り組み、入札を募り、プレゼンテーションを受け、最終的にはLMSを構築・統合・導入するベンダーを選定する。「おめでとう」と言いたいところだが、そう簡単にはいかない。誰もその新システムを使わなかったらどうするのか。従業員が必須の講座しか受けず、人事担当者が何週間もかけて調達・評価した追加の講座には見向きもしなかったら、どうだろうか。そもそもLMSの使い勝手が悪く、苦情のメールが人事チームに殺到し、通常の3倍に増えたらどうするのか。
ここで登場するのが「プロダクト思考」である。組織全体でビジネスアジリティを実現したいのであれば、プロダクトに直接関わらない部門の仕事も「プロダクト」と「顧客」という言語で捉え直す必要がある。まずは、その取り組みを「チェックリストをこなす仕事」としてではなく、「特定の顧客に対して解決すべき課題」として再定義することから始める。その課題の「成功指標」は、プロダクトの導入ではなく、顧客の行動における明確で測定可能な前向きな変化である。つまり、私たちが目指すのは「アウトプット」ではなく「アウトカム」(成果)である。
では、先ほどのLMSの例をこのように捉え直してみよう。人事チームに「調査して導入してください」と依頼するのではなく、人事部門のビジネスパートナーやリーダーは、次のように問題を提示すべきだ。
現在の人材育成施策は、従業員に認知されておらず、見つけにくく使いにくいシステム、そして現代のデジタル時代の労働力にとって無関係な内容のカリキュラムが原因で、ほとんど利用されていない。その結果、最も価値の高い社員の離職が増え、採用コストがかさみ、組織の士気も低下している。加えて、既存システムの無駄なコストも見過ごせない。どうすれば、従業員全体によりよい人材育成の機会を提供し、デジタルビジネスの最新トレンドを把握し、自身の成長に組織が真剣に投資していると感じてもらえるだろうか。成功の目安は、離職率が四半期ごとに10%改善し、育成コンテンツの利用が2倍に増加し、採用コストが15%削減されることである。
このように人事チームの仕事を再定義するに当たり、私たちはいくつかの重要な変更を行った。
1. まず、この取り組みの目的を「LMSの導入」から「社員の成功を支援する」へと再定義した。これは本質的に顧客中心主義のアプローチである。ここでいう顧客とは、企業の従業員のことである。
2. 次に、「この課題に対する解決策」という前提を一切取り除いた。これによってチームは、自分たちでアイデアを出し、それを評価し、「顧客」の成功に最もつながる方法を主体的に選べるようになる。その結果、彼らは自分たちのアイデアに強く関与するようになり、より広い視野から革新的な解決策を探すようになる。
3. 私たちは、明確な成功基準を設定した。それにより、チームはみずからの「顧客」を理解しようと積極的に関心を持ち、提供する「プロダクト」を継続的に改善することが求められるようになる。もはやLMSを導入しただけでは不十分だ。人事チームは、LMSが実際に使用されているかを確認し、その使用が離職率の改善や採用コストの削減など、組織が重視する指標にどれだけ貢献しているかを評価しなければならない。
意図した成果が得られないソリューション(あるいはプロダクト)を選んでしまうリスクを減らすために、チームはより反復的で探求的なアプローチを取る必要がある。チームは、「問題ステートメント」で掲げた目標をどうすれば最善の形で達成できるかについて、仮説を立てる必要がある。その仮説をテストし、顧客やユーザーからのフィードバックを得て、そのフィードバックをもとにアイデアを繰り返し改善していく。思い当たるところがあるだろうか。これはまさに、顧客対応を行うプロダクトチームが、常に最大限の価値を提供・回収するために実践している方法そのものである。
人事チームがみずからの取り組みにプロダクト思考を適用すれば、使いづらく中身の乏しいLMSを導入してしまう可能性は大幅に低くなる。実際のところ、最終的な成果物はLMSですらないかもしれない。たとえば、ある企業にとっては、戦略的かつ質の高い対面研修のほうが適しており、それがLMSの代替となるかもしれない。
もちろん、この考え方は人事部門に限ったものではない。たとえば、法務チームが契約書を作成しているとすれば、それが彼らにとっての「プロダクト」である。その契約書を使うベンダーが、法務チームにとっての「顧客」に当たる。もし契約書の内容が一部のベンダーにとって適していなければ、あなたのチームはテンプレートを何度もカスタマイズすることになり、時間もコストもよけいにかかってしまう。こうした赤入れの繰り返しを減らすには、法務チームは顧客のニーズを理解し、それぞれの顧客タイプに最も適した契約書を提供する必要がある。
こうした概念は、プロダクト以外の部門ではまだ一般的でないかもしれないし、組織としても、どこから始めればよいのかわからず戸惑うかもしれない。しかし、こうした変革には、他の大きな変化と同様に、リーダーシップの支援と理解が不可欠である。新しい働き方を実行に移せるよう、リーダーや現場のメンバーに対するトレーニングから始めるのがよい。一度彼らが「仕事をどう捉えるか」「解決策をどう探るか」、そして何より「顧客の課題を本当に解決しないアイデアは手放す」ことを理解すれば、その学びを他のメンバーに共有し、広げていくことができる。
今日、多くの組織でプロダクト思考が注目されているのは、それが「形式だけのアジャイルプロセス」ではなく、本質的なアジリティの考え方をプロダクトチームにもたらしているからだ。しかし、この考え方は、プロダクトやテクノロジーのチームに限定されるものではない。「組織のアジリティ」は、すべての部門にとって歓迎すべき変革なのである。
あなたのチームが担う仕事を「特定の顧客を持つプロダクト」として捉え、課題を与え、アウトプットではなく成果(アウトカム)で成功を測定するようにすれば、組織全体に「顧客中心」の文化が根づく。そして、誰かがあなたの製品を買うにせよ、あなたの会社で働くにせよ、あなたの会社と契約を結ぶにせよ、その人とあなた自身という双方の成功を常に最大化することが可能になるのだ。
"Bring Product Thinking to Non-Product Teams," HBR.org, April 7, 2020.







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)