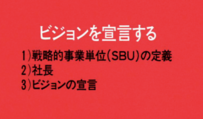-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
役に立たない助けが従業員を苦しめる
エイミーは、協働の強い文化で世界的に評価されているデザインコンサルティング会社「グロー・デザイン」(仮名)のシニアデザイナーだった。筆者らがエイミーと初めて会った時、彼女は同社の助け合いの精神を積極的に支持していた。しかし1年半後、彼女は涙を流していた。打ちのめされ、助けを得られず、退職を検討していた。いったい何が問題だったのか。
その答えは、役に立たない助け(help)である。
助け合いはグローの文化の根幹に織り込まれており、従業員ハンドブックには「グローの全価値観の根源」として明記されるほどであった。職場における助けについて詳細な研究を行うために筆者らが同社にアプローチしたのは、この文化ゆえである。筆者らはグローにおける助けの実態を長年研究し、具体的には、インタビューを69件実施し、チームメンバーが与え、受け取った助けに関する日報401件を分析した。そして、この強固な文化にもかかわらず、データからは予期せぬ事実が判明した。日報で報告された助けの要請の25%が、助けを受けた側から役に立たなかったと評価されていたのである。
すなわち、助けの4件に1件は、実際には役に立っていなかったことになる。
数十年にわたる研究で、職場での助けは価値があるものの、極めて稀であることが示されている。労働者は必要な助けを得られないことが多く、その理由はたいてい、彼らがそれを求めないためである。しかし近年、筆者らの研究を含むさまざまな研究が、マネジャーがマイクロマネジメントせずに助けを提供する方法を見出すことなど、助け合いの文化を創出する方法を明らかにしている。これにより助けははるかに一般的になった。
しかし、助けがより一般的になることにはリスクも伴う。協働で知られる組織でさえ、助けの相当な割合が役に立っていない。だからこそ、チームや組織で生産的な助け合いの文化を築きたいのであれば、役に立たない助けを理解する必要がある。
役に立たない助けとは何か
役に立たない助けとは、提供された助けが的を外してしまった場合に生じる。これは、助けがうまく実行されなかったり、約束されていた内容と違っていたり、あるいは単に受け手が必要としていなかったことが原因である。これらの失敗した試みは、通常、悪意によるものではない。実際、多くは善意に基づくものである。しかし、それでもエネルギーを消耗させ、仕事を遅らせ、信頼を損なう。









![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)