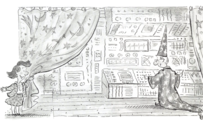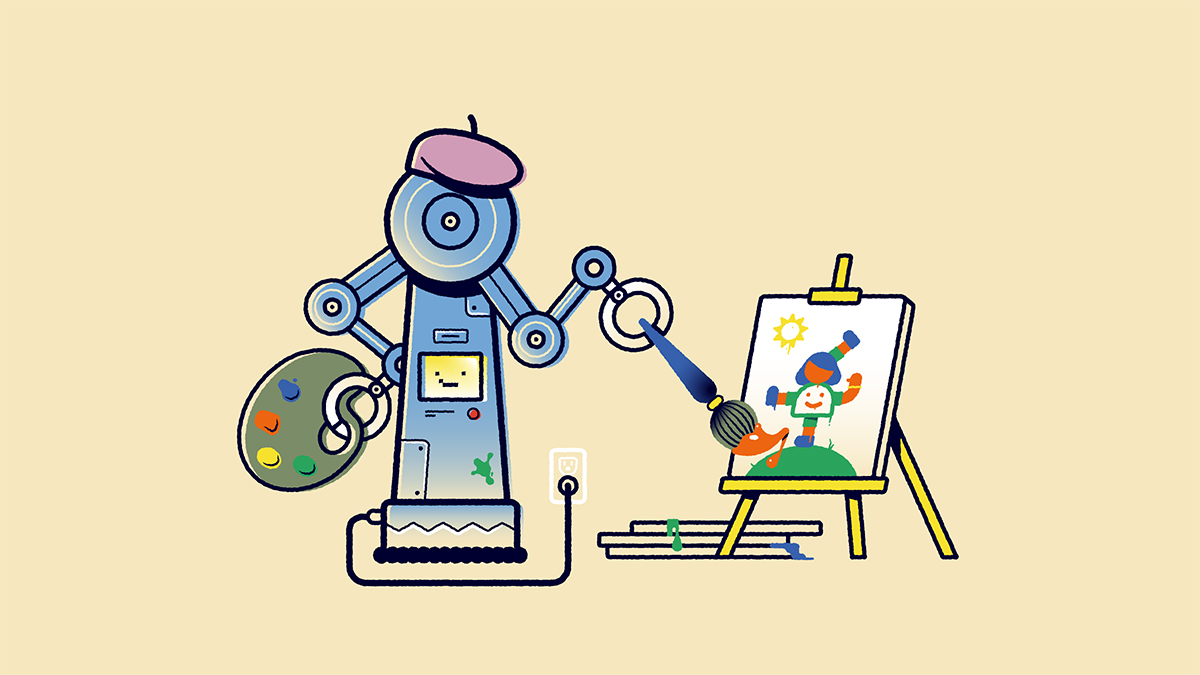
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
生成AIの活用によって人間が失っているもの
私たちの身の回りには、生成AIがもたらす多大な影響についてのメッセージがあふれている。ネット上には、組織が業務のスピードや規模を拡大し、プロセスを自動化・効率化するAI活用法の記事が絶え間なく飛び交っている。メールの受信箱やSNSのタイムラインも、「使えるAIツールトップ10」のリストであふれ、生成AIを使いこなせば仕事の効率性を高め、退屈な単純作業をなくせると謳っている。
一つ、はっきりさせておくべきことがある。生成AIは間違いなく、より多くのアウトプットを、より迅速に、より少ない労力で生み出す助けとなるものである。その点を否定する人は、正直なところ、現実が見えていない。
一方で、私たちはAIによって生み出されるアウトプットの価値に注目するあまり、それ以外の価値の源泉、たとえば、何かを学んだり、人間関係を構築したりすることの価値に目を向けなくなっている。自分たちの一つひとつの行動が、どのような形で真の価値、唯一無二の価値を生んでいるのかと自問することはまずない。
リーダーはいまこそ、冷静かつ厳しい目で組織を見つめ直し、この問いを投げかけるべきだ。そうしなければ、生成AIの導入によって生じた価値以上に多くの価値を失ってしまうことになりかねない。
価値はどこから生まれるのか
自分が、モーツァルトが交響曲を作曲したと伝えられている時のように原稿を書くことができたら──つまり、完璧にまとまった思考が、何の修正も必要ない形で、そのまま紙の上にあふれ出てくるとしたら──どんなによいだろうか。そのようなことを願うが、実際にはそうはいかない。
筆者が本稿を書くに当たっても、書き出しの部分を幾度となく修正し、つじつまの合わないアウトラインをいくつもつくった。いらいらして何度もPCから離れたり、完成原稿の10倍もの下書きを書いたりもした。好奇心に駆られて、筆者は生成AIにいくつかプロンプトを入れて原稿を作成させてみたところ、わずか10秒でそれなりに一貫性のある文章が出力された。
つまり、生成AIが組織や個人に莫大な価値をもたらす可能性を秘めているという点は疑いようがない。
複雑な業務や単調な作業を自動化することで、業務の効率性を高め、より高い価値を生む活動にリソースを回すことが可能になる。AIの計算能力を活用すれば、データ分析によって意思決定の質を向上させたり、アイデアの具現化や試行、改良を通してイノベーションのプロセスを加速させたりもできる──それも、人間ではとうてい実現できない規模とスピードで。ブレインストーミングの補助ツールとして使えば、AIは無限に近い分量のアイデアを提供し、人間の創造プロセスを支えてくれる。
リーダーは、こうした利点が業務の質や効率を向上させていることを念頭に置き、常に意識しておくべきだ。
だが一方で、生成AIに業務を委ねることに伴う代償はないのだろうか。言い換えれば、価値はほかにどこから生まれるのだろうか。検討すべき5つの重要な領域を紹介する。
知識や洞察の獲得
仕事に取り組んでいるうちに、目の前のタスクを超えた知識や理解が身についたというケースは少なくない。たとえば、外国語の適切な単語を探して四苦八苦しているうちに、その表現が記憶に定着して、後で思い出しやすくなる。あるいは、せっかく編み出した技術的課題への解決策が却下されてしまっても、それが他の課題の解決に役立ったり、それ自体が思いがけない新発見につながったりするケースもある(ペニシリンやコカ・コーラ、煙探知器はそうしたプロセスで誕生した)。さらに、情報を要約したり、統合したりするプロセスを通して、概念的なつながりに気づくこともある。
たしかに、翻訳や課題解決、文書の要約を生成AIに任せれば、より速く、場合によってはより正確に、しかも、より少ない労力で成果を得ることができる。しかし、そうすることで、本来なら得られたはずの学びが失われてしまう。儒家の思想家・荀子による「聞いたことは忘れる、見たことは覚える、やったことはわかる」という教えを思い出すべきだろう。
スキルの向上
上記と密接に関連する話として、「習うより慣れろ」ということわざがある。人は、実際に経験することでスキルを磨いていく。報告書の下書きを作って推敲を重ねることで編集スキルは向上し、コードのバグを探すことでプログラミングの腕は磨かれ、執筆に行き詰まって悪態をつくことで書き手としての忍耐力が養われる。学びと同様に、文書の推敲、コードの下書きとバグ探し、複数のパラグラフ案の作成などを生成AIに委ねることで、短期的にはメリットを享受できるが、長期的には自身の能力を高められないというリスクを伴う。
社会的つながりの維持
伝統的に、大半の仕事は集団で行われており、特に困難な問題については知恵を持ち寄って解決策を見出してきた。生成AIによって計算能力が劇的に向上した結果、従来なら他者の力を必要としていた課題を個人がそれぞれ自力で解決できるようになったが、それは同時に、周囲の人との交流が減ることを意味する。
そうした交流は、相互理解や絆、共同体の意識、さらに最終的には信頼関係の基盤となるものであり、組織が成果を生み出す力に多大な影響を及ぼすという点を理解しておくことが重要だ。また、こうした行動の変化によって、人々が孤独を感じやすくなり、個人のウェルビーイングに悪影響が生じていることも研究で示唆されている。
アイデアへのエンゲージメント
エンゲージメントとは、何かの役割を担う際に、その役割に心から向き合っている状態と定義され、成果の質や効率性を向上させ、個人のウェルビーイングと満足度を高めるなど、幅広い利点がある。
とはいえ、どのような人も、自分が取り組むすべての物事に、常に100%の力で向き合っているわけではない。生成AIが力を発揮するのも、そうした場面だ。
たとえば要約は生成AIの得意分野で、大量のデータからテーマを抽出する作業を人間よりはるかに速く処理できる。長大な報告書であれ、議事録であれ、その要約を生成AIに委ねると、人は精神的に一歩引いた状態になり、エンゲージメントの度合いが低下しがちだ。
人間が行う要約は能動的なプロセスであり、単にデータを取り出すのではなく、構成を組み立て、解釈し、アイデアをさらに発展させる。そうしたプロセスを通して、文書とのつながりが強まり、エンゲージメントを高められるのである。
AIの成果物を「後で見直して、コメントをつけたり、議論を広げたりするから大丈夫」と言うのは簡単だが、「本当にそうしているか」と自問すべきである。誰しも皆、多忙だから、「まあ、これで十分だろう」と言って、足りない点に気づくほど深く関わらずに済ませてしまってもおかしくない。
独自性の維持
経営関連の出版物や新聞のビジネス面を開けば、さまざまなタイプのリーダーシップスタイルについての記事を容易に見つけることができる。それには正当な理由がある。その場に応じたリーダーシップスタイルを取れるかどうかで、成果に大きな差が生まれる可能性があるからだ。
人は経験の積み重ねによって形作られており、携わった仕事を通してリーダーとしてのアイデンティティを固めていく。文書のトーンやメッセージの伝え方にも、プレゼンテーションのスタイルや問題解決の方法にも、他の人とは異なる、その人だけの特徴がある。生成AIを利用してメールやメモ、プレゼン資料を自動的に生成すれば、リーダーは時間を節約でき、より質の高い成果物を生み出せるかもしれないが、そうすることで、その人らしさを生み出してきた語り口や声が失われてしまう。
もう一歩踏み込むなら、大規模言語モデル(LLM)は本質的に「収束型テクノロジー」であるという点も忘れてはならない。生成AIに原稿の作成を依頼すると、学習データに含まれるすべての関連情報との整合性が最も高く、最も一致する内容が回答として提示される。つまり、同じLLMに同じような問いを投げかけたリーダーは皆、同じ前提に基づいて組み立てられた、同じような答えを与えられている(そうした回答が将来のモデルに学習データとして追加されることで、この仕組みが強化される可能性もある)。
生成AIの費用とメリットを天秤にかける
生産性や効率の向上といったメリットと、スキルの喪失やエンゲージメントの低下などのコストを天秤にかけるのは容易なことではない。リンゴとミカンではなく、リンゴとエンジンオイルを比較するようなものだからだ。しかも、コストとメリットの表れ方が一様ではないという点も話を複雑にしている。
筆者とハーバード・ビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授は、統合的な従業員価値提案の構築に関する調査を通して、組織の取り組みの効果を評価する際にリーダーが念頭に置くべき2つの重要な次元を特定した──レベル(個人か集団か)と時間軸(短期か長期か)である。
リーダーは、集団と個人の双方の成果に責任を負うべきだが、生成AIをどこで、どのように導入するかに関する決定は、その両方に影響を及ぼす。たとえば、あるプロジェクトでコード作成にAIを活用した場合、プロジェクトとしてのアウトプットは増大するだろうが、チームメンバーの個人レベルでの成長が犠牲になるかもしれない。
同様に、リーダーは、現時点でどのツールやプロセスが、部下やチーム、組織にとって有益かだけでなく、時間の経過とともに、それらがどう作用していくかまで考慮する必要がある。たとえば、会議の記録と要約を生成AIに任せれば、現時点では時間を節約できるかもしれないが、将来的にはエンゲージメントの低下につながりかねない。つまり、リーダーは現在の利益と将来のコストを天秤にかけるという、私たち人間がひどく苦手とする課題に取り組まなければならない。
AIの価値を監査する方法
生成AIはすっかり定着し、そのメリットは否定しようがないが、潜在的なトレードオフの存在を考えれば、リーダーは生成AIの利用について意識的に行動する必要がある。そのためには、ほかの重要な経営判断と同様、メリットとコストを客観的かつ総合的に評価することが求められる。リーダーが実施すべきAI価値監査のステップを以下に紹介する。
ステップ1:AIで対応できるタスクごとに、重視すべき価値の種類を見極める
まず、そのタスクがどのような価値を生み出しているのかを考えよう。量やスピード、品質、効率といった成果は目に見えやすいが、同時に、そのタスクが学習につながるか、社会的交流や人間関係を広げてくれるか、そして、その人ならではの表現を加えることがプラスに働くか、といった点も検討する必要がある。
上記の価値のリストは網羅的なものではないが、出発点としては十分だ。煩雑なプロセスである必要はなく、付箋のチェックリストのようなシンプルなものでもかまわない。重要なのは、さまざまな価値に思いをめぐらせ、目に見える成果以外の視点を持つことである。
ステップ2:特定した価値の種類に優先順位をつけて最適化する
すべてのタスクがすべての種類の価値を提供する必要はないし、すべてのプロジェクトがそれらの価値を等しく提供できるわけでもない。メリットが最も大きく、また最も必要とされる分野に集中しよう。たとえば、生成AIを使って議事録を要約すれば効率は高まるかもしれないが、つながりやエンゲージメントは低下する可能性がある。重要性の低い会議に限って要約をAIに任せたり、議事録作成をAIと人間で交互に行ったりする方法を検討しよう。
また、各タスクがより広いエコシステムや社会的ネットワークの中でどのように機能しているかという点も考慮すべきだ。たとえば、ブレインストーミング会議の代わりにAIを導入する場合、社員同士の信頼関係を築くために別の機会を設けることを検討すべきである。
ステップ3:毎回確認する
生成AIの影響をすべて理解できているわけではない。さらに、組織も業界もチームもそれぞれ異なっており、AIを使用すべきか否かは状況によるところが大きいという点も認識すべきだ。
筆者が「ミルクテスト」と呼んでいる手法を試すことを推奨する。生成AIの利用に関するあらゆる決定には、「消費期限」を設定すべきである。
牛乳をチェックするように、データが届いても、それを自動的に破棄(または採用)するのでもなく、必ず「匂い」を嗅ぐように評価を行う。科学者になったつもりで、仮説を立て、検証し、データを集め、実証的な根拠に基づいた結論を出す。そうすれば、優先順位づけが適切でないと気づいたらすぐ調整できるため、状況に応じた判断を下せる可能性が高まる。
* * *
最後にもう一点。生成AIを使うか否かの判断はリーダーのみに委ねられているわけではない(リーダーが主体となって決めるものでさえないかもしれない)。AIツールは安価でアクセスしやすく、広く普及しているため、従業員はガイドラインがあろうとなかろうと、AIをいつ、どのように使うか各自で判断している。
「測定できるものしか実行されない」とよくいわれるが、もしも自社のKPI(重要業績評価指標)をはじめとする評価指標が成果とスピードばかりに焦点を当てているのなら、従業員はできるだけ多くの業務を生成AIに任せようとするものだ。それらの指標のみが重要であるのなら(そうした場面はもちろんあるが)、AI任せでまったく問題はない。しかし、そうでないのなら、自分が奨励したいものを見直し、協働や学習など、失われかねない行動を奨励するような評価方法を検討すべきである。
最後に、生成AIと、それによって生み出される価値、さらに、損なわれるリスクのある価値について部下と議論すべきだ。メリットとデメリットを正しく理解していれば、彼らが自身や組織の利益にならない判断を下すリスクを減らすことができる。
"Recalculating the Costs and Benefits of Gen AI," HBR.org, June 23, 2025.






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)