
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
変革リーダーが抱える多大な感情労働
「あとどれくらい耐えられるか自信がありません」──筆者との定例の面談でそう語ったアマンダの声は震えていた。筆者の顧客であるアマンダは、社内で複数年にわたるデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取り組みを牽引していた。社内の多くのチームを結集させ、難しい判断を下し、深く根づいているシステムを変更する過程でたえず持ち上がる反発を受け止めてきた。
アマンダは、変革のビジョンを強く信奉していた。そのビジョンを推進するために激しく戦い、それを擁護し続けてきた。
しかし、アマンダは筆者にこうも打ち明けた。「毎朝目が覚めた時は、手ごわい課題に挑もうという強い気持ちがあります。けれども、夜になると、私はみんなを引き連れて崖っぷちに導こうとしている愚か者なのではないか、という不安がこみ上げてくるのです」
アマンダの言葉は、ほとんど話題にされることのない現実を浮き彫りにしている。その現実とは、変革を主導するリーダーが少なからぬ代償を払わされるという点である。
筆者はこれまで、組織を悩ませる「変革疲れ」についてたびたび論じてきた。具体的には、変革の長期化とともに、働き手のエンゲージメントの低下、不注意によるミスの増加、生産性の悪化、士気の減退といったことが起きるのだ。
変革がしばしば失敗に終わるという厳しい現実は、よく指摘されている。「変革の取り組みの3件に2件程度は失敗する」という類いの主張もよく見かける。しかし、変革の成否にばかり目を奪われると、重要なことを見落とす。変革の舵取り役を務めるリーダーが担う感情労働の負担の重さと、その負担がリーダーに及ぼすダメージが見えなくなるのだ。
あなたが変革を推し進めようとするリーダーだとすれば、自分が常に「内面の葛藤」を抱えていて、「積極性」と「躊躇の感情」の間で引き裂かれるかのように感じているかもしれない。たとえば、アマンダは、積極性により、ビジョンの実現に向けて戦おうという意思を持つ。しかし、その一方で、ためらいの感情により、プロジェクトを失敗させる原因になりかねないリスクや現実に不安を感じやすくなる。
この2つの要素のぶつかり合いがあること自体は、問題ではない。このような緊張関係があるからこそ、私たちは大きな変革を導くことができる。
しかし、積極性と躊躇する感情の緊張関係にうまく対処できなければ、リーダーであるあなたが押しつぶされてしまう。変革の実現という成果を上げることができたとしても、疲弊し、孤立し、次に変革に挑戦する際には成果が上がりづらくなるかもしれない。

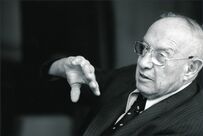




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









