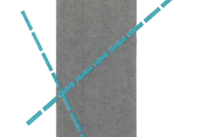-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
AIの個人利用を、組織的な導入へと移行させる方法
もしあなたの組織が、依然として従業員による生成AIでの場当たり的な実験に頼っているのであれば、いまこそ方針を変えるべきである。クロードを使ってメールの下書きを作成したり、チャットGPTでブレインストーミングをしたりといった実験は、個人や部門のレベルでは学習と生産性のメリットをもたらしうる。しかし、それらは通常は構造化も測定もされず、大規模な成果を生むことはめったにない(企業がいまだにAI投資の利益面の効果を実感していない一因は、ここにあると筆者らは確信している)。
生成AIから測定可能なビジネス価値を引き出すには、リーダーは自由な個人的実験から、構造化され全社的に連携した導入へと移行しなければならない。このようなツールは、焦点が一つの事業部門のみであれ組織全体であれ、生成AIの自由度の高い能力を、特定のユースケースに対応するアプリケーションへと変換する。これには企業用のナレッジアシスタント、カスタマーサービスエージェント、データの取り込み・検証システム、規制遵守の自動監視、大規模なマーケティングコンテンツの生成エンジンなど、さまざまなものが含まれる。
筆者らはAIとそのビジネス活用を研究する研究者であり、とりわけ大規模組織におけるプロセスマネジメントをAIがどう支援できるかについて探索してきた。実際の企業が個人レベルでの実験を超えて、エンタープライズAIツールの構築へと移行する過程を観察する中で、それを実現するには企業がデータインフラと協働の両方に対するアプローチを変える必要があることがわかってきた。本稿では、それぞれのベストプラクティスを提示し、エンタープライズ志向への転換を成功させながらエージェント型AIも見据えている企業の実例を紹介する。
個人レベルのAIからエンタープライズAIに移行する
構造化され全社的に連携したAIアプリケーションには、その仕組みから生じるいくつものメリットがある。複数のシステムと統合されることでデータの幅が広がり、推奨と出力の質が向上する。同じツールが何千人もの利用者を支援できるため、スケール化を実現しやすい。出力は標準化できるため、一貫性が高まる。使用状況がより厳密に管理され監査可能となり、ガバナンス上のリスクが減る。コスト、スピード、品質、イノベーションなどへの影響が厳密に評価されるため、より多くのROI(投資利益率)を生む可能性も高まるだろう。測定を通じて、欠陥への迅速な対処やコスト調整が可能になるからだ。
一部の企業はすでに、このようなシステムの構築に向けて必要な方向転換を遂げている。一例としてジョンソン・エンド・ジョンソンは2025年の初めに、個人的実験の大半は測定可能なビジネス価値を生んでいないと結論を下し、これ以上リソースを投入しないことを決めた。代わりに、同社の戦略的優先事項への技術活用を焦点とする、少数の全社レベルの生成AIプロジェクトのみを優先するようになった。医薬品開発、人事方針へのアクセス、医師とコミュニケーションを行う営業担当者への支援、サプライチェーンリスクの特定と軽減である。
コカ・コーラも同様に、新たなマーケティングコンテンツの開発など、大規模で全社的に連携したAIプロジェクトに注力することを決めた。同社が事業を展開する世界の180カ国・130言語向けに、20種類の専有マーケティング資産を1万の異なるバージョンにカスタマイズするために、生成AIを活用している。
しかし、エンタープライズシステムをより有益にする特性は同時に、構築を困難にする要因でもある。複雑なシステム間で高品質なデータを統合し、データフローを連携させ、出力をビジネスと整合させることは非常に大きな課題だ。AIの取り組みが本番導入へと至る割合の低さに言及した最近の調査結果は議論を呼んでいるものの、企業がこれらの面で苦労しているのは間違いない。
自社のデータフローをエンタープライズ用途向けに準備し、プロジェクトを通して事業チームと開発チームがどう協働するのかに焦点を当てることで、これらの課題に対処しやすくなる。以下がその方法だ。
データの準備態勢を整える
生成AIに対する組織的な準備は、非構造化データとその流れの可視性を高めて構造化し、戦略的に優先順位をつけることから始まる。たとえばノースウェスタン・ミューチュアルのナレッジアシスタントは社内の専有データを統合するが、そのデータは事前に体系的かつ信頼できる形でキュレーションと更新が行われ、検索可能な状態に整えられている。
しかし、ほとんどの組織はこの数十年にわたり、構造化データに焦点を合わせてデータの品質と管理に取り組んでおり、LLM(大規模言語モデル)を特定のビジネス課題に適応させるために必要となる非構造化データには対処してこなかった。









![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)